
半幅帯でお尻も隠せてスッキリ粋な後見結び風
映画やドラマの中で見た素敵な帯結び、自分でも試してみたいと思ったことはないでしょうか?
1953年の映画「祇園囃子(ぎおんばやし)」の中で、踊りのお姉さんがよく結んでいるような帯結びで、「後見結び」という結び方があります。映画の中では六寸帯のような帯で結んでいるようでしたが、半幅帯で結んでいるシーンもありました。
帯結びでお尻が隠れてスッキリ見えるし、細かく長さを気にしなくても、すごく簡単に楽に結べる方法なので、ぜひ、試してみてください。
今回は、長尺の半幅帯を使ってお伝えしていきます。
※説明の中で、女将が使っている帯は、博多織の小袋帯で長さが4m30cmぐらいあります。
初心者でもテキト―でも簡単に結べる半幅結び
1)帯を腰にあて、手先を膝につくぐらいの長さで取ります。
2)帯を内側に斜めに折りあげて体の真ん中あたりでさらに外に折ります。こうすると、自然に帯の輪が下になります。
3)折り上げた部分をクリップで帯板に留めます。後で帯板を挟みこむ場合は、折り上げた手先をクリップで衿に留めます。
4)帯を体にひと巻きしたら、タレ側を持ち、体の脇でクッと締めます。
締めすぎると苦しくなるので、その日の体の調子などによって、締める具合を調節しましょう。たとえば、外を歩く時間が多いのであれば、キュッと締まってると気持ちが良かったり、長く座る時間が多いのであれば、少し緩くしておいた方が楽だったりします。ただ、その体感は人によって違うので、ご自分で試してみると良いと思います。
5)帯を締めたら、手先を下に落とします。その上にタレ側を持ってきて、手先側とタレ側を体から離すように引いて持ち、タレ側を手先側の下から上に通します。
6)タレ先を上に引いたら抜ききらずに、お好みの長さを残したまま、手先側とタレ先側をそれぞれ持って、キュッと締めます。
7)手先側とタレ先側が重なっている山をクリップで留めます。
博多織の帯など滑りやすい帯の場合、クリップで留めておくと緩みません。帯結びで見えなくなるので、留めたままでも大丈夫です。
8)タレ先側を下に落とし、重なっているタレ先側の帯をズラして形を整えます。
重なっている帯をズラして幅を出すことで、帯にボリューム感が出るので、身長の高い方や、お尻や腰幅が気になる方には、お尻が小さく見える効果が期待できます。
9)タレ先側を上にあげて肩にかけ、手先側を上に折り上げたらクリップで留めて広げます。
10)タレ側の帯を下におろしたら斜め内側に折り上げます。タレ先が長い場合は、折りたたんで長さを調節しましょう。
11)手先を返してタレの中に通します。
12)手の上を通るように帯締めを締めます。帯締めが結びにくい場合には、先に仮ひもで帯を押さえてから帯締めを通すとやりやすくなります。帯締めは、しっかりめに締めましょう。
13)全体のバランスを見ながら、形を整えていきます。
たとえば、タレ側の先が出ている方向を変えたり、タレから出ている手先の長さを調節したり、お好みのバランスになるように形を整えます。
14)帯結びを背中に回して完成です。
たとえば、手先を長めにとったり、タレ側で折り返した部分の大きさを小さくするなど、大きさや形が変わるだけで、全然違う表情になって印象も違ってきます。結びが平らなので、背中を押し付けるような車や電車の移動でも潰れることはありません。
きもの初心者でもテキトーでも簡単に結べて、お尻がスッキリ見える効果も期待できる「後見結び」風アレンジです。身長の高さや腰幅に合わせて、手先やタレを調節してみてください。
女将が出会った昔の映画の話から帯結びの説明に繋がっていく女将の動画はこちらをご覧ください。
【テキトーなのにお尻も隠せてスッキリ粋に!半幅結びで後見結び風アレンジ】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
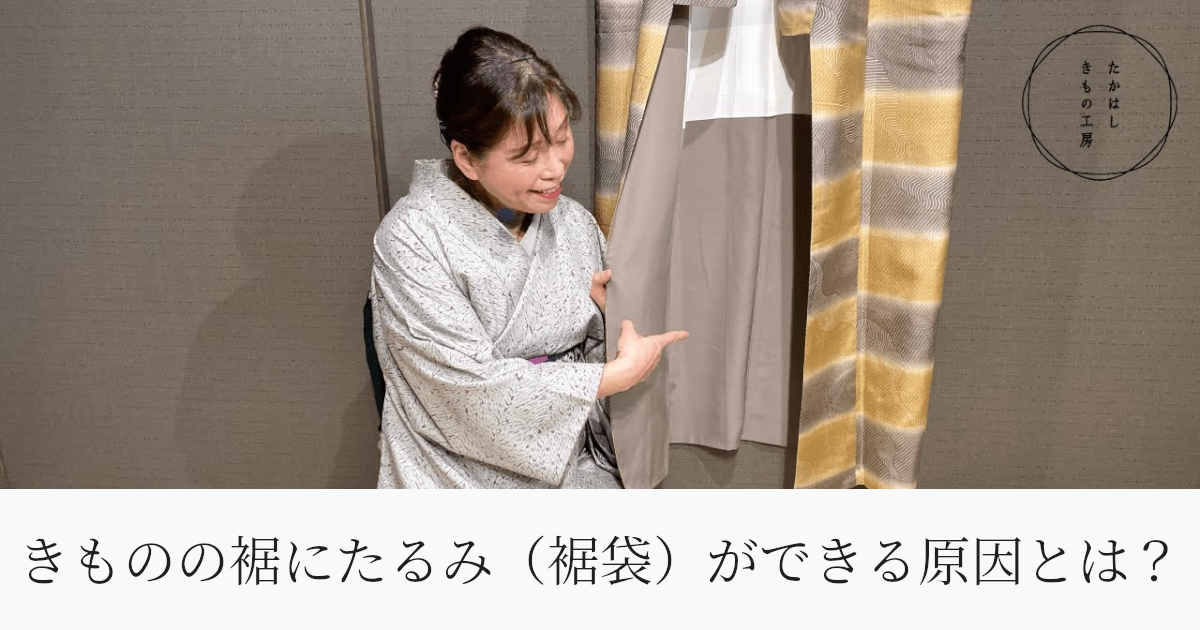
きものの裾にたるみ(裾袋)ができる原因とは?
袷のきものをきもの用ハンガーなどにつるしたときや、着付けで腰ひもを結んだときに、きものの表地の裾にたるみができた経験ありませんか?
このたるみを「動画では表袋(おもてぶくろ)以下同」と言いますが、特にやわらかもののきもので目立つと思います。
実は、この「表袋」は仕立てる時点でかなり回避できるにもかかわらず、その対策がされていない場合が多いようです。そのため、きものに袋が入ってしまうのは仕方がないことと思っている方も少なくないかもしれません。
今回は、「表袋」ができてしまう原因と「表袋」ができたきものの直し方の工夫をお届けしていきます。
もしかすると、きものを平らな場所に置いてピターっと表も裏も平らな状態で、きものをつるしてもピターッと「ゆるみ」がない状態がきれいな仕立てと思われていませんか?
一見、表も裏もピタピタッと合っているのがきれいな仕立てと思われがちですが、実は、着にくいんです。では、その理由をご紹介します。
裏地の「ゆるみ」には理由があった
まず、女将の訪問着を例に見ていきましょう。
表地は刺繍がされている生地なので、刺繍部分が裏地に響いてでこぼこしていますが、裏地を見ると全体に「ゆるみ」が入っています。
約10年前に仕立てたきもののため、経年による多少の縮みがあると思いますが、仕立ててすぐの頃はもっと「ゆるみ」がある状態だったと思います。
たかはしでは、裏に「ゆるみ」を入れる仕立てをします。裏に「ゆるみ」がなくピタピタの状態だと、表に袋ができてしまい着にくくなってしまうためです。
たとえば、やわらかものの縮緬の場合、表地の方が裏地よりも生地がずっと重いため、「ゆるみ」を入れずに仕立ててしまうと、着たときに裏地は体に沿うように付きますが、表地はすべって落ちるため「表袋」ができます。
和裁師さんは、その落ちる度合いや、経年による収縮や湿気による収縮を計算に入れて、裏地に「ゆるみ」を入れます。
そのため、仕立ててすぐの状態できものをつりさげると裏に「ゆるみ」がありますが、それが着やすいきものなのです。
逆に、着にくいきもの、必ず「表袋」になるというきものをお見せします。
実は「ゆるみ」がないきものは着にくい
この画像にあるようなきものを着ると「表袋」になります。
裏地に「ゆるみ」が全くありません。ピターッとしていて、むしろ表地に膨らんでいるぐらいになっています。
もし仕立て上がりがこのような状態だった場合には、仕立て直しを依頼しても良いと思います。
ただし、紬系のきものは生地が軽いので、やわらかものに比べると「表袋」になりにくいです。たとえば、大島紬の場合、表地は収縮しにくいのですが、それに比べると裏地が経年で収縮するため、それを計算して余計に「ゆるみ」を入れて仕立てたりします。
生地には経年収縮があるので、仕立てを工夫しても表袋になってしまうことはありますが、きものの着やすさを考えると、仕立てるときから「ゆとり」がなくピタピタに縫ってもらうのはできるだけ避けた方がよいと思います。
ぜひ、今後きものを仕立てるときに、お願いするお店の方に、裏地に「ゆるみ」を入れてくださいと伝えると、そのように仕立ててくれると思います。
一時期、きものを着ない時期に「ゆるみ」は要らない、ピターッと紙を畳んだように縫うことが良しとされたときがあって、「ゆるみ」を邪魔なものと考えていたのかもしれません。ただ、実際にきものを着だしたら、とても着にくいことがわかってきてたのではないでしょうか。
裏地に「ゆるみ」を入れて仕立てるというのは、きものを日常的に着ていた先人たちの大事な知恵ですね。
きものの裾の「たるみ」を解消する方法
すでに「表袋」になっているきものを着付けるには、腰ひもを締めてとめた後に整えることで、袋になった部分を解消することができます。
※腰ひもを締めて腰ひもに嚙んでいる生地をすべて引っぱり出した後に行います。
1)腰ひもの上の生地を触って、表地と裏地の二枚があることを確認します。
2)表地一枚だけをつまんで裾と一緒に持ち上げて引っぱります。
3)袋になっている部分の「たるみ」がなくなるまで、少しずつ引っぱりながら整えます。
※白枠内が袋を調整する前の状態です
このように着付けのときに調整すればよいとはいえ、着るたびに調整するのは大変です。
この裏地の「ゆるみ」に対しての知識が一般的になっていくと、きちんと着やすいきものを縫ってくれる和裁師さんが増えていくと思いませんか。
きものを仕立てるとき、裏の「ゆるみ」がある意味についても意識してみてください。
さまざまなご意見あることを承知の上で配信をきめた男気あふれる女将による動画はこちらをご覧ください。
【実は…あなたのきものにもあるかも!?きものの「裾袋」って何?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

きもの業界三大女将!?座談会・季節の移り変わりはどうすればいい?
きものを楽しむ中で、季節によって着分けるとき、たとえば、ネットの動画で見聞きした情報とお店で聞いた情報と、身近な人から聞いた内容とが、すべて微妙に違っていて、どれが正しいの?どうすればいいんだろう?と迷子になった経験はありませんか?
誰もが一度は経験されたことがあるのではないかという、季節の移り変わりでのきものの装いについて、きもの業界三大女将が本音で語っていただきました!
豪華ゲストお二方が気仙沼に
きもの英…

ここちよい着付けのために、補整する?しない?
きものを着付ける時に、補整をするのか、しないのか、ちょっとネット上を検索しただけでも、「補整は絶対した方がいい」とか「昔は補整してないのだから補整しなくて良い」とか、さまざまな意見が見られます。
たとえば、補整をせずに着る方たちの意見の中に、補整なしで着ると体型に沿って自然で良いという意見もあります。
一方で、そういった意見を聞いた方が、「私、補整してて、すみません」のような肩身の狭い思いをしている方がいるかもしれません。
着付けをするのに補整をするしないは、個人の自由なのですが、ここちよい着付けをするために、補整をしている方でも意外と知らない、たかはし流補整のイロハをお届けしていきます。
これから着付けを習う方や、習いたてというきもの初心者さんにも、ぜひ知ってほしい内容です。
「すっきり見える」だけじゃない補整をする理由
たかはしでは、「補」い「整」えるという字を使って「補整」をお伝えしています。
補整をする・しないは、どちらが上等かということではありません。
たとえば、自分にとって理想の着姿にするためや、自分にとって着ごこちのいい着付けに近づけるため、着付けの手間を減らしたいためなど、自分の好みに応じて、補整をする・しないを選ぶのが良いでしょう。
ちなみに、女将自身が「補整する・しない?」を聞かれたら、補整をする派です。
まず、補整をする目的として、全体的なバランスで考えた時、着姿がすっきり見えることです。きものを着るみなさんも望んでいることでしょうし、実は、すっきり見えるイコール着くずれしにくいんです。
たとえば、上半身が細くて、下半身にふわっと膨らみが出る体型をされている方。中年以降になると、特に腰まわりに浮き輪のようにお肉が付いてきやすいです。それ以外でも、上半身やウェストはすごく細くてお尻に向かって張ってきて、下半身にボリュームが出やすい骨格診断でウェーブ体型と言われる方がいらっしゃいます。
ウェーブ体型の方が、ウェストに合わせた上半身の着付けをすると、下半身のボリュームが強調される形になり、パーンとお尻が張って見えてしまいます。
この場合、ウエスト補整を入れることでお尻が小さく見える効果が得られます。
きものの生地は、タテ糸とヨコ糸が真横×垂直に重なって織られています。この生地目を意識して体に沿わせるようにすると、シワがよりにくくなります。
たとえば、裾を下すぼまりにしたい時、ウエストが細くてお尻が張っていると、お尻の部分で生地が引っ張られて歪みができます。そのため、最初は下すぼまりになっていても、歩くことで生地に力がかかっていくと、裾が開いてきてしまいます。
このように、お尻や太ももに張りがある体型の場合、裾が広がりやすいのです。生地の力にあらがって着付けているので、当然着くずれやすいです。
ウエストをお尻や太ももの張りに合わせて補整を入れ、できるかぎり真っ直ぐ寸胴にすると、生地がピタッと体に沿うようになります。
そのため、下すぼまりになった裾に対して、そのまま生地が上に上がるので歪みができにくいです。すると、生地の落ち着きが良くなり、着くずれしにくくなります。
さらに、一番気になるお腹の肉や腰肉は、帯を締めた後にぽっこり下腹として出てきてしまいがちです。たとえおはしょりを1枚にしてきれいにしても、立ち座りで腰に帯がぶつかって動くことで、上半身がブカブカと緩むことでも、着くずれに繋がります。
また、長い帯板を使うとどすこい体型に見え、帯板が腰にぶつかって着くずれてしまう場合があります。帯は細い部分に滑って移動していくので、帯と一緒に生地も動き、上半身の生地が緩みブカブカになって着くずれてしまいます。
お腹まわりのお肉が浮き輪のようにつき始めると、お肉を押さえこみたい気持ちになりますよね。
ただ、腰まわりのお肉を押さえ込んだとしても、ウエストが細いままだと腰まわりが張った状態になってしまいます。だから、ウエストに補整を入れていくと良いのですが、補整を入れれば入れるほど、太って見えることを心配されると思います。
そこで、補整の詰め物を多用せず、自分のお肉を持ち上げて、お肉を動かす、という新発想の補整を実現してくれるのが、「満点腰すっきりパッドスキニー」です。補整のための詰め物が少なくても補整が簡単にできるし、一発で補整が決まるという点も大きなメリットです。
パッドスキニーを、一番くびれているウエストだけ付けるのではなく、かならず骨盤にもかかる形でお肉をキューッと締めるように付けることで、お肉が動いていきます。(スポーツをされてきた方で筋肉質な方の場合、筋肉は動きにくいのでその上に補整を足すこともあります。)
自分のお肉がウエストの補整として入っていくため、パッドスキニーを使うとサイズダウンすることもあります。
仮に、補整は一切、付けなくて裾が広がってしまっても全然良いですという場合、それはその人の個性だと思いますし、ひとつの着方でもあると思います。
たとえば、補整を何もしなくても寸胴な体型ですという方もいますし、腰の曲線がなく真っ直ぐな方もいますので、補整が必要なのかどうかは、その人の体型にもよります。
下半身の補整を例に、お伝えしてきましたが、胸元を寄せて上げることも上半身の補整のひとつです。
胸のお肉が横に広がるような感じがする、下に落ちてしまうという場合、補整でお肉を上げることができたらすっきりと見えます。もし、胸のお肉をつぶして補整した方が良いと感じているのであれば、それが良いと思います。
かならず、こうしなければならない、ということはないのです。
大切なきものにも補整が効く理由
着姿や着ごこちに加えて、補整をすることは、きものを守ることにも繋がります。
タオルや補整アイテムを使用すると、その分、吸水性が上がるので、汗がきものに移ることを軽減することができます。
もちろん、補整をしたことで暑くて汗の量が増えるという側面もあります。
以上のことから、補整をする意味は大きくふたつです。
ひとつは、生地をすっきり体にまとわせることで着くずれを防ぐこと。もうひとつは、きものを守ることです。
着付けをするのに何を選び取るかは人それぞれです。これらふたつを考え合わせて、たとえば、補整を入れる量を季節によって調整するなど、考えると良いでしょう。
補整をする・しないは、上も下もなくフラットに考えて、自分の体に聞いて、選んでいくと良いと思います。
すべては自分の感覚と自分で選び取ったものを信じて、その上でここちよい着付けをされることで、もっときものを楽しめるようになると良いですよね。
ここちよい着付けをするために、女将の愛と理論と情熱がつまった動画はこちらをご覧ください。
【きもの初心者さんにも知ってほしい!ここちいい着付けの為に!補整ってしないとダメ?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

着付け師KOYANOに学ぶ目からウロコの着付けポイント
日常的に着物を楽しむなら、
少しでも着付けを楽に時間を短くしたい
着崩れないようにしたい
ここちよく着ていたい
と、思いますよね。
そこで今回は、日本舞踊専門の着付をされている着付け師のKOYANOさんから、着付けについてのコツを教えていただきました!
女将が着付け師KOYANOさんと出会ったら…
着付け師KOYANOこと古谷野貢さんは、現代着付けに舞踊着付けの技術を盛り込んだ「一日中着ても、カラダが楽で崩れない着付け」を口コミと紹介のみで岡山県倉敷市から全国を飛び回っている着付け師さんです。
他の着付け師さんと異なるのは、一般の方々の着付けを行うだけではなく、日本舞踊専門の着付けを行う衣裳方として各流派の舞台裏でご活躍されていることです。
たかはしの肌着に興味をお持ちになり、倉敷市から気仙沼までいらっしゃってくださいました。
※オリジナルブランド本京友禅「明和美染(みわびぞめ)」を展開する「創作きもの明和美」の代表も務められています。
実際に、古谷野さんと女将が話をしていると、肌着や補整、着付けについて話が尽きることなく盛り上がったそうですが、その中で女将が再確認できたことや目からうろこのテクニックをお伝えいたします。
楽で着崩れしない着付けの共通点とは?
日常的にきものを楽しむために、体が楽で着崩れしにくい着付けは、誰もが望むことだと思います。
そのための着付けとして、女将は、下半身は横糸の力を借りて、上半身は縦糸の力を借りて体に生地の目をフィットさせるように着付けるということをずっと言い続けてきています。
生地の目を意識して着付けると、生地の面で体が支えられるようなここち良さがありますし、生地が体に沿うようになるので着崩れもしにくくなるのです。
▼詳しい方法は、こちらの記事をご覧ください
「L字の法則」で着崩れ知らず、体を支えてくれる着付けに
女将がこの論理にたどり着いたのは、子どもの頃に習っていた日本舞踊での経験からでした。
とにかく下半身を締めたいということと、帯まわりをきつく締めるのは嫌なので、腰まわりだけを引き締めたいという強い願望があることを自覚していました。
なぜなら、それが一番ここちよく着付けることができることを、日本舞踊での着付けを通して肌で体感していたからです。
実際、古谷野さんの着付けを女将が体験した時、生地を体に当てる古谷野さんの手つきが女将が長年考えていたことと共通点がいくつもあり、「L字の法則」はまさにぴったり一致したのです。
さらに、古谷野さんのテクニックの中で、すごく有益な情報で女将がとても驚いたやり方がありました。それは裾よけのつけ方なのですが、普段の裾よけのつけ方を思い浮かべながら読み進めてください。
キレイで時短な裾よけのつけ方
裾よけを自分でつける時もそうですし、人につけてあげる時も次のようなやり方でつけているのではないでしょうか。
1.先に上前の位置を決めた後に下前を体に巻きつける。
2.上前を体に巻きつけた後、上前の下になった紐を外側に引き出し、紐を巻きつけて結ぶ。
古谷野さんの裾よけのつけ方は、この方法とはまったく違っていたのです。
《人に裾よけをつける場合》
1.着付ける相手の体の中心部分に裾よけの左右の力布を合わせて持つ。
2.裾よけを持っている手を右側にパタンと倒す。
3.紐が外側に来るので、そのまま体に沿って巻いていき、紐を巻きつけて結ぶ。
《自分で裾よけをつける場合》
1.体の真ん中で裾よけのセンターを決め、左右の力布を合わせて左手で持つ。
2.裾よけを持った手を左側にパタンと倒す。
3.紐が外側に来るので、そのまま体に沿わせて裾よけを巻いていき、紐を巻きつけて結ぶ。
裾よけを巻きつけた後で紐を抜くやり方よりも、ゆるんだりズレたりすることなく仕上がりがキレイになりやすいですし、紐を抜くという手間も無くなります。
これはほんのちょっとしたコツですが、着付けする上でのストレスがひとつ無くなったことになります。紐で巻きつけて結ぶタイプの裾よけを着る時は、同じやり方で着られるので、ぜひ試してみてください。
女将による目からウロコの着付け術はこちらの動画をご覧ください。
【着付師KOYANOに学ぶ!目からうろこの着付け術!着付け師さんから教わるポイント】
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

挟む力が弱くなったコーリンベルトの活用術
留め具の挟む力が弱くなってしまったコーリンベルト(着付けベルト、きものベルト)を、そのまま捨ててしまうのはもったいないと思ったことはありませんか?
コーリンベルトは、ゴムの劣化があるため10年も20年も使えるアイテムではありません。
なぜかというと、留め具の接合部分に使用されているゴムが硬化すると、きものを挟みこんで押さえる力がなくなってしまうからです。
もしコーリンベルトが使用中に外れるようになった時は、使用寿命を迎え、買い替え時がやってきたのかなと思ってください。
ただ、留め具の挟む力が弱くなった時でも、平ゴムはまだ使用できることが多いです。この平ゴムを活用して三重仮ひもにリメイクする方法をお届けします。
※コーリンベルトはコーリン株式会社が開発した着付け用の補助アイテムです。コーリンベルトは商標登録された商品名で、一般名称にすると着付けベルトやきものベルトですが、この記事ではコーリンベルトでお伝えしていきます。
裁縫が嫌い・苦手な方も作れる「三重仮ひも」
リメイクするなんて、裁縫は苦手だし、むしろ嫌いだしという方もいらっしゃるかもしれません。でも、ご安心ください。ズボラがきものを着て歩いていると言われる女将も簡単にできちゃった方法です。
<用意するもの>
使用寿命になったコーリンベルト
手ぬぐい(不要な薄手の帯揚げでも○)
糸切りばさみ
裁ちばさみ
縫い針
縫い糸
ものさし
クリップ※ミシンがある場合にはミシン
<作り方>
1)コーリンベルトの平ゴムの両端を糸切りばさみで切り落とし、留め具を外します。
2)真ん中にある調整具を平ゴムから抜き取ると、一本の平ゴムになります。
3)平ゴムを三等分に折り、糸切りばさみで切って、同じ長さの三本の平ゴムにします。
4)手ぬぐい(以降、布と表記)を縦に半分に折り、裁ちばさみで半分の幅に切ります。
5)切った布の一枚を半分に折って、筒状になるように端を縫います。
もう一枚を同じように縫い、筒状に縫った布が二本できます。
※ミシンをお持ちの場合には、ミシンで縫います。
6)針に40㎝ぐらいの糸を通し、筒状になった布の片方の端を、ギャザーを作るために縫います。
7)袋部分を下に、縫った部分を上にして使います。
8)等分した三本の平ゴムを揃えて、縫った布の中に入れ込みます。
9)縫った糸を引き絞ると、ギャザーになります。
10)布の内側に入れた平ゴムの端と布端を揃え、糸がある限り何度か往復し、しっかりと縫いとめます。
脇は糸で巻くように上から下にからげるように縫うことで、丈夫になります。
最後にしっかり玉止めをします。
11)ある程度、平ゴムを手で奥に入れ込むようにした後、ものさしを使って、ひっくり返します。
ひっくり返すと、片側が完成です。
12)反対側も同じように縫うために、平ゴムが付いた布をもう一方の筒状の布の中に入れ込みます。平ゴムが付いている側を長めに取って折り、クリップでとめるのがポイントです。
クリップでとめた部分にものさしを差し込み、中に入れ込みます。
平ゴムを布端に残した状態で、布を抜き切ります。
13)8~10と同じように、布端と平ゴムを揃えて縫いとめます。
14)布をひっくり返して、完成です。
実際にご自身の体で結んでみて、長さを調整してください。
手ぬぐいで作ると綿素材なので、摩擦により生地が動きにくく仮結びした時も止まりが良いです。
コーリンベルトの留め具のゴムが劣化している状態で使っている場合、平ゴムが丈夫なのでもったいなくて捨てられないという方もいらっしゃるのかもしれません。
ゴムが劣化してしまったコーリンベルトも、このように三重仮ひもに活用できると思えば、新しいものに替えやすくなりませんか。
衿元の着崩れを防ぎ、美しい着姿にするための重要なアイテムのひとつなので、使い勝手の良い留め具の挟む力が効く新しいものを使っていただければと思います。
お裁縫が嫌い・苦手な方も「私にもできる!」と思えちゃう女将の動画はこちら。
【使い古したコーリンベルトが三重仮ひもに?!】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
