
普段使いにおすすめの草履・下駄はズバリこれ!
下駄は底の形と鼻緒の裏の生地で選んで!
今回は、普段使いの足元のお話をしたいと思います。
まずは夏といえば、下駄。下駄といえば2枚歯でからんからんと音をさせてちょっと内股でつつっと歩く姿は憧れだけど、靴に慣れてしまった私たちにはちょっとハードルが高い履物かもしれません。
そういう点で右近下駄はつまづきにくいので、おすすめです。今は、まったく歯のないものも増えています。一脇さんの木草履も、そういう下駄の一種でしょうね。高さもなく、気軽に履けるものです。
歩き慣れていない方、転ぶのが怖い方には底がフラットな船底下駄をおすすめします。歯がないのでひっかかる不安がなくなりますよ。
底の形もそうなんですが、実は気にしてほしいのは「鼻緒の裏の生地」。必ず触ってみてください。
やっぱり浴衣のときは素足に下駄が清々しくて素敵だけれど、履き慣れていなくて皮がむけちゃった、なんていう経験をした人もいるのではないでしょうか。
そうならないためにも、鼻緒の裏に使われている別珍(べっちん)という生地が、なるべく肌あたりが柔らかいものを選んでください。手を入れて触ってみるのとわかります。
それでも慣れていないと痛くなってしまうこともあるので、裸足で下駄を履いておでかけするときには絆創膏を5枚くらい持ってでかけてください。ポイントは「皮が剥ける前に、痛いと思ったらすぐにそこに貼る」です。我慢しないで、すぐ貼りましょう。
普段草履の女将おすすめ3選
礼装のときの草履は、台の高さがあることが大切です。また白っぽいもの、金銀などのキラキラ感があると改まった感じがあり、礼装向きになります。
普段使いの草履はそうでないもの、ということになります。台が低くて楽なものが主流です。台が高くても、色使いが粋だったりすればそれはおしゃれ用ですね。
また鼻緒が太いものが流行したときがありました。鼻緒が太いほうが、靴のようにずぼっとのめって履く人にも楽です。
素材の問題では、合皮か本革かという選択もあります。以前は合皮の草履はリーズナブルで、1万円くらいでいろんな色で楽しめたり数を揃えたりできたものなのですが、最近合皮の値段が上がっているのです。2万円以上になっていきているものも多いので、だったらあと少しプラスして本革の草履にしてもいいのではないかと思う理由があります。
本革草履のおすすめポイント
まず「汚れや傷がつきにくい」ということ。ついた汚れも手入れをすればすぐにとれます。合皮は足の跡とかもつきやすく、なかなか汚れがとれにくいものが多いです。また合皮はちょっとぶつけたりするとすぐ傷になってしまいますが、本革は傷もつきにくい。丈夫です。
そして「長持ちする」ということ。実は合皮は水分や空気を通しやすいのか、中の芯材と沿いが悪くなってしまうのか、変な音がしてだめになってしまった経験を何度もしたことがあります。台が割れてしまったりもします。
本革のものはそれがなく、30年以上履いているものもあるくらいです。長い目で見ると、お得だと感じています。
日常使いのものこそ、本革の草履をおすすめしたいです。逆にときどきしか出番のない礼装様はむしろ合皮という選択もありかもしれません。
本革の草履にもデメリットはあります。それは「底が滑りやすい」ということ。宣伝になってしまいますが、たかはしきもの工房では「守さん」という両面テープではりつけるだけで底を滑りにくくし、また鼻緒のすげ跡から水が染み込むのを防ぐ商品を作っています。これがほどよく滑らず止まりすぎず、歩きやすい優れもの。おすすめです。
カレンブロッソもやっぱり便利!
日常使いの草履のおすすめはもうひとつあります。それは「カレンブロッソ」です。台がEVAという素材でできていて、雨や雪にも強くて滑りにくく、長時間立っていても絶妙なクッション性があって疲れません。台の側面が汚れても、その部分を洗えば綺麗になります。
難点は鼻緒が取り替えられないこと。一部取り替えられるものもありますが、靴などを履き潰す感覚で履く方も多いのではないでしょうか。
女将のマイブーム「雪駄」
最近の女将が普段使いに愛用しているのが、男性用の雪駄。実はこれがらくちんなんです。小さい台を選べば、女性でも履けると思います。
たかが履物、されど履物。足元のおしゃれはとっても大事ですよね。そしてやはり「歩きやすい」ということが大切です。そんなに安いものでもありませんから、ぜひ後悔しないよう草履や下駄を選んでいただけたらと思います。
あちこち回り道をしながらしっかり草履や下駄のおすすめポイントについて熱く語っている女将の動画はこちらです。
【後悔しない!女将的、草履・下駄の選び方&おすすめ紹介】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
紹介した商品
守さん【つま先用…

ズボラさん向け!しつけ糸の簡単な取り方
しつけ糸はどうしてついているの?
新しい着物を購入したとき、「しつけ糸」がついていますよね。
しつけ糸は、取ってから着るもの。
どうせとってしまうのに、なぜついているのでしょうか?
着物は仕立て上がってから、寝押しや座り押しなど体の重みで優しく折り目をつけていくものなのです。これもSDGsの考え方とも通じるかと思うのですが、アイロンやコテでしっかりと折り目をつけてしまうと、仕立て直すときに折り目が消えなかったりします。
また、アイロンなどできちっとプレスしすぎてしまうと、生地もふっくら感がなくなり、ペラペラな印象になってしまうことも。つぶれすぎず、ふわっと絶妙にしかも取れない折り目を仕上げるためにしつけが必要なのです。
しつけがあることで、着物がずれることなく折り目がつきキレイに仕上がるというわけです。
意外と重要な役目がある「しつけ」。
なくてもいいんじゃない?とおっしゃらず、これがあるから着物がキレイに仕上がっているんだな〜と思ってあげてくださいね。
女将流:しつけ糸の取り方
袷の場合ですが、袖と裾にしつけがかかっています。
しつけは、地域やお店、仕立師さんよってかける場所が違うことも。衿にかけることもあります。
袖のしつけの取り方
袖の部分はたいがい袖口をぐるりと囲んで、1本の糸でしつけされています。
たかはしきもの工房の場合は、玉結びを外に出して外しやすいようにしています。以前は玉結びが見えないようにする=袷の内側にすることが美しいとされていたのですが、それだと糸の端がどこにあるかわからず、取りにくいということで、このようにしてあります。
糸の端が見えないようにされている場合はハサミで切ってください。
袖口の付け根のところに糸の端があります。この玉結びのところ(糸の端)を持って、静かにひけなくなるまで引っ張ります。
引けなくなったところで、指で抑えてプチッと糸を手で切ります。
ハサミを使わないので布を傷つける心配もありません。
あとは、おなじようにするか、指で糸を引き抜いていけばとれます。
袖口の付け根のところは、かがってある場合もあります。たかはしでは、そこがかがってあるとしつけをとりにくい、ということで今はかがってありませんので、とても取りやすくなっています。
袖の丸みの部分も、かがってあることが多いです。たかはしでも、この丸みをキレイに抑えるため、この部分はかがってあります。
無理に引っ張らないで、かがってある部分の手前で糸を一旦切って、そっと引き抜けばかがってある部分もするっと取れますのでお試しを。
あとは、袖の袂の部分の玉結びをひっぱれば、するっと糸が抜けて袖のしつけ取り完了です。
端のしつけが見えないように止めてあったり、返し針をしたりしてある場合には、無理をして引きちぎるより、ハサミで糸を切ってとったほうが、布を痛めないかと思います。
裾のしつけの取り方
裾も同様にしつけ糸をとっていきます。
襟先の下のところに糸の端がありますから、玉結びを持って糸をひっぱり、ひけなくなったところで指で抑えて、糸を切っていきます。
中に玉結びをしてあって糸の端が見えないときは、最初もハサミで切ってくださいね。
裾は衽(おくみ)の角などかえし針をしてある場合もありますので、そういう場合は袖と同じように一旦そこで押さえて糸を切り、無理に引っ張ったりしないでください。
反対側の衽の角まできたら、あとは逆に襟先の玉結びを探してそれを引けばしつけ糸がするっと抜けます。
これでしつけ糸取りが完了です。
いろんなやり方があると思いますが、ズボラさん向きのしつけ糸の取り方のご紹介でした。
ぜひぜひ実際にしつけ糸を取っているところ、女将の動画をご覧くださいね!
【しつけ糸のいろは&取り方】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
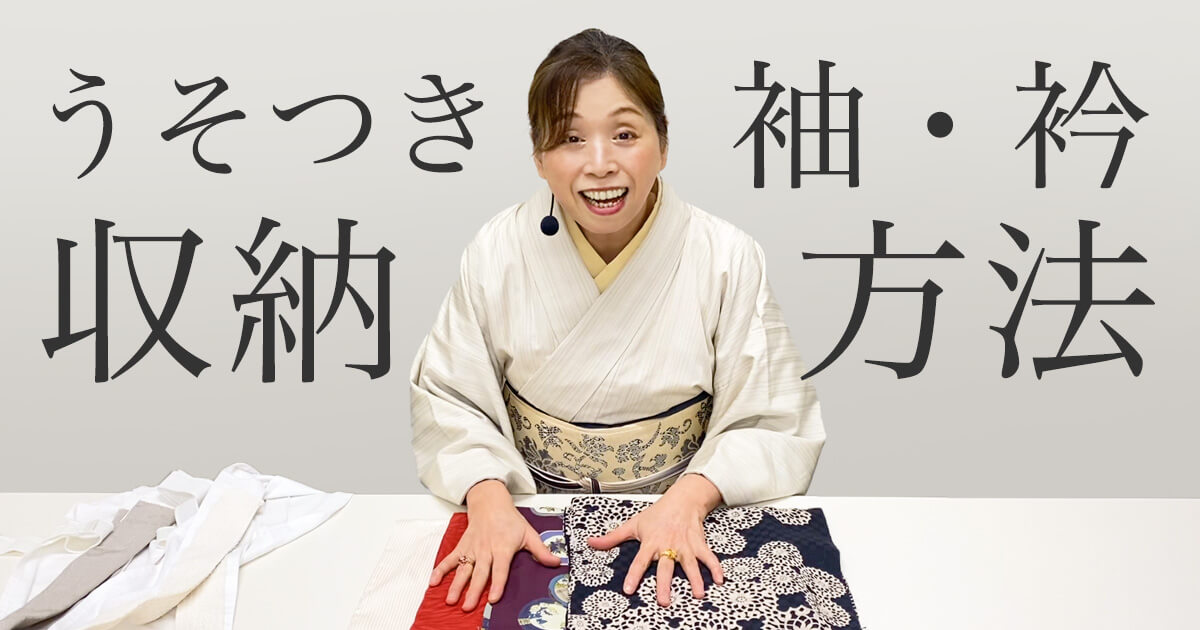
うそつき袖とうそつき衿の収納方法
今回は、収納のお話です。
しかも、うそつき袖とうそつき衿という、たかはしきもの工房のうそつきご愛用者『たかラー』さんにお役立ちな収納です。
着物や帯はいろんな収納方法をご存知かと思いますが、今回もマニアックなお話をお届けいたします。
うそつき袖はスカートハンガーで!
まず、うそつき袖。
たかはしきもの工房のものに限らず、うそつき袖をお使いの方も多いと思います。
箪笥の中に、畳んで入れると折ジワが気になったり、広げて入れると場所も取るし取り出しにくい……。何げに収納しづらいアイテムです。
毎日うそつき衿と袖の女将が編み出した、選びやすくてさっと取り出せてシワにもならない収納方法がスカートハンガーを使う方法です。
スカートハンガーは、4連とか5連になっているものだとたくさん収納できて省スペースに。止めるピンチがやわらかいものが、生地を痛めません。
袖山を上にして、マジックテープがある側をピンチで止めると、マジックテープが他のものにひっかかったりしづらくなるのでおすすめです。
女将は、作り付けの収納の盆にひっかけて扉を閉めていますが、普通の桐箪笥の扉の裏側だとスペースが足りないかもしれません。
クローゼットなど、日に焼けないところにかけておきましょう。
一連は袷用、もう一連は単衣用などとして、使い分けをすると便利です。
完全にシーズンオフになったら、お手入れするものはお手入れして、全て重ねて三つ折りにして箪笥やクリアケースに収納します。
全部重ねてまとめておくことで、出したり移動したりするのがしやすく、しわくちゃになりにくいのです。
うそつき衿はぱたぱた畳みでコンパクトに
うそつき衿は、たかはしきもの工房独自の形をしています。
衿に、えもん抜きとベルトがついているのですが、衿を左右3つにたたんで、それを芯にしてくるくるとえもん抜きを巻いていくと、とてもコンパクトにたためます。
1)最初に衿の部分を畳みます。片側を三等分して真ん中に重ねていきます。
両側たたんで、長方形に整えます。この時、衿は同じ太さではないので、基準は自分の気持ち良いように揃えてください(下図参考)
2)それを芯にして、くるくるとえもん抜きを巻いていきます。ベルトもたたんで内側に巻き込みます。
3)できあがり! ばらけず、扱いやすいサイズにたためました!!
箪笥にもしまいやすいですね。
半衿もあまり汚れなかったようなときには、衿芯を入れたままハンガーにかけておいてもう一度使うというのも、楽でいいですよ!
前日に衿芯を入れて用意しておくのも、当日の朝楽でよいものです。
うそつき衿の畳み方は、ぜひ開発者の女将の動画をご覧ください。
【うそつき袖・衿の収納術】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

ゴシゴシ擦らない予洗いで真っ白足袋生活
泡で汚れを掻き出す柔らか予洗いで足袋を真っ白に!
皆様、足袋はどうやって洗っていらっしゃいますか?
白い足袋はどうしても汚れが目立つし、普段は柄足袋や気軽な足袋ソックスという方も多いのではないでしょうか。
でも、やっぱり白足袋は礼装にも使われるだけあって、履くと気持ちがビシッとシャン!と気合が入りますし、とても気持ちのよいものです。
カジュアルファンにも遠ざけないで使って欲しいなと思い、今回は白足袋を楽に真っ白に洗い上げる方法2022年度版をお届けいたします。
それは洗濯機に入れて洗う前に「予洗い」をすること。な〜んだやってるけどいまいちだよ、とおっしゃる方もいるかもしれませんが、実はその予洗いのやり方で、洗い上がりも足袋の持ちも、全然違うんですよ。
ズボラな女将でも続いている、真っ白になる達成感が嬉しい予洗い方法は、以下の通り。
予洗いの方法
【用意するもの】
・足袋洗い用専用スポンジ たびすけ
・ウタマロ石鹸
・ぬるま湯
1)ぬるま湯(30〜40度)に足袋を漬け、厚みのある底までしっかり水を含ませてびしょびしょにします。しっかりとお湯の中で押して、水分を中まで入れ込むのがポイント。
2)白い足袋には「蛍光増白剤」が入っていて真っ白に洗い上げることができるウタマロ石鹸がおすすめ。
それを汚れが目立つところに塗りつけていきます。
3)たびすけで汚れを優しく擦ります。
このとき、足袋だけでなくスポンジ側にも石鹸を塗布して、両方に石鹸がついた状態で擦るのがポイント。ゴシゴシする必要はありません。
力をいれないで優しく擦ります。力で汚れを落とすのではなく、優しく擦ることで、きめ細かい泡がたち、その泡で汚れを浮かせてとっていくのです。
たびすけに使われている繊維の形態は三角形になっていて、その特殊な形態によって傷をつけることなく汚れをかきとっていきます。
強く力を入れると、実は汚れを奥に押し込めてしまうような感じもして、このように泡で洗うやりかたをしています。身体も昔はナイロンのボディタオルでゴシゴシ洗うのがいいとされていましたけれど、最近は擦らずに泡で優しく洗いましょうと言われていますよね。それと同じです。
4)一度水につけて汚れの落ち具合を確認し、まだ残っているところがあったらもう一度泡をたっぷりつけて擦ります。
このとき、下から足袋を持っている手の指先などで汚れの部分を押し上げて、スポンジによくあたるようにするとより落ちやすくなりますよ。
5)予洗いが完了したら、洗濯機に入れて洗えばOK。
この予洗いひとつで足袋が真っ白に洗い上がりますので、ぜひお試しください。
力を入れるのは逆効果!? 足袋も痛まない泡洗い
以前は力を入れてゴシゴシしたり、たわしのようなもので洗っていたのですが、この細かい泡でやさしく擦り洗いする方法に変えてから足袋も長持ちするようになりました。
目に見えて白くキレイになり、やっていて楽しい作業なので、ズボラな女将でも続いています!
だいたい、いやだ、やりたくないという作業は労力の割に成果がないようなものが多いですよね。わかります。
でも、この足袋の予洗いは、白い足袋が気持ちよく真っ白になると本当に気持ちがいいので、ぜひ「いやだなあ〜面倒だなあ〜」と思っている人にこそ試してみていただきたい作業です。
洗う時も履く時も、白足袋はやっぱり気持ちがいいものですよ!
<おまけ:女将の予洗いワンポイント>
石鹸は、蛍光増白剤が入っているウタマロと、入っていない純石鹸を貼り合わせて使っています。
ちょっと濡らしてぎゅっと押しつけあうだけでくっつきます。白いものを洗うときはウタマロ側を、そのほかのものは純石鹸側で洗っています。手作り二層石鹸、便利ですよ!
今回ご紹介した「たびすけ」はこちらです。
やさしく洗えて、足袋底の汚れがよく落ちる
足袋洗い専用スポンジ…
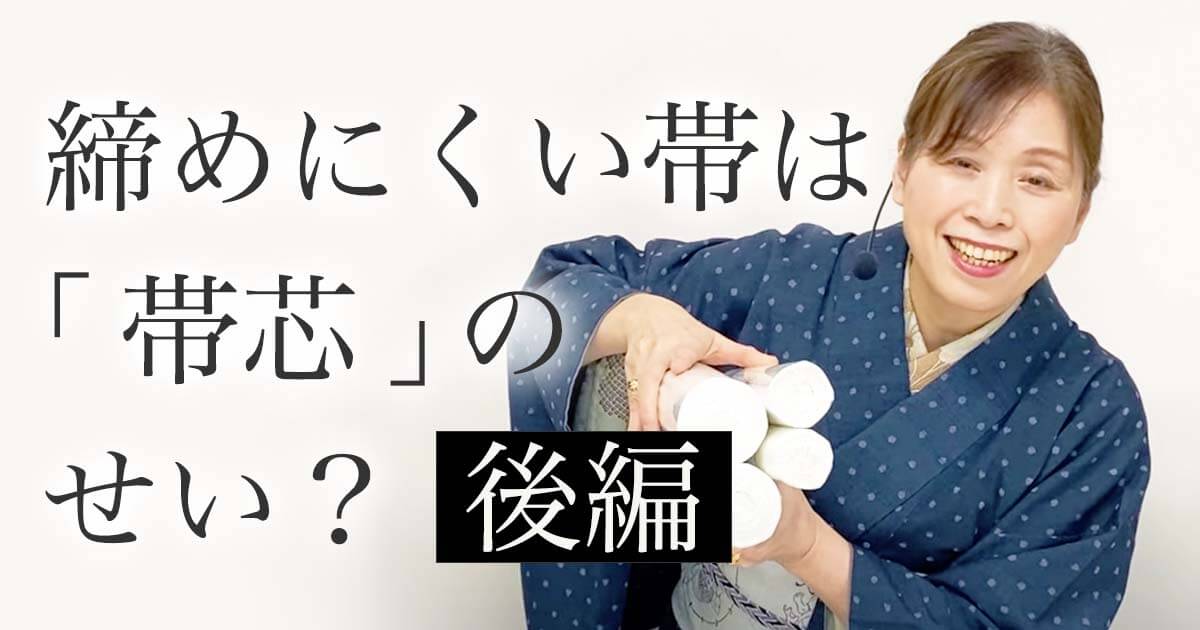
締め心地のいい帯は帯芯次第 帯芯を選んで仕立てよう<後編>
帯芯の違いで、着物生活のストレスが減る
前回帯芯についてお話しましたが、YouTubeでもコメントをたくさんいただきました。
帯を作る時に呉服屋さんで帯芯を選ぶことはできるのでしょうか?というご質問をいただきましたが、おっしゃる通りで、ほとんどの場合がお任せで、帯芯について聞かれることはなかったのではないでしょうか。
でも、だからこそ帯芯の違いで締め心地の差が出ること、自分はこの帯芯を使ってほしいが、そういうことはできるのか?と聞いていただくことなど、お客様からのお声が呉服屋にとっても勉強になるのではないかと思うのです。
もし、これから帯を仕立てる方や、今持っている帯の締め心地がどうかなと思っている方などがいらっしゃったら、ぜひ帯芯についても考えてみていただきたいと思います。
日常的にちょこちょこ着る場合には、ちょっとした使いにくさなどの我慢の積み重ねというものは、着るのが嫌になってしまう要因にもなりますし、そういったことを解決したいと常に考えています。
着やすいということは、ストレスなく着物をたのしめるということ。
帯も、ぜひそのように帯芯を選ぶ仕立てをしていただいて自分好みのストレスのない締め心地で使ってほしいということで、帯芯の販売や仕立てを始めることになりました。
今回は具体的にこんな帯地には帯芯、というお話をさせていただきたいと思います。
名古屋帯と袋帯の帯芯の使い分け
九寸名古屋帯の場合
名古屋帯用には双糸という、二本の糸を撚り合わせてあるしっかりとした厚手の帯芯をおすすめしております。
糸を撚り合わせることで強度が2.5〜3倍になると言われており、しっかりとした帯芯になります。
九寸名古屋は袋帯ほど張りのある生地のものは少ないので、双糸の帯芯で張りをもたせるとよいのです。
縮緬の染め帯など、着物と同じような張り感のない帯地には 厚手の「竹」という二十番手の双糸が普通ですが、女将的には特選(最厚地)を選びます。
なぜならしょっちゅう着る人は、帯芯がこなれて柔らかくなっていくのが早いから。このあたりは好みもありますので、自分の感覚を大事にしてください。
ほどよい厚みの帯地には、少し張り感のある厚手の「竹」を選びます。
張り感の強い帯地には芯は入れないという選択肢もありますが、こなれていくと柔らかくなりすぎるので薄手の「梅」を選びます。
帯芯を入れても入れなくてもあまり差は出ないのですが確実に支えになりますので、入れたほうがおすすめです。
もしくは、袋帯用の単糸のやわらかい帯芯「月」でもいいし、絹芯という選択肢も出てきます。
名古屋帯に袋帯用の帯芯を使っても問題はありません。お好みでよいのです。
絹芯は張りはまったくありません。絹芯を入れると高級に扱ったような気持ちになるのですが、張りをもたせたいときには向きません。
でもとても軽いし、張りの強い帯地には向いています。なんでも絹芯がいいいうことではないので、帯地の張りによって使い分けてください。
袋帯の場合
着物よりも軽いような、柔らかい染め袋帯の場合は、袋帯用の帯芯では柔らかすぎると思います。
その場合は名古屋帯用の厚手「竹」か特選でも。
張りはあるけれど地厚さはなく、少し透けても見えるくらいの袋帯には、名古屋帯用の薄手「梅」でもよいかと思います。
張り感がしっかりしている袋帯は、芯を入れないという選択もありだと思います。
それでも薄い帯芯を入れると、少しふっくらとしますので立派な感じにもなりますし、お好みです。
いずれにしても袋帯には厚手を入れると重厚感が増しますので、そのあたりのバランスを見るのもありかと思います。
自分の好きな帯の固さの好みを把握しよう
もし普段している帯で締めやすいなと感じているものがあったら、それが自分の好み。
触って「これくらいだな」ということをわかっていると、購入するときにも「これくらいだ」と判断できるようになります。
今までは「おまかせで」と、頼む方も受ける側も済ませてきてしまっていたこの「帯芯」問題ですが、日常着物においては、ちょっとの着心地向上が大きな差を生むのです。
細かいことですが、意識を向けていただくと、着物生活の快適さがぐんとアップしますよ。
三河帯芯
三河帯芯
¥2,200(税込)〜
マニアックトークを炸裂させている女将の動画も、ぜひご覧くださいね!
…
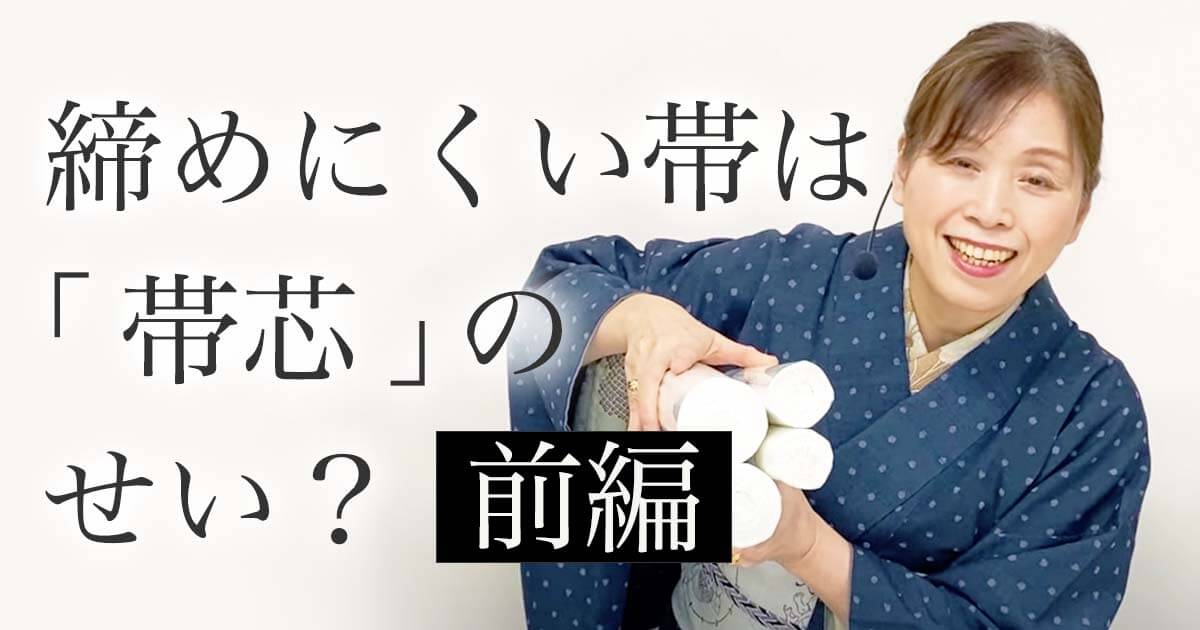
締めにくい帯は「帯芯」のせい? 帯芯を選んで仕立てよう<前編>
帯芯にも良し悪しがある。糊を使っていない国産品を選ぼう
色や柄がとても気に入っているんだけど、なんとなく締めづらい9寸帯、もしくは袋帯などはありませんでしょうか?
帯が締めにくい原因としては、実は「帯芯」が原因であることが多いのです。
帯芯はどんなものを使っていますかと聞かれて、答えられる方は少ないのではないでしょうか。
帯芯もいろいろなものがありまして、たかはしきもの工房では全て三河で生産されているものを使っています。
5種類の厚さの帯芯を揃えていて、お客様にどの帯芯になさいますか、と実際触って選んでいただいています。
薄いものから厚いものまで、張りや硬さも違いますし、帯によっては帯芯が不要な場合もあります。帯地にベストでかつお客様のお好みの仕上がりになるようにご提案をしています。
この帯芯も実は中国産のものもあり、国産のものとの大きな違いは、そのハリ・コシを織ではなく、糊を使って出しているというところです。
糊は抜けるとくたくたになってしまうのですが、織でしっかりとしたものは、変わりません。
糊を使っていない、国内産のものをおすすめする理由はもう一つ。
糊は虫やカビを呼ぶからです。
これは畳紙も同じことで、糊を使った洋紙のものより糊不使用の和紙をおすすめします。
国産の5種類の帯芯をご紹介
帯芯として取り扱っているのは、名古屋帯用で薄手・厚手のもの、袋帯用の薄手・厚手のもの、あとは特選という非常にしっかりとしたハリのあるものの5種類です。
名古屋帯用の帯芯は2種類。薄手の「梅」という四十番手の双糸のものはとても柔らかいものです。
厚手は「竹」という二十番手の双糸のもの。番手の数字が大きくなるほどやわらかくなっていきます。
袋帯用の帯芯は、薄手のものは「都」六十番手の単糸。とても柔らかいものです。袋帯で少し心許ないな、ちょっと硬さを足したいなというときに使います。
厚手のものは「月」三十番手の単糸で、柔らかめの袋帯に使います。
袋帯は帯地そのものが非常にしっかりしたものもあるのでその場合は帯芯を入れないという選択もあります。帯芯といっても、実はいろいろなのです。
最後に「特選」のご紹介なのですが、これは本当にしっかりとしたハリとコシがあるものです。とても柔らかい生地のときに使います。
ハンドメイドで半幅帯を作る方などには、特選を1本買って半分に切ると、2本分の帯芯が取れます。柔らかい帯芯を半分に折って二重にすることもできますが、特選を半分に切る方がリーズナブルにできますよ。
この「特選」を使うと、ピシッとした半幅帯ができます。たかはしきもの工房でも日本手ぬぐいの生地で半幅帯を作ってみました。おかげさまで好評です。
帯は、色や柄しか見ることがほとんどないのではないでしょうか。お仕立てを頼むにしても帯芯はお任せなことが多いと思います。
でも実は、帯芯は「使用感」「着心地」を大きく左右する大切なものなのです。
帯も着物と同じで、芯を替えてお仕立て直しをすると、生まれ変わったようになります。
たかはしきもの工房ではこの「帯芯」の重要性をより多くの方に知っていただきたくて、ネットショップでの帯芯の販売と、帯のお仕立てもお受けするようにしたいと思い、
今回は、帯芯の種類のご紹介をしました。
次回はもう少し詳しい「帯芯」のマニアックなお話をさせていただきますので、お楽しみに!
三河帯芯使用長尺広巾コットン半巾帯
長尺広巾コットン半巾帯
¥22,000(税込)
マニアックトークを炸裂させている女将の動画も、ぜひご覧くださいね!
【帯難民必見!帯の締めやすい、締めにくいは〇〇が大事!】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
よろしかったらご覧ください!
日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
