
初心者でもできる、きもののたたみシワを防ぐ簡単なコツ
きものをたんすから出したら、嫌なところにたたみシワが…。ということを、経験されたことがあるのではないでしょうか。
そんなたたみシワを防ぐ、基本のきもののたたみ方をお伝えします。
きものを着る前の日に準備するのではなく、当日の朝にきものを出すという方には、特におすすめのテクニックです。きものを出した時、「シワにアイロンかけなきゃ」となるのは、本当に嫌ですよね。
今回ご紹介する方法は、後でシワにならないように注意して、丁寧にたたむようにしているので、きものが何枚か重なっていても、極力シワができにくいたたみ方です。ぜひ、ご活用いただければ幸いです。
きものを出したときアイロンがけ不要にするために
画像はきものをたたんでいる時の目線に近い状態で、たたみ方をご説明します。
きもの初心者さんにもすごくいいと思いますが、ベテランさんもご自身のきもので思い当たることがあったら、ぜひ一緒にやってみてください。
基本的に、内側にゆるみがあるきものが着やすいきものです。
内側の裾あたりの中に芯が入っているので段差がでてしまいます。どうしてもピタッと平らな状態にはならないこともあります。それでも、できるだけシワにならないように、まず右側の脇線で折ります。
折った後、裾側を押さえて、裾側から肩に向かって手で布を寄せるようになでつけます。
なでつけるのは、裾側から肩へ一方方向です。
その後、衽(おくみ)線で折り返します。
きものの場合、折り跡が付いているので、本来はそんなに難しいことはありません。そのまま同じ折り跡を折っていきましょう。
次に、衽と衽を合わせます。ここがひとつの肝です。
脇線で合わせるのではなく、衽を折ったら、衽と衽をこっつんと合わせて、ピタッときちんと合わせます。
右手で裾側に重みをかけて押さえながら、裾側から肩に向かって生地を寄せていきます。
裾にシワができると格好悪いので、右手でしっかりと押さえたまま、左手で生地を真ん中に寄せていきましょう。
脇線を手前に連れてきます。
背中心の折れがピタッと合わさるはずです。
同じように裾側を右手で押さえて、裾の方にたまっている生地を肩に向かって寄せていきます。
裾はなるべくきっちり合わせた状態で、肩に向かってくるくると折り込みます。
折り込んだ後、折り込んで丸めたものを右手側にクーッと引きます。丸まっているので中の生地は動きません。
次に衿、袖まわりをたたみます。まず、下側になる袖を入れますが、袖の肩の部分とたもとの先を持ち、キュッと引きます。
パンッと生地を張ります。
バサッと身ごろの下に入れます。
下に入った袖がよれていないことを確認しましょう。
次は衿を整えていきます。
衿先を右手で押さえて、左手でシワを伸ばしていきます。
衿の下にシワができやすいので、衿の下にスーッと手を入れて生地のたるみを伸ばします。
衽線で折れているので、右手で衿先を押さえて衿の折山を持ちキュッと上に引きます。
同じように、衿の折山を合わせて、二枚重ねた衿の折山を持ち、上にプンッと引きます。
上側になる袖を手前に持ってきますが、今はまだ生地だまりが残っています。この時点では、生地だまりがあっていいです。
背中心の折山も真っ直ぐに整えたら、生地だまりがある部分をたたいてならしていきます。たたくと生地が広がって、馴染んでいきます。
よく衿の部分を折るのが大変と言われます。
きちんと衿折がなっていない場合、たたみにくいです。
衿折がきちんとしているものは、もともとの折れ線と同じように整えていけば、衿の中もきちんと折れていきます。
衿が中に入っていると、背中の折れ線の角度が鋭角になってきますが、この角度はきものの生地や、仕立て屋さんによって違ってくると思います。
たとえば、衿がすべて同じように重なっていると背中の折れ線の角度が鋭角になります。
繰越から三角がでるような折り方をすると、背中の折れ線の角度が浅めになります。
生地によっては硬いものだとつりが出たりするので、その場合は角度が深い方が良い場合もあります。衿折の線が薄くても見極めて、背中心を持って引くようにすると衿が中に入ってきます。
衿を整えたら全体を触ってみて生地のボコボコがないようにならしていきます。
ならした後、左手を袖山側に置いて、布を衿先に向かって寄せていきます。
衿先あたりに生地溜まりができます。
衿先のあたりに右手を置いて、左手で裾側を持ちます。内側はまだブカブカしている状態です。
左手で丸めた裾を広げながら袖山側に重ね合わせます。ブカブカはまだ、内側にあります。
内側と外側では生地の厚みもある分、内側の生地が余るのは当然です。右手の折り返しに指を入れて、生地のたるみがないように左側の裾を一枚ずつ引っぱります。
一枚ずつ裾を引くと、裾の重なりがズレるのがわかると思います。地厚なものほど、ズレは大きくなります。裾をズラしておくことで折り返しの内側の線が一本で済みます。
裾線を合わせて折ってしまうと内側のたるみで折り返しの線が三本ぐらいシワがよります。折線が一本だと割と気になりませんし、シワくちゃにならなくて済みます。内側の生地の余りをしっかり引っ張るのが大事です。
今回ご紹介した方法は、できるだけアイロンがけしなくて済むたたみ方でもあります。
たたみ方の説明に使ったきものは、二年ぐらい着ていないきものです。上にきものを重ねていたので、生地の厚みによる段差がある部分にはシワが入りました。しかし、深いシワでなければ、簡単にアイロンで取ることができますので、やはりキレイにたたむことが大事だと思います。
たたんだきものを持ち運ぶときは?
きものを持ち運びするとき、たとう紙に入れたままたたむ方が多いのではないでしょうか。実はその方法だと、きものにもシワができるし、たとう紙もぐちゃぐちゃになります。
持ち運びするときのおすすめは、たとう紙の上にきものを乗せてたたむ方法です。
たとう紙の上にきものを乗せたら、たとえば、帯揚げや丸めたタオルなどを折り返す部分に置いてから、たとう紙ごときものを折ります。
もう一方も折って三つ折りにします。
この状態で風呂敷で包むときものもシワになりにくいし、たとう紙も傷つきにくいです。
少々のことではシワにならないので、たとえば、紙袋に入れて持つこともできます。持ち運びのときに、試してみてください。
女将流・擬音語たっぷりのきもののたたみ方の動画はこちらの動画をご覧ください。
【簡単なコツで、きもののイヤなたたみシワを防ぐ!初心者も知っておきたいマニアックなこと】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
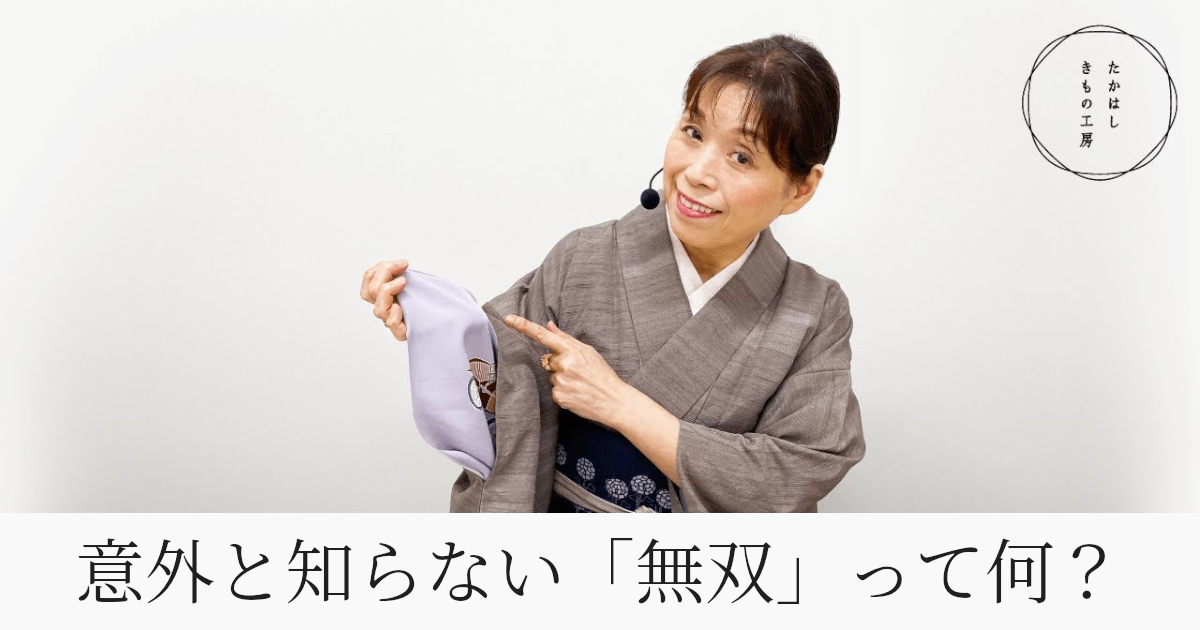
意外と知らない「無双」って何?
普段、きものを着ている中で、耳にしていても、なんとなくわかっているようで、よくわかっていない言葉って、ありますか?
その言葉の意味をきちんと知ることで、きっともっときものが楽しくなるようなきものの基本の言葉。
今回は、襦袢の「無双(むそう)」という言葉の意味とその使い分け方をお伝えしていきたいと思います。
「無双」って、業界の専門用語では?
襦袢(袖)には、「無双」や「半無双」、「単衣」と種類がありますが、「無双って、何?」と思われたことがあるのではないでしょうか。
ちなみに、辞書で「無双」の意味を調べると、
…
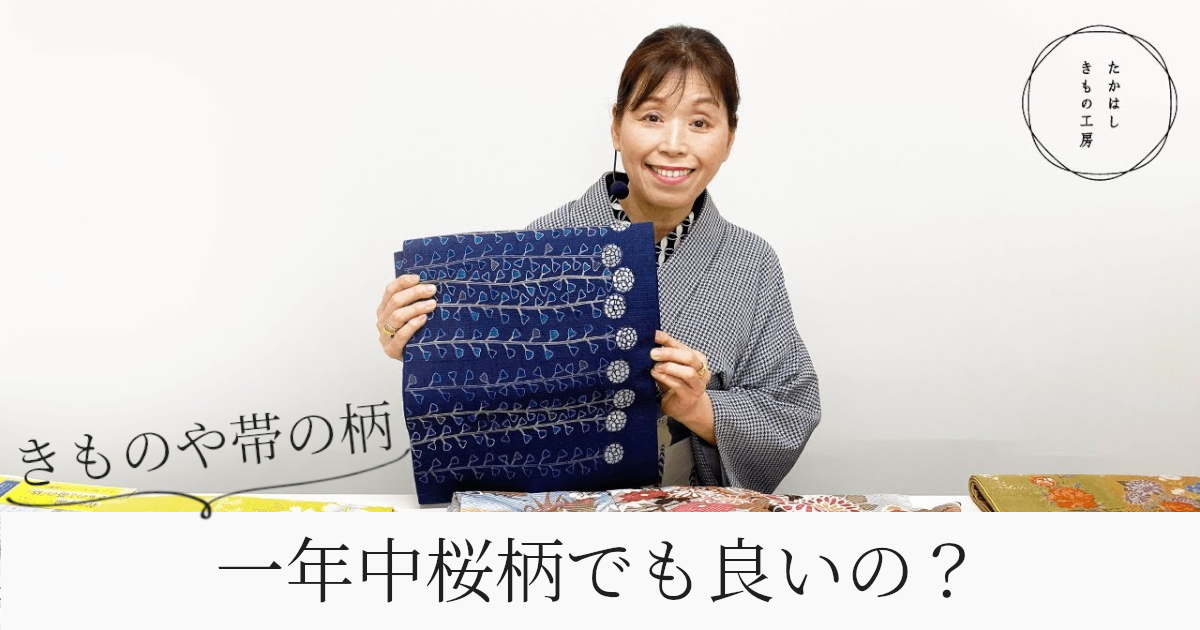
きものや帯などの柄、一年中桜柄でも良いの?
きものや帯の柄で季節を楽しむとか、季節に合わない柄は着ちゃいけないとか、いつ誰が決めたのかわからない決まりごとを耳にしたことがあると思います。
そのため、きものや帯などを選ぶ時、「この柄って、今の季節に選んで大丈夫なの?」と思ったことがあるのではないでしょうか。
たとえば、直接注意されることがなかったとしても、誰かにそんなのダメでしょって思われるんじゃないかという不安もあると思います。
作家・きものデザイナーの宇野千代さんは「桜が好きだから」と、一年中桜柄のきものやバッグ、小物類を愛用されていたそうです。
堂々と私はこの柄が好きだから一年中着ると言えるのもとても素敵です。柄の好みはその人の自由ですので、何でもありでしょう。
しかし、そこまで貫いて楽しむことができる人はほとんどいらっしゃらないと思います。
宇野千代さんの考え方を基本にしながらも、女将が40年以上のきものを着てきた中で、柄選びで気をつけていることをお伝えしていきます。
季節の柄選びの決まりに囚われるのではなく、楽しみ方のひとつとして選んで、もっときものが楽しくなるための参考になれば幸いです。
織りで柄を作っている生地はどうする?
まずは、生地の柄から。
白生地には、地模様(織で柄を作っているもの)があります。地模様があるものとないものいろいろですが、紋意匠(縮緬の種類のひとつで、地紋を織り出したもの)というタイプのものだといろんな柄があります。
たとえば、茶道をされる方だとよく色無地のきものを作られると思うのですが、その生地を選ぶ時、色目としてピンクやえんじなどの華やかな暖色系の色で染める時には、地紋の柄を
気にすることは無いと思います。
普段着るきものとしてちょっと地味な寒色系の色を選ぶ時や、今後、法事でも使うようなきものを選ぶ時には、地模様に吉祥文様(おめでたい、縁起の良い柄)を選ばないということがあります。
たとえば、宝づくしは吉祥文様のひとつですが、どんな地味な色目でも法事の時に着ることはしません。
仏事にも使える生地かどうかの判断ポイントとして、
…

一枚の半衿を倍長く使える付け方の工夫
「この半衿、もう使えないな」と思う時って、どんな時でしょうか。
色・柄の好みの変化、生地の状態など、状況によって様々かと思います。
その中で、「一部黄ばみがあるだけで、他はきれいなのに使えないのはもったいない…」と思ったことはありませんか?
半衿の一番汚れやすい箇所は、首に直接触れる部分です。
ファンデーションなどの化粧汚れや、皮脂汚れが原因で、洗っても黄ばみが落ちず、黒ずんだような感じになると、もう使い続けるのは嫌になりますよね。同時に、部分的な黄ばみだけで捨ててしまうのは、ちょっと残念なのではないでしょうか。
今回は、一枚の半衿を倍長く使うことができる半衿の付け方の工夫について、広幅(約20cm)の半衿と一般的な幅(約16.5~17cm)の半衿を使ってお伝えしていきます。
幅が広いのは半衿を倍長く楽しむため
たかはしオリジナルの「小千谷縮半衿」は、きものの生地を半分に切って半衿にしています。そのため、一般的な半衿より広い、幅約20cmです。
幅を広くとっている理由は、半衿を長く使うための工夫がしやすいようにと考えたためです。
首が直接触れる内側は汚れが付きやすいので、半衿を洗って付け直す際に黄ばみが気になる部分を内側にずらして縫い付けて使えば、同じ半衿を長く使えるわけです。
では、半衿の付け方の工夫をご紹介します(襦袢も、うそつき衿も縫い付け方は同じです)。
たかはしのうそつき衿は、たかはしきもの工房のブランドネームがある方が外側で、ブランドネームがない方が内側になります。
※襦袢の場合、外側:きものに接する側、内側:体に接する側
この後の説明で出てくる外側と内側は上記を基準にしているので、内側と外側を混乱しないように注意しながら読み進めてください。
黄ばみが取れなくても諦めない半衿の付け方の工夫
半衿の付け方の工夫について、広幅(約20cm)の半衿と一般的な幅(約16.5~17cm)の半衿を使ってお伝えしていきます。
(1)広幅(約20cm)の半衿の場合
《使いはじめのとき》
まず衿の内側から半衿を縫い付けていきます。
たかはしオリジナルの「小地谷縮半衿」の場合ですが、衿幅があり両端がロックミシンで始末しているため、約1cm中に折り返して縫い付けます。
縫い付けた後、衿の外側が上に来るように返します。
半衿を衿幅と同じ幅に折ります。折って衿幅からはみ出た分を中に入れ込み、外側を縫い付けます。
《黄ばみが気になってきたら》
生地幅がたっぷりあるので、内側に約1cm折り込んでいた生地をさらに1㎝折り込むようにして縫い付けていくと、衿汚れが付きやすい部分が内側に入ってくるので、外からは見えなくなります。
この方法で半衿を縫い付けるようにして使っていくと、多分5回分ぐらい折り込んで使うことができます。
最初に半衿を縫い付ける時のポイントは、衿の外側の折り込みを増やし、内側の折り込みを少なめにして縫い付けるようにすること。
半衿を外して洗い、付け直す度に少しずつ内側にずらして折り込んでいけば、衿の外側はきれいな状態で外側には見えません。できるだけ生地を無駄にせず、有効に使える方法だと思います。
※上記のように半衿の内側にずれ込んでいくので外からは見えなくなります
広幅の半衿の方がやりやすい工夫ですが、一般的な幅の半衿でも同様の工夫をすることができます。
(2)一般的な幅(約16.5~17cm)の半衿の場合
《使いはじめのとき》
衿の内側に半衿を縫い付けていきます。
一般的には、半衿を折り込んで縫ってくださいと聞いたことがあると思いますが、極論で言えば、折り込まずにそのまま縫っても構いません。
半衿の耳の部分の状態にもよりますが、折り込まずに縫い付けると、見た目が格好悪いと感じるかもしれません。
実際は、半衿の耳の部分が見えた状態と折り込まれた状態で縫い付けるのは、きものを着た状態ではそれほど違いはわからないものです。
内側を縫い付けた後、衿の外側が上に来るように返し、半衿を衿幅と同じ幅に折ります。
折って衿幅からはみ出た分を中に入れ込み、外側を縫い付けます。
《黄ばみが気になってきたら》
半衿を洗濯をしながら使い続けて、首に直接触れる部分の黄ばみが気になってきたら、広幅の半衿と同じく内側にずらして付け直しましょう。
内側の折り込みを約1~1.5cm増やし、汚れた部分が内側に入り込むように縫い付けます。同様に外側を縫い付けていきます。
このような方法で3回は付け直して使えると思います。
《透け感のある薄手の半衿の場合》
薄手の半衿で、折り返した部分が透けて見えるような場合には、外側の折り込みを調整して、生地の端が半衿の折った部分にまでいくようにすると見えません。
黄ばみが気になってきて、折り込みをずらす場合、内側の折り返しを生地の端が半衿の折った部分にまでいくように折り込み、縫い付けます。そして、外側の折り込みを約1~2cmにして縫い付けます。
透ける半衿でも2回は付け直して使えると思います。
半衿の付け方を工夫することで、一枚の半衿を倍長く使うことができます。
たとえば、1000円の半衿を3枚買うのであれば、3000円の半衿を3回折り込みをずらして使った方が、不要になって廃棄するものも減らすことができますし、長く使えて良いと思いませんか。
まずは、ぜひご自身で試してみてください。半衿を使っている中で、黄ばみ以外でも、生地がよれてきたり、色褪せた時なども折り込みをずらして付け替えてみると、長く使うことができます。
さらに、このようにして使いきった半衿は、クッションや枕の詰め物に使うなど、まだ利用できるので、きもの生活を楽しみましょう。
女将による一枚の半衿で倍使える半衿の付け方はこちらの動画をごらんください。
使いきった半衿の使い方はこちらをご覧ください。
▼女将流・捨てられない絹の使い方
https://k-takahasi.com/blog/2021/09/7812/
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

帯揚げ・帯締め、簡単&キレイな結び方
日常できものを楽しむなら、着付けをいかに「早く・楽に・キレイに!」するのかは、重要なポイント。
中でも、帯揚げや帯締めは、きもの全体に対して占める面積は小さいですが、キレイにできているのかどうかで印象が違ってくる部分でもあります。
帯揚げと帯締めの結び方について、動画や本など世の中にたくさん紹介されていますので、ご自分に合った方法を選んでください。
ほぼ毎日きものを着る女将だからこそ、いかに早く・楽に・キレイに!を目指した、便利で簡単な結び方をお伝えしていきます。
意外と目につく部分はすっきり結びたい帯揚げ
帯揚げで女将が意識している点は、生地の厚みも含めて良いものを選ぶことです。帯揚げが見える面積は小さいですが、ペラペラの生地では格好がつきませんし、結び目もふんわりしません。
結び目をふんわりする片輪結び(ちょうちょ結びの羽が片方だけの状態)の結び方からお伝えしていきます。
1)スタンダード編
帯揚げを帯枕にかける時、帯揚げの五分の二から三分の一ぐらいに折って、かけています。
帯揚げの上の部分は帯枕にかけているので、折られている状態になります。
帯揚げの体の脇の部分が人の目に付くので、キレイに整えるように気をつけましょう。
帯枕に帯揚げをしっかりとかけるために、帯揚げを前に引きながら下の部分を引くと、帯枕に帯揚げの下の部分が入っていきます。
帯揚げの結び目を片輪結びにする時は、帯揚げの長さを調節して、左側を短めに持ちます。
帯揚げを前に持っている状態で、帯揚げを平らに整えます。
帯揚げはきつく締める必要はなく、飾りとして締めるものですが、帯揚げの生地がブカブカしていると、体の脇の部分に生地がたまることになるので、キュッと前に引いてキレイにすっきり入るようにします。
最初に三分の一に折っていた分を平らに持ち、帯揚げの下側の三分の一を折って平らにします。
三分の一に折ったものを、山になるように半分に折り、山に沿って指をスーッと後ろに持っていきながら、帯揚げを整えます。
反対側も同じように、最初の三分の一を折って整えていきますが、左側を持っているのが大変だと感じる場合には、帯揚げを帯に一旦、挟んでおきます。
帯揚げを前に引き、山が上の状態できものと同じように左側の帯揚げが上になるように重ね、体の中央でひと結びします。帯揚げはきつく結ばず、体にあたる程度で構いません。
さらに、下にある左側の帯揚げだけを下にグッと引き下げると、結び目の上方が平らに整います。
上にきている帯揚げの下に右手を真横に入れ、輪を作ります。
輪の中に左手の指一本を入れながら、右手の指先で垂れている帯揚げを輪の中にゆっくり引き込みます。
結び目はギュッと結ばずに、ふんわりとしたままでOKです。
真ん中を持ち上げて、帯揚げをまっすぐ下に帯の中に入れ込みます。
仕上げに帯をしごいて帯揚げをキレイに整えたら完成です。
この結び方よりもさらに簡単な方法があります。
2)よりズボラ編
左右の帯揚げをキレイに整えるところまではスタンダード編と同じです。
左右を同じ長さで持ち、輪を上にして左の帯揚げを上にかぶせて、ひと結びします。
垂れている帯揚げを内側に丸めたら、帯の中に入れ込むだけです。
帯の中に携帯などを出し入れしない場合には、早く締められて、とても簡単です。
また、他の結び方でよく聞くのは次のようなやり方です。
3)その他①編
帯揚げをひと結びした後、下側の帯揚げを結び目のところでねじって、帯の中に入れ込みます。
上側の帯揚げを結び目にクリッとひと巻きしてから、帯の中に入れ込みます。
さらに、帯揚げをひと結びせず、ただ挟む方法もあります。
4)その他②編
左右の帯揚げをキレイに整えるところまではスタンダード編と同じで、左右を同じ長さで持つように調節します。
右側の帯揚げを前に持っていき、体の中央よりちょっと長いくらいで帯揚げを折ります。
帯揚げが長く、折りたたんだ部分が体の脇まで来るような場合には、さらに折って胸下あたりに厚みを持たせるように調節します。
半分に山にして折り、帯を引きながら帯揚げにそって、手をすべらせて帯の中に入れ込みます。
反対側も同じようにして整えて、最初に入れた帯揚げの上にかぶせるように入れたら、帯揚げを引いたまま帯をしごいて整えます。
この結び方で締めると、はんなりした色っぽい感じになります。重なり部分が少し見えても素敵ですし、山がふたつあるのも素敵ですね。
結び目をどんな風に結ぶのかについては、自分がどう見せたいかを考えて帯揚げを締めていくと良いと思います。
帯揚げの結び方のポイントは、
…

着付け師KOYANOに学ぶ目からウロコの着付けポイント
日常的に着物を楽しむなら、
少しでも着付けを楽に時間を短くしたい
着崩れないようにしたい
ここちよく着ていたい
と、思いますよね。
そこで今回は、日本舞踊専門の着付をされている着付け師のKOYANOさんから、着付けについてのコツを教えていただきました!
女将が着付け師KOYANOさんと出会ったら…
着付け師KOYANOこと古谷野貢さんは、現代着付けに舞踊着付けの技術を盛り込んだ「一日中着ても、カラダが楽で崩れない着付け」を口コミと紹介のみで岡山県倉敷市から全国を飛び回っている着付け師さんです。
他の着付け師さんと異なるのは、一般の方々の着付けを行うだけではなく、日本舞踊専門の着付けを行う衣裳方として各流派の舞台裏でご活躍されていることです。
たかはしの肌着に興味をお持ちになり、倉敷市から気仙沼までいらっしゃってくださいました。
※オリジナルブランド本京友禅「明和美染(みわびぞめ)」を展開する「創作きもの明和美」の代表も務められています。
実際に、古谷野さんと女将が話をしていると、肌着や補整、着付けについて話が尽きることなく盛り上がったそうですが、その中で女将が再確認できたことや目からうろこのテクニックをお伝えいたします。
楽で着崩れしない着付けの共通点とは?
日常的にきものを楽しむために、体が楽で着崩れしにくい着付けは、誰もが望むことだと思います。
そのための着付けとして、女将は、下半身は横糸の力を借りて、上半身は縦糸の力を借りて体に生地の目をフィットさせるように着付けるということをずっと言い続けてきています。
生地の目を意識して着付けると、生地の面で体が支えられるようなここち良さがありますし、生地が体に沿うようになるので着崩れもしにくくなるのです。
▼詳しい方法は、こちらの記事をご覧ください
「L字の法則」で着崩れ知らず、体を支えてくれる着付けに
女将がこの論理にたどり着いたのは、子どもの頃に習っていた日本舞踊での経験からでした。
とにかく下半身を締めたいということと、帯まわりをきつく締めるのは嫌なので、腰まわりだけを引き締めたいという強い願望があることを自覚していました。
なぜなら、それが一番ここちよく着付けることができることを、日本舞踊での着付けを通して肌で体感していたからです。
実際、古谷野さんの着付けを女将が体験した時、生地を体に当てる古谷野さんの手つきが女将が長年考えていたことと共通点がいくつもあり、「L字の法則」はまさにぴったり一致したのです。
さらに、古谷野さんのテクニックの中で、すごく有益な情報で女将がとても驚いたやり方がありました。それは裾よけのつけ方なのですが、普段の裾よけのつけ方を思い浮かべながら読み進めてください。
キレイで時短な裾よけのつけ方
裾よけを自分でつける時もそうですし、人につけてあげる時も次のようなやり方でつけているのではないでしょうか。
1.先に上前の位置を決めた後に下前を体に巻きつける。
2.上前を体に巻きつけた後、上前の下になった紐を外側に引き出し、紐を巻きつけて結ぶ。
古谷野さんの裾よけのつけ方は、この方法とはまったく違っていたのです。
《人に裾よけをつける場合》
1.着付ける相手の体の中心部分に裾よけの左右の力布を合わせて持つ。
2.裾よけを持っている手を右側にパタンと倒す。
3.紐が外側に来るので、そのまま体に沿って巻いていき、紐を巻きつけて結ぶ。
《自分で裾よけをつける場合》
1.体の真ん中で裾よけのセンターを決め、左右の力布を合わせて左手で持つ。
2.裾よけを持った手を左側にパタンと倒す。
3.紐が外側に来るので、そのまま体に沿わせて裾よけを巻いていき、紐を巻きつけて結ぶ。
裾よけを巻きつけた後で紐を抜くやり方よりも、ゆるんだりズレたりすることなく仕上がりがキレイになりやすいですし、紐を抜くという手間も無くなります。
これはほんのちょっとしたコツですが、着付けする上でのストレスがひとつ無くなったことになります。紐で巻きつけて結ぶタイプの裾よけを着る時は、同じやり方で着られるので、ぜひ試してみてください。
女将による目からウロコの着付け術はこちらの動画をご覧ください。
【着付師KOYANOに学ぶ!目からうろこの着付け術!着付け師さんから教わるポイント】
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
