投稿
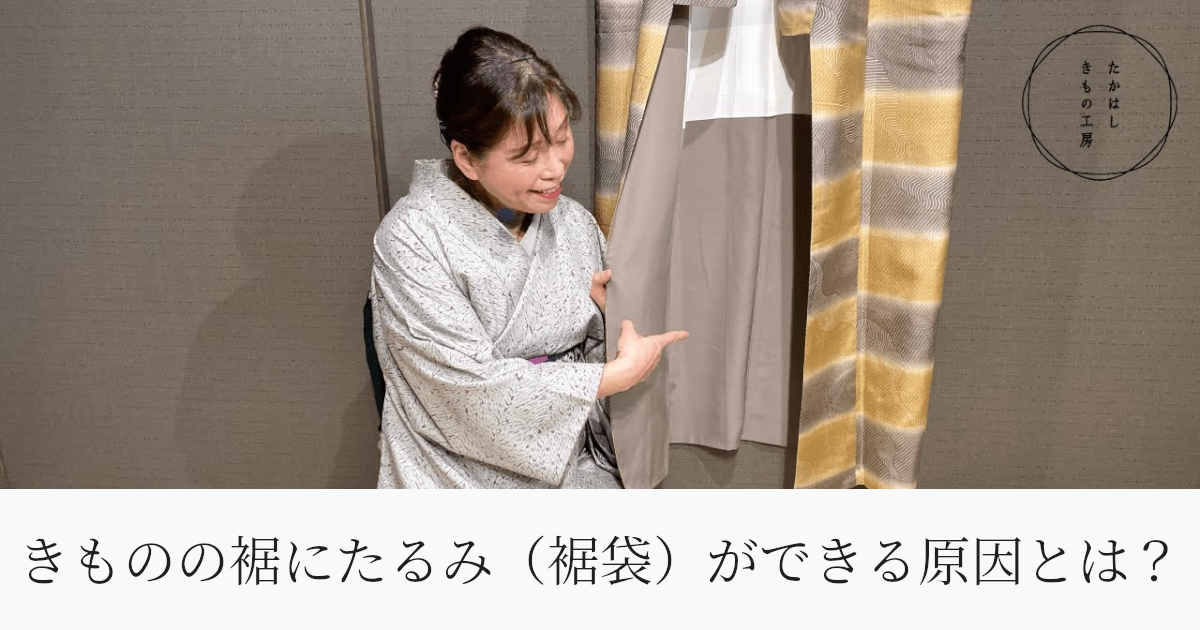
きものの裾にたるみ(裾袋)ができる原因とは?
袷のきものをきもの用ハンガーなどにつるしたときや、着付けで腰ひもを結んだときに、きものの表地の裾にたるみができた経験ありませんか?
このたるみを「動画では表袋(おもてぶくろ)以下同」と言いますが、特にやわらかもののきもので目立つと思います。
実は、この「表袋」は仕立てる時点でかなり回避できるにもかかわらず、その対策がされていない場合が多いようです。そのため、きものに袋が入ってしまうのは仕方がないことと思っている方も少なくないかもしれません。
今回は、「表袋」ができてしまう原因と「表袋」ができたきものの直し方の工夫をお届けしていきます。
もしかすると、きものを平らな場所に置いてピターっと表も裏も平らな状態で、きものをつるしてもピターッと「ゆるみ」がない状態がきれいな仕立てと思われていませんか?
一見、表も裏もピタピタッと合っているのがきれいな仕立てと思われがちですが、実は、着にくいんです。では、その理由をご紹介します。
裏地の「ゆるみ」には理由があった
まず、女将の訪問着を例に見ていきましょう。
表地は刺繍がされている生地なので、刺繍部分が裏地に響いてでこぼこしていますが、裏地を見ると全体に「ゆるみ」が入っています。
約10年前に仕立てたきもののため、経年による多少の縮みがあると思いますが、仕立ててすぐの頃はもっと「ゆるみ」がある状態だったと思います。
たかはしでは、裏に「ゆるみ」を入れる仕立てをします。裏に「ゆるみ」がなくピタピタの状態だと、表に袋ができてしまい着にくくなってしまうためです。
たとえば、やわらかものの縮緬の場合、表地の方が裏地よりも生地がずっと重いため、「ゆるみ」を入れずに仕立ててしまうと、着たときに裏地は体に沿うように付きますが、表地はすべって落ちるため「表袋」ができます。
和裁師さんは、その落ちる度合いや、経年による収縮や湿気による収縮を計算に入れて、裏地に「ゆるみ」を入れます。
そのため、仕立ててすぐの状態できものをつりさげると裏に「ゆるみ」がありますが、それが着やすいきものなのです。
逆に、着にくいきもの、必ず「表袋」になるというきものをお見せします。
実は「ゆるみ」がないきものは着にくい
この画像にあるようなきものを着ると「表袋」になります。
裏地に「ゆるみ」が全くありません。ピターッとしていて、むしろ表地に膨らんでいるぐらいになっています。
もし仕立て上がりがこのような状態だった場合には、仕立て直しを依頼しても良いと思います。
ただし、紬系のきものは生地が軽いので、やわらかものに比べると「表袋」になりにくいです。たとえば、大島紬の場合、表地は収縮しにくいのですが、それに比べると裏地が経年で収縮するため、それを計算して余計に「ゆるみ」を入れて仕立てたりします。
生地には経年収縮があるので、仕立てを工夫しても表袋になってしまうことはありますが、きものの着やすさを考えると、仕立てるときから「ゆとり」がなくピタピタに縫ってもらうのはできるだけ避けた方がよいと思います。
ぜひ、今後きものを仕立てるときに、お願いするお店の方に、裏地に「ゆるみ」を入れてくださいと伝えると、そのように仕立ててくれると思います。
一時期、きものを着ない時期に「ゆるみ」は要らない、ピターッと紙を畳んだように縫うことが良しとされたときがあって、「ゆるみ」を邪魔なものと考えていたのかもしれません。ただ、実際にきものを着だしたら、とても着にくいことがわかってきてたのではないでしょうか。
裏地に「ゆるみ」を入れて仕立てるというのは、きものを日常的に着ていた先人たちの大事な知恵ですね。
きものの裾の「たるみ」を解消する方法
すでに「表袋」になっているきものを着付けるには、腰ひもを締めてとめた後に整えることで、袋になった部分を解消することができます。
※腰ひもを締めて腰ひもに嚙んでいる生地をすべて引っぱり出した後に行います。
1)腰ひもの上の生地を触って、表地と裏地の二枚があることを確認します。
2)表地一枚だけをつまんで裾と一緒に持ち上げて引っぱります。
3)袋になっている部分の「たるみ」がなくなるまで、少しずつ引っぱりながら整えます。
※白枠内が袋を調整する前の状態です
このように着付けのときに調整すればよいとはいえ、着るたびに調整するのは大変です。
この裏地の「ゆるみ」に対しての知識が一般的になっていくと、きちんと着やすいきものを縫ってくれる和裁師さんが増えていくと思いませんか。
きものを仕立てるとき、裏の「ゆるみ」がある意味についても意識してみてください。
さまざまなご意見あることを承知の上で配信をきめた男気あふれる女将による動画はこちらをご覧ください。
【実は…あなたのきものにもあるかも!?きものの「裾袋」って何?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

初めての仕立てで驚いた【きもの初心者必見】
普段、洋服よりも着物の方がいいのではないかと思いはじめた、きもの初心者の佐藤です。こんにちは。
着物の話をした時の、体感3回に1回ぐらいの頻度で、
母:「着物はお金がかがんだよ~」という言葉が出てきます。
訳:着物を着るにはお金がかかるんだよ
確かに、着物、帯、帯締め、帯揚げなど、ファストファッションはもちろん、よくお店で市販されている洋服に比べたら、一つ一つの価格は高いと思います。
ただ、最近、別の視点で考えたら、佐藤にとっては、着物を着る「価値」の方が洋服を着る「価値」よりも高いのではなかろうかと。
【理由1】:日常で特別感が味わえる。
着ているだけで普段の自分とは違う側面からお褒めの言葉をいただけたり、運転で道を譲ってもらえたり、見知らぬマダムからお声をかけてもらえたりと嬉しいことが多い。
【理由2】:地元への地域貢献になる。
肌着などをはじめ、たかはしで購入するため。そして、社内のみんなにも喜んで もらえる。
【理由3】:姿勢が変わった。
着付けで骨盤が立つ形になり、姿勢が良くなったためか、身長が163cmから164.7cmになった(驚)
とは言え、無理して頑張っても、持続するのが難しくなるので、無理せず楽しめたらと思っております。
今回のテーマは、振袖以外の着物を初めて仕立てた時に驚いたこと。「試着」に関わるびっくりからお届けいたします。
自分に合うものをどうやって選ぶのか?
着物は一枚の反物から作られていますが(胴裏や八掛等は置いといて)、いろいろと反物を見ている時に思ったのです。
「自分に合う着物ってどうやって選ぶんだろう?」と。
そもそも、洋服でもオーダーメードしたことがないため、洋服との比較もできないわけですが、何を基準に選べば良いのかもわかっておりませんでした。
(振袖の時は総柄ピンクや赤など華やかなものを避けてセレクト)
佐藤:「どんなのが自分に合うのかわからなくて…。」
店長:「まず、自分の好きそうな色や柄のものを体に当ててみたらいいのよ。」
洋服選びで、自分の好きな色と似合う色というのが違うというのを何度も経験してきた佐藤。それ故、自分のパーソナルカラーの「紺」とか「青」とか選びがちに。すると…
女将:「そういうのもカッコいいかもしれないけど、こっちのも良いよ~」
と、勧められたのは洋服ではあまり選ぶことがない、少し紫がかったピンクがベースの格子の紬の反物。
佐藤:「うおおおぉぉ~(*'ω'*)」
では、試着してみましょうということで、出てきたのは「うそつき衿」と「腰ひも」。
「うそつき衿」が体にセットされた後、選んだ反物が体に巻きつけられ、気づくと…。
なんということでしょう(*'▽')
まるで着物を着ているかのような状態の佐藤が鏡に映っていたのです!
仕立てる前の反物の状態なのに、試着ができるということがすごく驚きでした。
そして、着た時のイメージがしやすいので、試着ができるならば安心して選べるなと思いました^^
…結果、買っちゃいました~っ(≧▽≦) てへっ
※その時仕立てた着物を使用しての着付け教室
初めての仕立てからその後
「試着」は、着物を選ぶための一つの手段ではあるわけですが、まだまだ着物のコーディネートがわかっていない佐藤きもの初心者。
例えば、着物に合わせる帯や、帯締めと帯揚げの組み合わせ、半衿にどんなものを持ってくるかなどなど。まだまだわかっていないので、手持ちのものであくせくするのみ…(;'∀')
ただ、日々、自分にとって新しいことを知るたびに、「む、無限なのかっ!」と思えるほどに、組み合わせの妙と言うのでしょうか、楽しみ方も無限大なのかとドキドキ、ワクワクしております。
振り返ると、初めてたかはし主催の「浴衣でビアガーデン」に参加したのが約3年前。初めての着付けを教えていただいてから約2年。(2022年9月末時点)
礼装よりも「日常きもの」を楽しむ機会の方が圧倒的に多いのですが、着物を選ぶ時の自分の傾向が見えてまいりました。(主に、リサイクルきもの中心ですが)
…

ドキッ!振袖以外の初めての仕立て着物【きもの初心者必見】
こんにちは!2年目&きもの初心者の鷹木です。
私、ついに決意し…思い切ってゲットしてしまったのです!
振袖以外の、自分自身の“着物”を!!(´艸`*)
たかはしの業務の中で、ブログを書く際にもいろいろと学んではいるものの、自分で着物を着れるようになることはもちろん、自分の着物をゲットすることもできていませんでした。
入社以来、浴衣、下着類等、和装に必要なアイテムを周りからこそろに固めてきていました。そして、ついに!毎年10月開催の「たかはしの創業祭」という、素敵!&お得!な、大イベントでラスボス“着物”にたどり着くことに成功したのです!
今回は、私の初めての仕立て着物にお付き合いいただければと思います☆
創業1967年たかはし史上No.1に輝く
振袖以外で初めて着物を仕立てる私。
ドキドキしながらお店へ行ったところ、、、。
O島店長:「たかはし歴代1位だよ~。」
と。
…

びっくり!洗える着物の裏側「水通し」【きもの初心者必見】
こんにちは!きもの初心者&たかはし2年目の渡部です。
新社屋に移転してきたばかりの頃は、自分で整理したハズの小物やレンタル商品などの膨大な商品を
「アレ(汗)どこにしまったっけ(…

ちょっと許せないな
2008年10月28日
昨日まで当店の創業祭でした~ お陰様で無事終了m(_ _)m
ご来店いただいたお客様はもちろん、いらっしゃれなかったお客様にも、心より本当に、本当にありがとうございました。
ところで
今日のタイトル、ちょっと過激ですが
でも、ちょっと許せないんですよ。

これ、しみ抜きに預かった仕立て途中の着物。
つまり仕立屋さんが誤ってシミを付けてしまったということなのですが。
あ、いえいえそれが許せないのではないのです、人のすることに間違いは付きものですから。許せないのはこの縫い方。
写真ではわかりにくいかもしれませんが、かなりぶくぶくで針目も真っ直ぐではなく、裾や褄先などちょっとひどいんだな……。…

つじつま
2007年5月2日
「つじつまが合わない」とか、「つじつまを合わせる」は「辻褄」と書くそうで、裁縫用語からきているんですって。
「辻」は縫い目が十文字に合うところで、「褄」は着物のすその左右のこと。
どちらも、きちっと縫い目が合っていないとチグハグな着物になってしまうことから、物事の道理や筋道が合わないことを「つじつまが合わない」というようになったそう。
ところでうちは悉皆(しっかい)が元々の本業(←って、副業があるわけではないんだけど…^^;)
たくさんの仕立物を見せていただくし、解かせていただくがずいぶんと勉強させられる。
以外と多いのは裁ち間違い。
その他にも訪問着の柄があっていない、袖が反対、紋がずれてる、落款の入る場所が変! 辻も褄も合ってない、などなど
驚くような仕立て方も……
『この仕立屋さんはこれが変だとわかっていないんだな…』と思えるような、稚拙な間違いに出会うとプロ意識の無さに腹が立つ。
確実に『これは確信犯だな』と思える仕立て、つまり間違えたことをわからないように画策した形跡にあうと悲しくなる。
それはその仕立屋さんの小狡さに対してと、いうこともあるが、
実は仕立屋さんがそうせざろう得ないような、雇い主である呉服屋さんの容赦ない扱い方、ということにも傍らにはあるみたい。…
