
半幅帯でお尻も隠せてスッキリ粋な後見結び風
映画やドラマの中で見た素敵な帯結び、自分でも試してみたいと思ったことはないでしょうか?
1953年の映画「祇園囃子(ぎおんばやし)」の中で、踊りのお姉さんがよく結んでいるような帯結びで、「後見結び」という結び方があります。映画の中では六寸帯のような帯で結んでいるようでしたが、半幅帯で結んでいるシーンもありました。
帯結びでお尻が隠れてスッキリ見えるし、細かく長さを気にしなくても、すごく簡単に楽に結べる方法なので、ぜひ、試してみてください。
今回は、長尺の半幅帯を使ってお伝えしていきます。
※説明の中で、女将が使っている帯は、博多織の小袋帯で長さが4m30cmぐらいあります。
初心者でもテキト―でも簡単に結べる半幅結び
1)帯を腰にあて、手先を膝につくぐらいの長さで取ります。
2)帯を内側に斜めに折りあげて体の真ん中あたりでさらに外に折ります。こうすると、自然に帯の輪が下になります。
3)折り上げた部分をクリップで帯板に留めます。後で帯板を挟みこむ場合は、折り上げた手先をクリップで衿に留めます。
4)帯を体にひと巻きしたら、タレ側を持ち、体の脇でクッと締めます。
締めすぎると苦しくなるので、その日の体の調子などによって、締める具合を調節しましょう。たとえば、外を歩く時間が多いのであれば、キュッと締まってると気持ちが良かったり、長く座る時間が多いのであれば、少し緩くしておいた方が楽だったりします。ただ、その体感は人によって違うので、ご自分で試してみると良いと思います。
5)帯を締めたら、手先を下に落とします。その上にタレ側を持ってきて、手先側とタレ側を体から離すように引いて持ち、タレ側を手先側の下から上に通します。
6)タレ先を上に引いたら抜ききらずに、お好みの長さを残したまま、手先側とタレ先側をそれぞれ持って、キュッと締めます。
7)手先側とタレ先側が重なっている山をクリップで留めます。
博多織の帯など滑りやすい帯の場合、クリップで留めておくと緩みません。帯結びで見えなくなるので、留めたままでも大丈夫です。
8)タレ先側を下に落とし、重なっているタレ先側の帯をズラして形を整えます。
重なっている帯をズラして幅を出すことで、帯にボリューム感が出るので、身長の高い方や、お尻や腰幅が気になる方には、お尻が小さく見える効果が期待できます。
9)タレ先側を上にあげて肩にかけ、手先側を上に折り上げたらクリップで留めて広げます。
10)タレ側の帯を下におろしたら斜め内側に折り上げます。タレ先が長い場合は、折りたたんで長さを調節しましょう。
11)手先を返してタレの中に通します。
12)手の上を通るように帯締めを締めます。帯締めが結びにくい場合には、先に仮ひもで帯を押さえてから帯締めを通すとやりやすくなります。帯締めは、しっかりめに締めましょう。
13)全体のバランスを見ながら、形を整えていきます。
たとえば、タレ側の先が出ている方向を変えたり、タレから出ている手先の長さを調節したり、お好みのバランスになるように形を整えます。
14)帯結びを背中に回して完成です。
たとえば、手先を長めにとったり、タレ側で折り返した部分の大きさを小さくするなど、大きさや形が変わるだけで、全然違う表情になって印象も違ってきます。結びが平らなので、背中を押し付けるような車や電車の移動でも潰れることはありません。
きもの初心者でもテキトーでも簡単に結べて、お尻がスッキリ見える効果も期待できる「後見結び」風アレンジです。身長の高さや腰幅に合わせて、手先やタレを調節してみてください。
女将が出会った昔の映画の話から帯結びの説明に繋がっていく女将の動画はこちらをご覧ください。
【テキトーなのにお尻も隠せてスッキリ粋に!半幅結びで後見結び風アレンジ】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
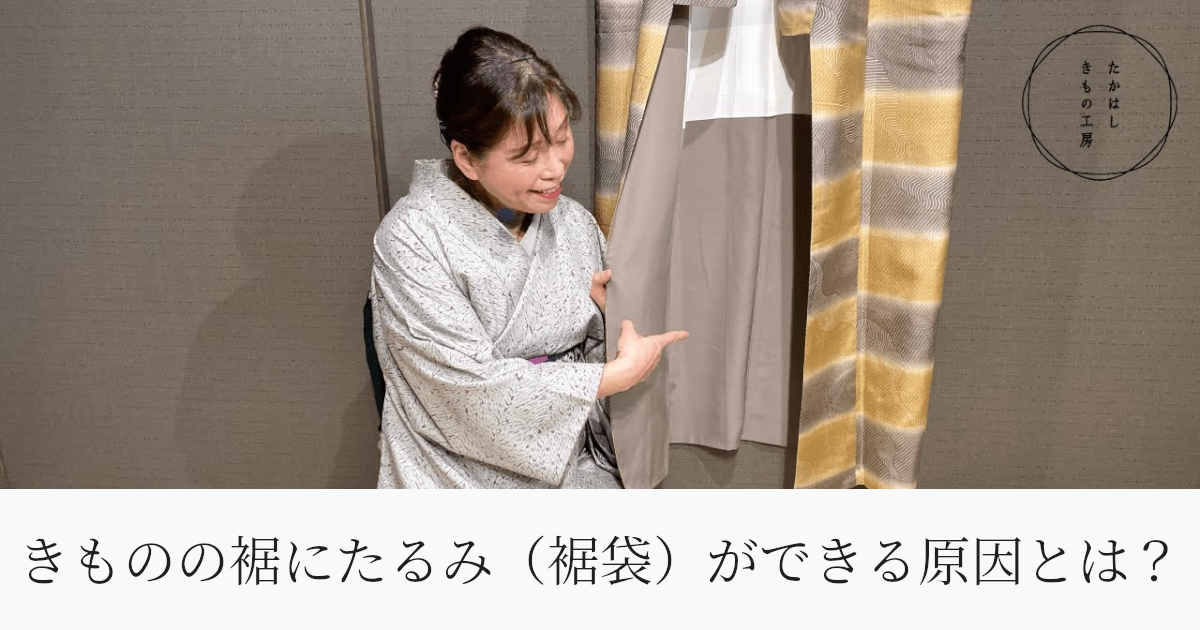
きものの裾にたるみ(裾袋)ができる原因とは?
袷のきものをきもの用ハンガーなどにつるしたときや、着付けで腰ひもを結んだときに、きものの表地の裾にたるみができた経験ありませんか?
このたるみを「動画では表袋(おもてぶくろ)以下同」と言いますが、特にやわらかもののきもので目立つと思います。
実は、この「表袋」は仕立てる時点でかなり回避できるにもかかわらず、その対策がされていない場合が多いようです。そのため、きものに袋が入ってしまうのは仕方がないことと思っている方も少なくないかもしれません。
今回は、「表袋」ができてしまう原因と「表袋」ができたきものの直し方の工夫をお届けしていきます。
もしかすると、きものを平らな場所に置いてピターっと表も裏も平らな状態で、きものをつるしてもピターッと「ゆるみ」がない状態がきれいな仕立てと思われていませんか?
一見、表も裏もピタピタッと合っているのがきれいな仕立てと思われがちですが、実は、着にくいんです。では、その理由をご紹介します。
裏地の「ゆるみ」には理由があった
まず、女将の訪問着を例に見ていきましょう。
表地は刺繍がされている生地なので、刺繍部分が裏地に響いてでこぼこしていますが、裏地を見ると全体に「ゆるみ」が入っています。
約10年前に仕立てたきもののため、経年による多少の縮みがあると思いますが、仕立ててすぐの頃はもっと「ゆるみ」がある状態だったと思います。
たかはしでは、裏に「ゆるみ」を入れる仕立てをします。裏に「ゆるみ」がなくピタピタの状態だと、表に袋ができてしまい着にくくなってしまうためです。
たとえば、やわらかものの縮緬の場合、表地の方が裏地よりも生地がずっと重いため、「ゆるみ」を入れずに仕立ててしまうと、着たときに裏地は体に沿うように付きますが、表地はすべって落ちるため「表袋」ができます。
和裁師さんは、その落ちる度合いや、経年による収縮や湿気による収縮を計算に入れて、裏地に「ゆるみ」を入れます。
そのため、仕立ててすぐの状態できものをつりさげると裏に「ゆるみ」がありますが、それが着やすいきものなのです。
逆に、着にくいきもの、必ず「表袋」になるというきものをお見せします。
実は「ゆるみ」がないきものは着にくい
この画像にあるようなきものを着ると「表袋」になります。
裏地に「ゆるみ」が全くありません。ピターッとしていて、むしろ表地に膨らんでいるぐらいになっています。
もし仕立て上がりがこのような状態だった場合には、仕立て直しを依頼しても良いと思います。
ただし、紬系のきものは生地が軽いので、やわらかものに比べると「表袋」になりにくいです。たとえば、大島紬の場合、表地は収縮しにくいのですが、それに比べると裏地が経年で収縮するため、それを計算して余計に「ゆるみ」を入れて仕立てたりします。
生地には経年収縮があるので、仕立てを工夫しても表袋になってしまうことはありますが、きものの着やすさを考えると、仕立てるときから「ゆとり」がなくピタピタに縫ってもらうのはできるだけ避けた方がよいと思います。
ぜひ、今後きものを仕立てるときに、お願いするお店の方に、裏地に「ゆるみ」を入れてくださいと伝えると、そのように仕立ててくれると思います。
一時期、きものを着ない時期に「ゆるみ」は要らない、ピターッと紙を畳んだように縫うことが良しとされたときがあって、「ゆるみ」を邪魔なものと考えていたのかもしれません。ただ、実際にきものを着だしたら、とても着にくいことがわかってきてたのではないでしょうか。
裏地に「ゆるみ」を入れて仕立てるというのは、きものを日常的に着ていた先人たちの大事な知恵ですね。
きものの裾の「たるみ」を解消する方法
すでに「表袋」になっているきものを着付けるには、腰ひもを締めてとめた後に整えることで、袋になった部分を解消することができます。
※腰ひもを締めて腰ひもに嚙んでいる生地をすべて引っぱり出した後に行います。
1)腰ひもの上の生地を触って、表地と裏地の二枚があることを確認します。
2)表地一枚だけをつまんで裾と一緒に持ち上げて引っぱります。
3)袋になっている部分の「たるみ」がなくなるまで、少しずつ引っぱりながら整えます。
※白枠内が袋を調整する前の状態です
このように着付けのときに調整すればよいとはいえ、着るたびに調整するのは大変です。
この裏地の「ゆるみ」に対しての知識が一般的になっていくと、きちんと着やすいきものを縫ってくれる和裁師さんが増えていくと思いませんか。
きものを仕立てるとき、裏の「ゆるみ」がある意味についても意識してみてください。
さまざまなご意見あることを承知の上で配信をきめた男気あふれる女将による動画はこちらをご覧ください。
【実は…あなたのきものにもあるかも!?きものの「裾袋」って何?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

きもの業界三大女将!?座談会・季節の移り変わりはどうすればいい?
きものを楽しむ中で、季節によって着分けるとき、たとえば、ネットの動画で見聞きした情報とお店で聞いた情報と、身近な人から聞いた内容とが、すべて微妙に違っていて、どれが正しいの?どうすればいいんだろう?と迷子になった経験はありませんか?
誰もが一度は経験されたことがあるのではないかという、季節の移り変わりでのきものの装いについて、きもの業界三大女将が本音で語っていただきました!
豪華ゲストお二方が気仙沼に
きもの英…

ここちよい着付けのために、補整する?しない?
きものを着付ける時に、補整をするのか、しないのか、ちょっとネット上を検索しただけでも、「補整は絶対した方がいい」とか「昔は補整してないのだから補整しなくて良い」とか、さまざまな意見が見られます。
たとえば、補整をせずに着る方たちの意見の中に、補整なしで着ると体型に沿って自然で良いという意見もあります。
一方で、そういった意見を聞いた方が、「私、補整してて、すみません」のような肩身の狭い思いをしている方がいるかもしれません。
着付けをするのに補整をするしないは、個人の自由なのですが、ここちよい着付けをするために、補整をしている方でも意外と知らない、たかはし流補整のイロハをお届けしていきます。
これから着付けを習う方や、習いたてというきもの初心者さんにも、ぜひ知ってほしい内容です。
「すっきり見える」だけじゃない補整をする理由
たかはしでは、「補」い「整」えるという字を使って「補整」をお伝えしています。
補整をする・しないは、どちらが上等かということではありません。
たとえば、自分にとって理想の着姿にするためや、自分にとって着ごこちのいい着付けに近づけるため、着付けの手間を減らしたいためなど、自分の好みに応じて、補整をする・しないを選ぶのが良いでしょう。
ちなみに、女将自身が「補整する・しない?」を聞かれたら、補整をする派です。
まず、補整をする目的として、全体的なバランスで考えた時、着姿がすっきり見えることです。きものを着るみなさんも望んでいることでしょうし、実は、すっきり見えるイコール着くずれしにくいんです。
たとえば、上半身が細くて、下半身にふわっと膨らみが出る体型をされている方。中年以降になると、特に腰まわりに浮き輪のようにお肉が付いてきやすいです。それ以外でも、上半身やウェストはすごく細くてお尻に向かって張ってきて、下半身にボリュームが出やすい骨格診断でウェーブ体型と言われる方がいらっしゃいます。
ウェーブ体型の方が、ウェストに合わせた上半身の着付けをすると、下半身のボリュームが強調される形になり、パーンとお尻が張って見えてしまいます。
この場合、ウエスト補整を入れることでお尻が小さく見える効果が得られます。
きものの生地は、タテ糸とヨコ糸が真横×垂直に重なって織られています。この生地目を意識して体に沿わせるようにすると、シワがよりにくくなります。
たとえば、裾を下すぼまりにしたい時、ウエストが細くてお尻が張っていると、お尻の部分で生地が引っ張られて歪みができます。そのため、最初は下すぼまりになっていても、歩くことで生地に力がかかっていくと、裾が開いてきてしまいます。
このように、お尻や太ももに張りがある体型の場合、裾が広がりやすいのです。生地の力にあらがって着付けているので、当然着くずれやすいです。
ウエストをお尻や太ももの張りに合わせて補整を入れ、できるかぎり真っ直ぐ寸胴にすると、生地がピタッと体に沿うようになります。
そのため、下すぼまりになった裾に対して、そのまま生地が上に上がるので歪みができにくいです。すると、生地の落ち着きが良くなり、着くずれしにくくなります。
さらに、一番気になるお腹の肉や腰肉は、帯を締めた後にぽっこり下腹として出てきてしまいがちです。たとえおはしょりを1枚にしてきれいにしても、立ち座りで腰に帯がぶつかって動くことで、上半身がブカブカと緩むことでも、着くずれに繋がります。
また、長い帯板を使うとどすこい体型に見え、帯板が腰にぶつかって着くずれてしまう場合があります。帯は細い部分に滑って移動していくので、帯と一緒に生地も動き、上半身の生地が緩みブカブカになって着くずれてしまいます。
お腹まわりのお肉が浮き輪のようにつき始めると、お肉を押さえこみたい気持ちになりますよね。
ただ、腰まわりのお肉を押さえ込んだとしても、ウエストが細いままだと腰まわりが張った状態になってしまいます。だから、ウエストに補整を入れていくと良いのですが、補整を入れれば入れるほど、太って見えることを心配されると思います。
そこで、補整の詰め物を多用せず、自分のお肉を持ち上げて、お肉を動かす、という新発想の補整を実現してくれるのが、「満点腰すっきりパッドスキニー」です。補整のための詰め物が少なくても補整が簡単にできるし、一発で補整が決まるという点も大きなメリットです。
パッドスキニーを、一番くびれているウエストだけ付けるのではなく、かならず骨盤にもかかる形でお肉をキューッと締めるように付けることで、お肉が動いていきます。(スポーツをされてきた方で筋肉質な方の場合、筋肉は動きにくいのでその上に補整を足すこともあります。)
自分のお肉がウエストの補整として入っていくため、パッドスキニーを使うとサイズダウンすることもあります。
仮に、補整は一切、付けなくて裾が広がってしまっても全然良いですという場合、それはその人の個性だと思いますし、ひとつの着方でもあると思います。
たとえば、補整を何もしなくても寸胴な体型ですという方もいますし、腰の曲線がなく真っ直ぐな方もいますので、補整が必要なのかどうかは、その人の体型にもよります。
下半身の補整を例に、お伝えしてきましたが、胸元を寄せて上げることも上半身の補整のひとつです。
胸のお肉が横に広がるような感じがする、下に落ちてしまうという場合、補整でお肉を上げることができたらすっきりと見えます。もし、胸のお肉をつぶして補整した方が良いと感じているのであれば、それが良いと思います。
かならず、こうしなければならない、ということはないのです。
大切なきものにも補整が効く理由
着姿や着ごこちに加えて、補整をすることは、きものを守ることにも繋がります。
タオルや補整アイテムを使用すると、その分、吸水性が上がるので、汗がきものに移ることを軽減することができます。
もちろん、補整をしたことで暑くて汗の量が増えるという側面もあります。
以上のことから、補整をする意味は大きくふたつです。
ひとつは、生地をすっきり体にまとわせることで着くずれを防ぐこと。もうひとつは、きものを守ることです。
着付けをするのに何を選び取るかは人それぞれです。これらふたつを考え合わせて、たとえば、補整を入れる量を季節によって調整するなど、考えると良いでしょう。
補整をする・しないは、上も下もなくフラットに考えて、自分の体に聞いて、選んでいくと良いと思います。
すべては自分の感覚と自分で選び取ったものを信じて、その上でここちよい着付けをされることで、もっときものを楽しめるようになると良いですよね。
ここちよい着付けをするために、女将の愛と理論と情熱がつまった動画はこちらをご覧ください。
【きもの初心者さんにも知ってほしい!ここちいい着付けの為に!補整ってしないとダメ?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

初心者の着付けも楽になる着やすいきものの生地感とは
きもの初心者の方から「着付けを練習する時、どんなきものが良いですか?」と聞かれることがあります。
きもの初心者の方たちが、その人にとって一番覚えやすい着付けを覚えるまでは、着にくい素材のきものは避けた方が良いと思います。なぜなら、まだ手の使い方に慣れていないからです。
たかはしでは、きもの初心者の方でも着やすいきものとして、ちょっとマットな質感の紬をおすすめしています。
なぜその結論になったのかも含めて、三種類の生地を例にしてお伝えしていきます。
これから着付けを練習するきもの初心者の方はもちろん、すでに自分で着られる腕があるのになかなか上手くならないと感じている方も、生地による着やすさの違いを知ることで、もっと楽に上達できるかもしれません。
やわらかものの小紋、マットな紬、浴衣を例に、生地感による着やすさの違いを知っていただければと思います。
摩擦力による生地感の違い
よく大島紬は着やすいという方がいらっしゃいます。確かに着きやすいです。
ただ、まだ手が慣れていない初心者の方が大島紬を着ようとすると生地が滑ります。
生地はその質感によって表面がツルツルとして滑らかな生地(摩擦力が小さい)と、表面に凹凸があって摩擦力が大きい生地とに大別されます。大島紬はツルツルとしている生地に属します。
結城紬はどちらかというと摩擦力の大きい生地に近いです。ただ、絹なので木綿に比べると滑ります。程よく滑って程よく止まる生地というのは、摩擦力が大きすぎないものです。
たとえば、十日町きものや結城紬などは、マットな質感の紬です。他の生地と比較するために、結城紬を用意しています。
やわらかもののきものは一見すると着やすそうに見えるかもしれません。でも実際は、着付けに慣れないうちは生地がズルズルと手から逃げやすく扱いにくいです。生地に落ち感があるため、生地を上に上げようとしても下に落ちやすいので、いつもの要領でやってみたらおはしょりが長くなるということもありがちです。
生地をキュッと体に張らないとスルスルと落ちていくので、手が慣れていないと扱いが難しいと思います。
ここまでの話から、ツルツルしていないし、汚しても自宅で洗えるし、木綿きものが気軽で良いんじゃない?と思われるかもしれません。確かに汚れた時のことを考えたら、浴衣で練習すれば良いのでは?と思うのも当然です。
たかはしスタイルの着方教室では、一番最初から浴衣は教えていません。
なぜかというと、生地の摩擦力が大きいので、上前と下前を重ねた状態で生地を引っ張っていくと、生地が滑らずゆがみができます。そのため、きれいな着姿にするには、体から離して重ねるようなコツが必要です。
では、生地感による着付けやすさの違いを、ボディへの着付けで見てみましょう。
初心者が特に着にくいやわらかもののきもの
生地を体に沿わせるようにぴったりと当てていないと、きものが全部下に落ちていきます。
そうならないためには、ぴったりとお尻に生地をつけた状態で生地をずっと持っていられたら生地が落ちにくいです。
このコツは、今から新しく習いますという方には難しくて、最初は体にぴったりと沿わせることなく、ゆとりがある状態で着付けようとしてしまいがちです。するとどんどん生地が落ちていきますし、片方の手で押さえながら上前に嚙んでいる下前の生地を抜こうとすると、手で押さえていない方の生地が落ちていったりと、とても扱いにくいと思います。
上半身の胸元をきれいにすることは難しいことではありませんが、下半身をきれいにするとなると、落ち感のあるきものはすごく大変です。
初心者にも着やすくおすすめ!マットな質感の紬
マットな質感の紬系のきものは、持った時点で軽いです。上前を合わせた後、下前を体にぴったりと沿わせることが無くても、生地が落ちていくことはありません。
たとえば、生地を押さえている手を替えるという時も、一か所でも押さえておけば、生地が止まっててくれます。
ゆるく体に沿わせてあげれば、程よい摩擦力があるので生地が止まっててくれます。
腰ひもを結ぶところをきれいに整える時も、生地が止まっているのでそれほど難しくなく生地を整えることができると思います。
きものを着付ける時、生地を体にピタッと沿わせることは基本ですが、最初はそれがうまくできないことが多いので、生地が軽くて押さえやすく扱いやすいきものが着やすいです。
本当は難しい浴衣や木綿、ウールのきもの
上半身だとわかりやすいので、腰ひもを締めた状態で他の生地との違いを見ていきます。
腰ひもを締めた後、おはしょりをトントンして整えていきます。
先に下前を整えた後、上前を体に沿わせるようにすると、生地の摩擦力が大きいため、上前の生地と一緒に下前の生地が動いてしまいます。
きれいに整えるためには、生地を体から離して重ねるようにします。
生地目も整えないと生地がぶかぶかしてきれいに整えることができません。
おはしょりの中の下前の生地も体に合わせてきれいに折りたたむ必要があります。
たとえば、誂た浴衣で生地にハリ感のあるものだと、ノリによるハリがあってきれいに着るにはコツが必要で、きもの初心者の方だと難しいわけです。
生地を下に下げたいと思っても、摩擦によって体に吸いついたようになって、なかなか思うように動かないと思います。生地を動かすためには、体と生地の間に手を入れて、体から生地をいったん離すと動きやすくなります。
生地目をきっちりひとつひとつ整えていくのが難しい生地は、摩擦力が大きい生地です。
木綿やウールもその傾向があります。
着やすい生地を選ぶための摩擦力を何で見分ける?
着るものの摩擦力の大きさを何で見分けるのかというと、毛羽立ちの多さです。
麻以外の天然繊維は生地に対しての毛羽立ちが多いです。毛羽立ちが多いほど、摩擦力が大きい生地になります。絹も天然繊維ですが、糸の生成によってツルツルと滑らかになっており、摩擦力が小さくなります。
大島紬もどちらかというとツルツルとして手から逃げやすい傾向があるので、ちょっとマットな紬が良いと思います。
浴衣はきものに比べると、手に取る気軽さがあるせいか、浴衣ぐらい着られるんじゃないかとよく聞きますが、実際には浴衣をきれいに着付けるのは難しいです。
なぜなら、体の線は出やすいですし、生地の摩擦を意識しながら体から離して整えていかないといけないので、意外と難しいのです。
これから着付けを練習されるきもの初心者の方は、程よく滑って程よく止まる軽い生地を目指して練習するきものを決めていただければと思います。
写真だと伝わりにくいですが、動画だと生地感がよりわかりやすいです。女将による生地による着付けのしやすさの違いの動画はこちらをご覧ください。
【知れば着付けが楽になる!『初心者必見!』着やすいきものの生地感】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

自分に合う呉服屋さんを気軽に探せる方法
ここ数年できものを楽しむようになられた方は、最初はお母さまのきものや、おばあさまのきもの、リサイクルきものなど、身近にあるきものや既に仕立てられているきものから始めた方がほとんどなのではないでしょうか。恐らく、呉服屋さんできものをまず一枚買ってから始めたという方は、少ないと思います。
呉服屋さんで開催されている着付け教室などをきっかけに、そのお店の馴染みになると、買い物がしやすくなったり、ちょっとした疑問も聞きやすいということがあるでしょう。
しかし、呉服屋さんとまったく接点の無い場合、呉服屋さんに気軽に入ることができないという声をよく聞くことがあります。
気軽に呉服屋さんに入ることができない原因としては、
呉服屋さんでこんな風に言われて悲しかった
希望を伝えたのに希望の通りに仕立ててもらえなかった
すごく高額な商品を買わされたらという不安がある
買うつもりが無いのに行ってはいけないのではないか
など、ネット上などでネガティブな情報を目にすることが考えられます。
日常できものをもっと楽しむために、今回は、呉服屋さんとの上手な付き合い方をお伝えします。
日常できものを楽しむための呉服屋さんとの付き合い方
理想は、お住まいの近くで直接相談に乗ってくれる呉服屋さんがあると、すごく良いです。御用達のお店になるような地元の呉服屋さんと一軒は繋がっておくことをおすすめします。
ただ、その一軒のお店だけに絞って行くということではなく、核となるお店を見つけ、目的に応じて複数のお店を使い分けると良いです。
たとえば、地元の呉服屋さんを核とするお店として、大手チェーン店の呉服屋さん、リサイクルきもの屋さんなど、目的に合わせて通うというような形です。
核となるお店に、自分の寸法や持っているきものや好みなど、いろんなことをわかってもらっていることが、きものライフを楽しむにあたって大きなメリットになります。
たとえば・・・
素敵な帯を見つけた時、手持ちのきものに合うかどうかがわかる
着合わせを考えた時、何か弊害がある場合、それは止めた方が良いなどのアドバイスがもらえる
小物を選ぶ時、手持ちの小物と似ている場合に、新たに加える色味としておすすめの小物を提案してもらえる
このように、何か商品を選ぶ際にも、着ることを前提とした提案がもらえて、着方や着合わせについても相談に乗ってもらえると、きものの楽しみ方の幅が広がりますよね。
また、核とするお店に、地元の呉服屋さんをおすすめしたい理由がふたつあります。
ひとつめは、チェーン店の呉服屋さんの場合、転勤によって人が移動してしまう可能性があるからです。地元の呉服屋さんの場合は、その可能性が低いです。
ふたつめは、チェーン店の呉服屋さんの場合、そのお店の方の想いだけで経営しているわけではないため、担当する人が替わることで齟齬が発生する可能性もあります。地元の呉服屋さんの場合、経営者が直接接客する場合もあり、相対的にその可能性が低くなります。
そのため、長い目で見て考えると、地元の呉服屋さんを核になるお店にしておくと良いです。
いずれにしても、付き合っていくお店の中で、確実にこの人だったら信頼できると思える人が見つかる事が一番です。
長く付き合える呉服屋さんを見つけるには
長く付き合える呉服屋さんを見つけるには、日常できものを着ることを前提にしているかどうかを、取り扱いしている商品の種類やスタッフの対応を見ていくと良いです。
まず、商品の取り扱いについて。きものや帯だけではなく、肌着や帯揚げ、帯締めなど、きものを着る時に必要な小物が充実しているかどうかが重要なポイントです。
昔は、きものを買うだけで着ないお客さまは沢山いらっしゃいましたが、今はきものを買う方や呉服屋さんに入ってみたい方にとっては、きものを着ることにプラスになるお店を探していると思います。
きものを着るためにいい商品の提案があるというのも選ぶ視点のひとつではありますが、きものを着ることに即して経営しているお店が、きものを着ることにプラスになるお店です。
たとえば、きものと帯は沢山取り扱いがあるのに、帯揚げや帯締めがほとんど置いていないお店の場合、きもののコーディネートには興味が無い可能性が高いです。
逆に、小物の提案があるお店や寸法の相談に乗ってくれるようなお店は、着ることにとても興味があるお店の可能性が高いわけです。
次に、接客してくれるスタッフについて。着方や着合わせの相談はもちろん、お客さまからの質問に対して、親身になって対応してくれるかなどが、ポイントになってくると思います。
たとえば、帯締めや帯揚げなどの小物を買おうとしている時、その商品についての話だけではなく、疑問に思っていることや、次に着ていく場所にどんなものを着たら良いのかなど、着る時を想定して会話がされているかどうかで、自分との相性も確かめられると思います。
お客さまの話をあまり聞かずに、一方的に決めつけるのではなく、一緒に相談しながら選んだり決めたりできるかどうかが、きものを着始めた方には必要なお店だと考えています。
こうじゃなきゃダメですというような形ではなく、多方面からの視点で提案がもらえるお店なら長くお付き合いできると思いますし、お客さまが疲れたり、がっかりすることも少ないでしょう。
実際に、自分に合う呉服屋さんを見つけるには、そのお店に来店して、確かめるほか無いわけですが、呉服屋さんに行くのに一番ハードルが低いのは、お友達の御用達のお店に一緒に連れて行ってもらうケースです。お店と自分の間に、仲介してくれる人がいるから非常に安心ですよね。
ただ、注意したいのは、お友達にとってベストなお店であっても、自分にとってベストなお店かどうかはわかりません。そのため、最初は一歩引いた気持ちで、自分の感覚でお店を見ていくと良いと思います。
一人でもできる気軽に呉服屋さんに入る方法
お友達の御用達のお店に行く時も、ひとりで呉服屋さんに行く時も、試してもらいたいことがあります。これは、呉服屋さんに入る口実にもなるので、気軽に呉服屋さんに入りやすくなる方法です。
それは、「きものについて、ちょっと教えてくれませんか?」と呉服屋さんに入ってみることです。
たとえば、着合わせの話や、寸法について、リサイクルきものを着ていて困っている点など、買う目的ではないけれど聞いてもいいですかという体で、尋ねてみることです。
これは呉服屋さんにとっても、話のきっかけになり、お客さまとの接点にもなります。
きものを楽しむために、良いお付き合いが長くできるお店を探すのであれば、ぜひいろんなお店に沢山入ってみることをおすすめします。
いろんな呉服屋さんに行って、自分に合う呉服屋さんかどうかを探していく中で、このお店なら信頼できる呉服屋さんが見つかったなら、一度きものを仕立ててみると、きものの楽しみ方が広がります。
きものを仕立てるために、寸法をメジャーで測っただけで決めて仕立てた場合、寸法が狂う可能性もあります。そのため、サンプルのきものを試着することで、より体に合った寸法に調整してくれるお店もあります。
ただ、そのようにして仕立てた場合であっても、一回の仕立てで一番着やすいベストなきものには、なかなかたどり着かないです。
なぜなら、選んだ反物の生地の落ち感にもよりますし、サンプルを試着したとしても、着る時の腰ひもの位置がズレると身丈も変わります。裄についても、礼装用と日常用では寸法が違います。仕立て方の袷と単衣でも違ってきます。これを言い出すとキリが無いので、ここで留めておきます。
まったく同じ寸法できものを仕立てたとしても、すごく自分に合ってて良い感じという時と、ちょっとその感じとは違うという時もあるのはそのためです。
きものを纏った感覚を体感し、いろんなことを考え出すとキリが無いですが、だからこそ自分なりのこだわりが生まれることも、きものの楽しみのひとつではないでしょうか。
人間だものトラブルもあるけれど、幸せもある
いろんな呉服店さんと付き合っていく中で、ちょっとしたトラブルもまったく起こらないということは、ほとんど無いと思います。誰もが人間なので、失礼なこともあるかもしれませんし、間違いも起こることもあるでしょう。
そのため、自分に合う呉服店さんを探していく別の視点として、何かトラブルがあった時の解決方法で、判断できることが多いと思います。
以前、きものをどこかの呉服屋さんで買った時の経験をSNS投稿されていた内容を事例にお伝えします。
そのお客さまは、希望の寸法を持っていき、その通りに仕立てて欲しいと頼んだそうです。しかし、仕上がってきたきものはその寸法の通りにはなっていなかったので、直してほしいと依頼したところ、そのお店では「あなたの身長からこちらが判断して仕立てた」と言われたそうです。
この場合、お店側でお客さまが希望された寸法に問題があると思ったのであれば、仕立てる前にお客さまに伝えた方が、このトラブルを回避することができたでしょう。
会話をすることで、たとえば、この身丈だと短いと思いますと伝えたら、私は余分は一切要らないのでぴったりにしたいのでこの寸法で仕立てて欲しいという会話になったのかもしれません。お客さまが希望した寸法の理由がわかれば、希望した寸法で仕立てることができたのでしょう。
以前のように、きものをあまり着なかった時代には、きものを人に着せてもらうことが多かったので、身丈を長めに仕立てるのが一般的でした。そのため、仕立てる寸法を任せますということになると、身丈が長めに仕立てられる可能性が高いです。
このようにトラブルがあった時、すぐに謝ってくれるお店だと、気持ちよく付き合っていけますよね。
ただ、これは逆にお客さまの場合も同じです。お店に任せると言ったのであれば、任せた責任がお客さまにはあります。その結果、もし自分の思い通りにならなかった時、一方的にお店が悪いと決めつけて文句を言ってしまうと、お店との良い関係性を築いていくのは難しくなります。
お店もお客さまも、腹がくくれているかどうかということが、良い関係を築けるかどうかというところの分かれ道になります。
お店と良い関係性を築いていくなら、何か気づいたことがあれば素直にそれを伝える環境を築いていくことに意識を向けてもらえると、お互いにとって良い関係ができていくと思います。
どうぞ恐れずに、教えてもらいたいことを持って、呉服屋さんにどんどん入ってください。もしお店の人に面倒くさがられたら二度と行かなければ良いだけですし、もし間違えて謝ってもくれないお店はもう行かなければ良いだけですから。
これまで呉服屋さんに行ったことがある方にとっては、今までがっかりした経験もあるでしょうけれど、逆にすっごく幸せな経験をされたこともあると思います。
きものライフは、自分一人での楽しみもありますが、一人だけの楽しみじゃないと考えています。
きものを通して人の輪を広げていくことで生まれる楽しみは、人との関わりで楽しみが増幅されるような感じを経験されたことはないでしょうか。その人の輪の中には、お友達はもちろん、お店もあって欲しいと願っています。
今は、呉服屋さんとの関わりは無く、ネットで全部揃える方も多いかもしれませんが、直接的な人間と人間との関わりの中で、より深まっていく思いが生まれるはずです。
そういった経験も共有しながら、どんどんみんなでお互いに良い形を目指しながら手を携えて、きものがもっと楽しいものになったらいいなと思っています。
ぜひ核となるお店を見つけて、きものライフがより楽しくなるようなお店との関係性を築いていっていただければと思います。
ぜひ呉服屋さんに行ってもらいたいと本気で思っている女将の動画はこちらをご覧ください。
【自分に合う呉服屋さんを探すコツ&気軽に入る技を伝授!こわくない!ドンドン入ろう呉服屋さん♪】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
