投稿

浴衣をきもの風に楽しむためのちょい広バチ衿
夏に浴衣を着るのに、浴衣としてはもちろん、きもの風にも着たいと思ったことありませんか?
以前、綿麻や麻のきものや浴衣を、浴衣としてもきもの風にも、どちらも対応できるようにするために、ちょい広バチ衿が良いですとお伝えしました。
以前、ご紹介した「ちょい広バチ衿」はこちら
https://k-takahasi.com/blog/2022/10/10887/
「ちょい広バチ衿」の動画はこちら
この動画でお伝えした「ちょい広バチ衿」の仕立て方について、誤解を生んでしまったようなので今回、改めて「ちょい広バチ衿」についてお届けしていきます。
「ちょい広バチ衿」≠「広衿をバチ衿にしたもの」
以前、紹介した動画を見た方が、「ちょい広バチ衿」にしてくださいと呉服屋さんにお願いしたら、呉服屋さんが困ってしまったということがあったそうです。実際、呉服屋さんから直接お問い合わせをいただいたこともありました。
たかはしきもの工房のYouTubeの動画のコメント欄にも、
「ちょい広バチ衿にしてくださいと伝えたら、仕立て屋さんから裏衿が必要です。」
と言われたという書き込みをいただきました。
そして、「ちょい広バチ衿」には裏衿を使うのかという問い合わせもいただいたのです。
さらに、「あづまやきものひろば」の柴川さんが、「ちょい広バチ衿」について動画の中で話されていたというのですが、女将が伝えたかった衿とは異なっているようでした。
柴川さんの話に出ていたのは、よくアンティークのきものや、おばあちゃんの箪笥から出てきたきもので見かける衿のことかもしれません。
広衿のきものは、衿の内側にある「引き糸」や「スナップボタン」を使って衿を折りますが、その衿の部分を元々縫い留めてしまう仕立て方があります。
恐らく、日常できものを着る場合に、衿を折って着るのは面倒くさいから、衿を折る必要がなくなれば便利だからという理由でできたのではないでしょうか。
広衿のきものの衿を折って縫う仕立て方を「ちょい広バチ衿」と想定したことで、仕立て屋さんや和裁師さんにも誤解が生じてしまったのではないかと予想されます。
夏に浴衣や夏きものを楽しむためのご提案としての「ちょい広バチ衿」は、より涼しさを重視したいので、夏物に裏衿を付けるということはいたしません。なぜなら、生地の厚みで衿が膨れて、余計に暑さを感じてしまうためです。
たかはしで提案する「ちょい広バチ衿」とは、バチ衿の幅を少し広げることだけを指しています。
「ちょい広バチ衿」=バチ衿の幅を少し広げること
衿幅の違いがどんなことに影響するのかをお伝えしていきます。
二種類の浴衣に衿を入れてきもの風にしていますが、比べると衿幅が違うことが分かると思います。
向かって左側は、既製品の浴衣です。
衿幅が背中心で約5.5cm、胸元の部分で約6.5cmと、背中と胸元でおよそ1㎝の差があります。
「バチ衿」とは、三味線のバチのように持ち手から先端に向かって幅が広がっているように、背中から衿先の方に向かって、衿幅が少しずつ広がっている衿のことです。一方、背中から衿先に向かって一定の衿幅の衿を「棒衿」と呼んでいます。
一般的な既製品の浴衣は、「バチ衿」になっていて少し胸元で衿幅が広くなっています。
向かって右側は、綿麻の反物を浴衣に仕立てたものです。
きもの風にも着られるようにと背中心では約5.5cmですが、胸元で衿幅が広くなるようにした衿になっていますが、これも「バチ衿」です。裏衿を付けずに衿を半分に折って作っている「バチ衿」になります。
女将は身長が高め(164㎝)ですし、きものについて様々な実験をするために、背中心の衿幅を5.5cmではなく、6㎝にして仕立ててみたところ、暑苦しく感じたそうです。
そのため、たかはしでは背中心の衿幅は5.5cmを推奨します。身長が170cm以上の方であれば、少し衿幅を増やしても良いかもしれません。たとえば、IKKOさんは、一般的な衿幅に比べると相当衿幅を広くしています。
きものの寸法が考えられた昔と今とでは、平均身長が変わっています。学校保健統計調査によると、約100年前と比べ、女性の平均身長は約10cm弱高くなっているそうです。
きものの寸法は着る人の身長や体型に合わせたものであるので、縦に伸びた分、横幅がまったく変わらないわけはないと考えています。たとえば、比率で考えた時、縦に120%伸びたら、横に120%の幅になるわけです。
そのため、身長や体型に合わせて衿幅を調整した方が、きものの着姿がキレイに見えます。
「ちょい広バチ衿」にするための衿幅は?
「ちょい広バチ衿」に仕立てるために、衿幅をどの部分から広げると良いのかというと、
女将の結論としては、次の通り。
背中(背中心)の衿幅は5.5cm
耳の下、肩のあたりから少しずつ衿幅を広げていく
衿を入れずに着ると、向かって左側の方が涼しげに感じませんか?
ただ、身長が高めの方の場合、左側の衿幅だと、衿元が貧相な感じに見えてしまう場合もあります。
せっかく浴衣を仕立てるのであれば、浴衣地も質の良いものが多く出回っていますし、価格も高くなっているので、きもの風にも楽しめると着られる機会も増えて良いですよね。きもの風にも着るためには、衿幅を広くすると胸元がゆったりとしバランスよく見えます。
どのくらい衿幅を広げれば衿元や胸元がキレイに見えるのかを、衿幅のイメージができるように、5.5㎝幅に畳んだものを背中にクリップで留めています。
背中の衿幅と同じ5.5cm幅のまま「棒衿」にした場合のイメージです。
江戸前のチャキチャキしたような躍動感や普段着のカジュアル感があって、可愛らしさも出る衿幅です。
きもの風にも着たいと考えると、衿幅を広げた方が良いと思います。
既製品の浴衣の場合だと、6.5cmぐらいなので「棒衿」に比べても、あまり大きな差は感じないかもしれません。
※左側が「棒衿」で、右側が胸元あたりで衿幅が約6.5cmの「バチ衿」
さらに衿幅を広げて胸元で7.5cmぐらいの幅になると、きもの風に感じられると思います。
このように衿幅によって、着姿の印象に違いが出ますよね。
たとえば、礼装用の訪問着の場合、衿幅を広くすることによって、カジュアル感よりもフォーマルで優雅な雰囲気に感じられます。
また、衿を広くすることで、肩線が外側に移動するので、肩幅がスッキリと見える効果もあります。
ただ、身長が低い方や細身の方が衿幅を広くすると、バランスがよくありません。身長が高く、大柄の男性の場合には、衿幅を広げた方がバランスよく着こなせるはずです。また、女性も同じように、たとえば、とてもグラマラスな方は衿幅が広い方がスッキリと見えます。
このように衿幅による見え方の違いを踏まえて、浴衣での「ちょい広バチ衿」を提案しています。
きものの衿は、基本的には反物を半分に割った生地を使用して作ります。反物幅が40cmとすると、半分に割ったものが20cm幅の生地。その生地をさらに2つに折ると10cmあるので、縫い代部分を除くと、最大で9cmの衿幅を作ることができます。
ところが、9cmの幅となるとものすごく広い衿幅になるので、広げたとしてもせいぜい8cmくらいまでとなるでしょう。
ただ、できるだけ衿を汚したくないと衿幅を細くと思われるかもしれません。でも実は、衿を汚れにくくするためには衿幅で調整するよりも、衿を首からどれだけ離して着付けられるのかが大切です。
衿が首にくっついてしまう場合は、首の後ろの衿を横に広げるようにして着付けることで、首から衿が離れるので、衿幅を広くしても衿が汚れにくくなります。
普段着テイストを残しつつ、衿を入れることできもの風に着る場合には、身長や肩幅、胸幅によって、7~8cmぐらいで衿幅を割り出すのが良いでしょう。
背中心の衿幅が約5.5cmで、胸元に向かって衿幅をどのぐらいに広げると格好いい着姿になるのかを把握するために、自分で鏡を見ながら手持ちの広衿のきもので試してみても良いかと思います。
浴衣を浴衣として着たり、衿を入れてきもの風にも着たりと、夏のきものの楽しみ方に繋がれば嬉しいです。
女将による「ちょい広バチ衿」の動画はこちらをご覧ください。
【ゆかたをきものチックに楽しむ!ちょい広バチ衿のすすめ完全版】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

浴衣が似合わない…40代から浴衣を着るなら【きもの初心者必見】
ある夏、自撮りの浴衣姿を見て驚愕しました(@_@)
こんにちは。たかはし二年目&きもの初心者の佐藤めぐみです。
たかはしで開催される数ある催事・イベントで、私が一番最初に参加したのが「ゆかたでビアガーデン」でした。ドレスコードが浴衣(夏きもの可)で、どなたでも参加できます。参加する際、ネット通販で浴衣セットを買ったのです。
久しぶりにその浴衣を着たら「まるで、バ○ボン」(@_@)
上半身のボリュームドーン!そして、明らかに似合っていない…。
※浴衣姿の上半身
「ゆかたでビアガーデン」に参加されたマダムたちの浴衣姿は、とっても粋で素敵なので憧れちゃいます。自分も少しでも浴衣姿が素敵なマダムに近づきたい!(^^)!
ならば佐藤きもの初心者「40代&少しスラリ(※)」に似合う浴衣は何だ~?と、「浴衣…

全部ほどいて無駄なくリメイクできる【きもの初心者必見】
こんにちは。新人(2年目)の鷹木です!
先日、気仙沼市の隣の隣の市にある某イ○ンモールをプラプラしていた時、着物を扱っているお店の‟ママ振りリメイク“…たる宣伝が目につき、吸い寄せられるかのようにそのお店へ。
もう夏の時期から冬の成人式に向けて準備も始まっているんだなぁと思いつつ、ママの振袖を素敵にお直しして着るかぁ、ふんふん、どれどれ、いいなぁ(._.)と見入っておりました。
そのため、側に来ていろいろと話しかけてくれた店員さんの話が、全然入ってこなかった私でした…。(ごめんなさーい(^▽^;))
という事で今回のテーマは、着物は「リメイク」できることです!
着物は”ほどいて”お直しできちゃう!
以前の記事で、(誰かの)決まったサイズでできている着物でも、着付けの仕方で体格差をカバーして着回しできることをご紹介しました。
※詳しくは”着回し”って体格差があっても大丈夫?!をご覧ください。
ただし、着付けの工夫ではどうにもならない…という場合はお直しが必要なことも学んでいました。この場合のお直しは、小さい着物を大きくするために「縫い代」や「内揚げ」を出して広げるという方法でした。
その方法とは異なり、全部ほどいてまるっとサイズ替え!または着物を洋服にも作り直せちゃうというのだから驚きました。
着物はひとつの反物から直線裁ちで裁断し、すべてのパーツをほぼ直線で縫っています。そのため、仕立てられた着物をほどくと、また一枚の生地に戻るので、無駄な生地がない!ということなのです。
なるほど!細かいパーツになっていない、大中小、様々な生地に戻るのだから、その使い道は自由なんだ!
色柄だって変えれちゃう!
古くなった着物を別の色や柄に染め直し、新しい着物(生地)に生まれ変わらせる‟染め直し“という技術を使えば、仕立て直しもリメイクも更に楽しくなることもわかりました!
染め直しの方法には、
元の色を抜かず、そのまま上から同系色の濃色、もしくは暗色をかけて染めるシンプルな方法の「色揚げ」
着物を脱色してから他の色に染める「染め替え」
色合いが華やかな着物の全体に色を加え、渋く落ち着いた色合いにする「目引き」
着物をほどかず丸のままの状態で染め直しを行う「丸染め」
着物の柄の部分を染めずに地色だけを染め直す「柄染め」
着物に新たに絵柄・模様を付け足す「柄足し」
など、こんなに様々な方法があったことも驚きです!
着物のリメイクに関連して、今は亡き祖母が元気だった頃の思い出を思い出しました。
亡き祖母の浴衣がリメイクで復活
気仙沼では、毎年夏になると「気仙沼みなと祭り」が開催されます。小学校までは家族や親戚と楽しんでいたお祭りも、中学になると友達と行くようになりました。その時の浴衣は、今は亡き祖母が私のために手作りしてくれたものでした。
当時、祖母は反物を何枚かのパーツに大きく切って、絵柄が素敵に見えるところを考えながら、型紙も無しに浴衣を作っていた記憶があります。(最近やっと、きものに型紙はないということもしりました!)夏休みのお祭りを迎える前に、祖母は毎日コツコツと手縫いで針を動かしていてくれたことを思うと、私にとってその浴衣はとても特別な浴衣になりました。
この祖母の手縫いの浴衣を高校生までは毎年着ていましたが、着付けができる人が周りに居なかったこともあり、地元を離れて学生・社会人になるとまったく着なくなってしまいました。
数年を経て、久しぶりに浴衣を着たいと思えた頃には、その時代に合った色柄や、年齢に応じた大人っぽい柄の浴衣が欲しくなり、新しい浴衣を買って着ていました。
その後、20年近くもたんすの中に眠っていた思い出の浴衣が、復活の機会を得ることができたのです。
なんと、母の友人のお母さん(もう90歳オーバーのお婆ちゃんです!)が、簡単な物であれば浴衣を洋服にリメイクしてくれるというのです。その方は、自分の楽しみとボケ防止のために縫物をしているそうで、お願いすると喜んで引き受けてくれました。
私の思い出の浴衣はもちろん、母が子どもの頃自分のお母さんに作ってもらい40年以上大事にしてきた浴衣、妹が着なくなった浴衣など数点をリメイクすることに。
それら全てが丁寧にほどかれて、ワンピースとなって復活したのです!まさに着物(浴衣)リメイク!!
私の一着の浴衣が、ほどかれて生地に戻され、そこから洋服が2着分できました。そのことでわかったことですが、着物と簡単(シンプル)な洋服に使用されている生地の量の違いにも驚きでした。
浴衣のままだったら、着ても年に数回だけ、あとは着られなくなった柄やサイズでほとんど眠っていた着物や浴衣。それが今では、暑い時期にはほぼ毎日涼しく快適に着られるルームウェアになっています。また、家族が大好きでよく行く温泉♨にも必ず持参の、私・母・妹の親子三世代、みんなでおそろい温泉ウェアとしてもフル活躍アイテムとなったのでした☆
※家族との温泉旅行にて私と妹のリメイクワンピースです
嬉し・楽し・思い出いっぱいのリメイクワンピースを、最初に作ってくれたお婆ちゃんとリメイクしてくれたお婆ちゃん達に感謝を忘れず、いよいよ生地が傷んで破れるまで(笑)
今後も大切に着ていきたいと思います(*´з`)
まとめ
お直しの技術で古い着物のサイズ変えはもちろん、シミや汚れも仕立て直しで見えなく隠せちゃったり、染め直しにより色柄を変えて世代を繋いでいくことはとてもおもしろくて素敵なことだと思いました。
生地に戻ることでも、ワンピースやチュニック、ドレスまで、その着物の種類と柄により用途とデザインは様々に、他にもバックや傘、財布、小さなアクセサリー等にまでリメイク出来ちゃうんですね!
着物のままでなくとも思い出やお気に入りを無駄にせず、大事にしていけるのはとても素敵で良いなぁと思いました。
新人がびっくりしたことシリーズは下記リンクバナーから一覧をご覧になれます。
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
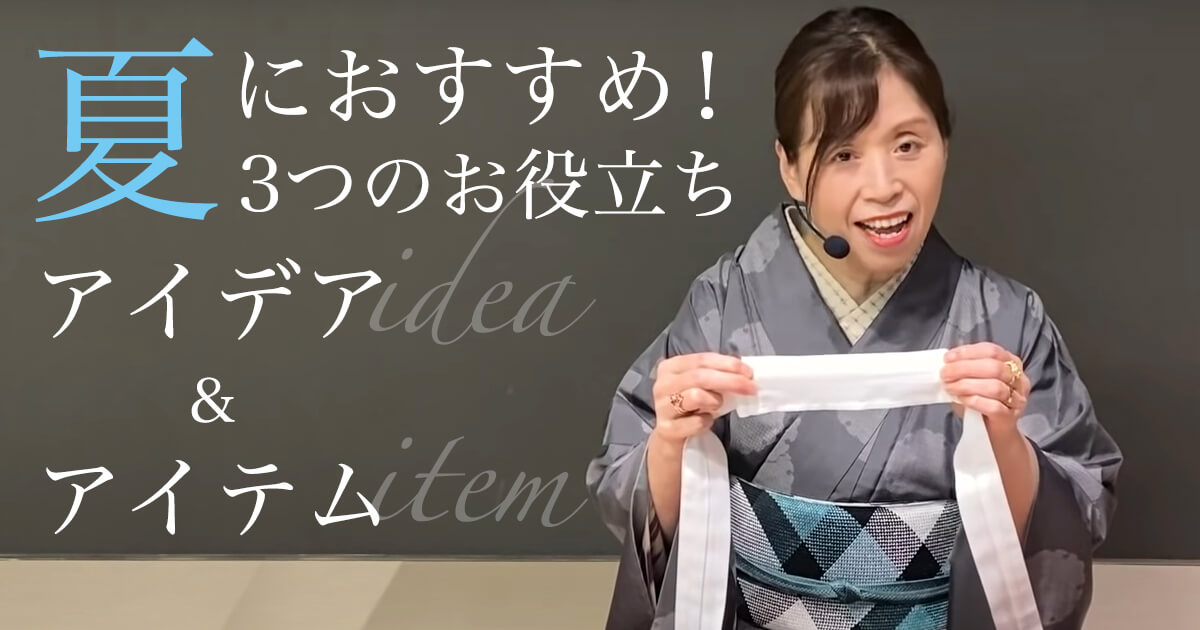
夏におすすめ!3つのお役立ちアイデア&アイテム
夏は暑い、と覚悟を決めるのも大事
蒸し暑い日が増えてきましたね。これから夏に向かってどんどん暑くなっていきますが、夏着物を着こなすために有効な小技をご紹介いたします。
夏着物は、暑いし汗もかくし、透けるし、着るのには結構ハードルが高いと思いませんか? 10年ほど前までは「着物=正絹」という感じでしたから、汗をつけたくないとかいろいろ思うと着るのがおっくうでした。最近は、綿麻や新素材など洗えるものも増えていますので、気軽にトライできるようにはなっていると思いますが、やはり少しでも涼しく楽に夏を乗り切りたいと誰もが思っていると思います。
でもまずですね、暑いし汗をかくからイヤだとか思っている時点で夏着物がイヤになってしませんか?
実はこの思考パターンを変えるだけで、汗が相当減るような気がします。
「夏は暑いんだ」と覚悟を決める。汗をかいてもいいように、準備をして着る。それで随分と変わります。夏はもう、何を着ていても暑いわけですから「これを着れば涼しい」なんていうものはほぼ存在しないわけです。気の持ちようでコントロールするのも、実はひとつの夏を乗り切るアイデアと言えるのではないでしょうか?
凹凸のある素材は涼しい
平織りの素材は、汗をかくと肌に張り付くこともあり、暑いと感じる方も多いのではないでしょうか。実は、満点スリップの上半身の素材が速乾性のあるポリエステルなのも、女将が木綿の平織り素材を暑いと感じたから。体感の差はあるとは思いますが、しじら織やワッフルなどぽこぽこした素材で肌に触れる面積が狭いため、涼しく感じます。
そこで、単衣や夏着物につける居敷当ての素材もダイレクトワッフルにしてみたところ、さわやかでいいかんじになりました。
そこで「薄地で涼やか、汗による張り付きも軽減。綿ワッフル織りの居敷当て(いしきあて)」として販売を始めたところ、少しずつ売れ始めています。この居敷当ては、収縮率が縦横1%未満でほぼ変化がないところも特徴です。毛羽立ちにくい構造で、二次収縮も起こしにくいです。天然繊維はどうしても伸縮が大きいものが多いので、単衣や浴衣なども自分で洗おうと思っても、居敷当てとの伸縮率の差でつれてしまったり、難しいケースもあります。その点とても安心して使っていただけますし、絹に比べて安価なのも嬉しいところです。お着物好きな方には一度お試しいただきたいアイテムです。
夏におすすめ!技ありえもん抜き
夏は、ちょっとえもんが首につかず、ゆったりと抜けることで涼しさが感じられます。これもお好みですが、冬よりも気持ちえもんを抜くことで快適になります。
でも、うまくえもんが抜けないのよね。えもん抜きをつけると、背中で透けて見えてしまうし‥‥という方のために、新商品の「技ありえもん抜き」をご紹介します。
たかはし式えもん抜きとは違い、襦袢の背中に直接縫いつけるタイプになります。
縫いつける場所は、えもんを抜いた状態で、ウエストの一番細いところから3〜4センチ上になります。まず仮止めして、自分にちょうどいい場所を探してください。
そして、使い方は襦袢を羽織ったらひもを身八つ口から通して、下に引き下げます。えもんが程よく抜けたら、衣紋抜きを下に引き下げながら前で結びます。このとき「下にさがるんだよ〜」と心の底から呪文をかけるとよいそうです!
紐を結んでしまえば、えもんは固定されますので、前で襦袢の衿を胸を包むように会わせればオッケーです。
この詳しいやり方は商品ページもしくは動画でもチェックしてくださいね。
【夏きものでも透けないえもん抜き!たかはし新商品「技ありえもん抜き」紹介&縫い付け方&使い方!】
以上夏を少しでも涼しく過ごすための心構えとアイテムのご紹介でした。
女将による3つの小技のご説明はこちらです!
たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
【夏におすすめ!3つの小ワザ紹介】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
いかがでしたでしょうか?
知恵と工夫で、蒸し暑い梅雨も、夏本番も、着物を楽しみましょう。
日常着物をもっと楽に、たのしく、かんたんに。ズボラ女将の日常着物術、これからもお楽しみに!
紹介した商品
綿ワッフルの…
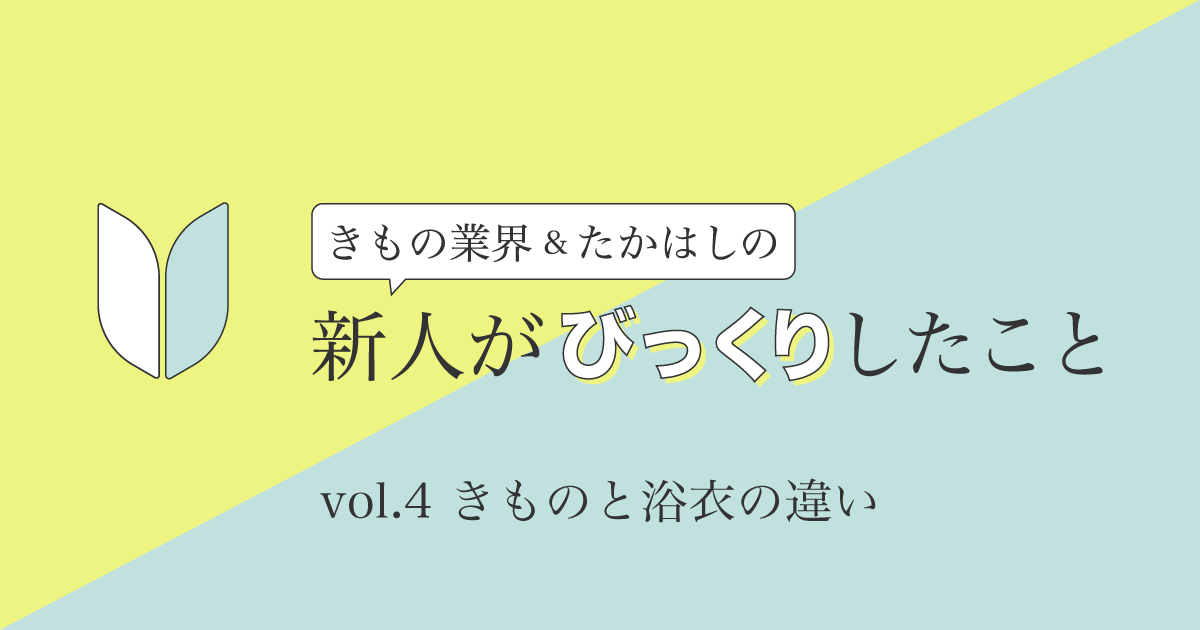
【きもの初心者必見】きものと浴衣の違いって何?
着物初心者、たかはし新入社員の藤田です。
本日は、
“きものと浴衣の違いについて“
学んだことを皆様に共有させていただければと思います!
主に「夏きもの」と「浴衣」の違いがわかりませんでした。
「夏きもの」・・・単衣や薄物が当てはまります。
(詳しくはvol.1きものと季節の関係で紹介しております。)
【着物初心者必見】着物は季節によって着分けるルールがあった?!
浴衣はお祭りに着るもの、と言う程度の認識でした。
これも違いの一つではありますが、ポイントは3つありました。
違いその①着方の違い
きものの場合
着物は肌襦袢と長襦袢を着る(たかはしで言うと襦袢セットになりますね。)
帯も袋帯や名古屋帯などを使用するのが一般的で、結び方の種類としては、お太鼓結び、銀座結びなど。
(帯の種類や結び方については、次回ご紹介したいと思います)
足元は足袋に草履
浴衣の場合
浴衣は下着だけが一般的
帯は半幅帯または兵児帯が一般的。結び方も着物とは違って、よく見かけるのは一文字結び、文庫結びなど。
よくショッピングセンターなどでは作り帯などが販売されていて、浴衣は着付けのレベルが下がり着付けに詳しくなくても気軽に楽しめるように感じます。
身丈や裄を少し短く着付けるのも違いの一つ
足元は、裸足に下駄
ただ、最近では浴衣でも帯や結び方によって帯〆を使用したり、兵児帯を、仮ひもを使って華やかに結んだり、楽しみ方は自由になってきているそうです。
さらにレベルが上がると浴衣に、八寸帯でお太鼓結びにし楽しむ方もいらっしゃるようです。大人な着こなしでとても憧れます。
オススメの三重紐はこちら
違いその②生地の違い
私調べでは、一般的には下記のような区分となっているそうです。
夏きもの・・・絹(絽、紗)、麻、ポリエステルなど
浴衣・・・木綿、綿麻、ポリエステルなど
違いその③仕立て方の違い
きものの場合
広衿:3寸(約11.5cm)
着る時に衿を折って、衿幅を調整できるのが特徴。衿山がふっくらと仕上がります。
スナップボタンや引き糸が付いています。
浴衣の場合
バチ衿:1.5寸(約5.5cm)
既に半分に折って仕立てられている。浴衣の他に長襦袢もバチ衿が一般的だそうです。
由来としては、昔、浴衣は寝巻きとしての使用が主流だったため、着る際にわざわざ衿を折ったりする手間を省くためと言われています。
夏きものと浴衣の境界線は曖昧になってきている?
最近では、浴衣を夏きものとして楽しむ方もいらっしゃいます。
着方でも触れましたが浴衣でも帯〆を使う方もいらっしゃるので、明確な境界線というのは昔ほどないのかなと感じました。
また、浴衣をきものに見せる最大のポイントは、「半衿を見せる」ことだと思います。
襦袢を着なくても、肌着などにでも合わせられる、うそつき衿がおすすめです。
私自身、きものと浴衣をそれぞれ購入するのはお財布的に厳しいので、浴衣でもきものとして楽しめるのは嬉しいです!
また素材、生地についても、曖昧になっていることが分かりました。
例えば、
木綿生地で、バチ衿のものがあったとします。
昔であればこれは「浴衣」と言えるでしょう。
ですが今は、浴衣・夏きもの両方で楽しめます!
バチ衿の着物は衿幅を調整する必要がないので、日常着や初心者向けとしておすすめですね。
ただし、柄でこれは明らかに浴衣って言うのもあるので両方で楽しむためには柄の選び方が大事です。
浴衣の柄は、着物に比べ、夜でも映えるように柄や色が派手だったり、金魚や花火、朝顔など夏らしい柄が多いです。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
きものと浴衣の違いについてまとめてみました。
夏きもの
生地
麻、絹(絽、紗)、ポリエステルなど
衿
広衿
帯
袋帯、名古屋帯など
着方
肌襦袢と長襦袢を着用した上から着物を着る。足元は足袋に草履
浴衣
生地
木綿、綿麻、ポリエステルなど
衿
バチ衿
帯
半幅帯、兵児帯
着方
下着の上から着る。足元は裸足に下駄
【…
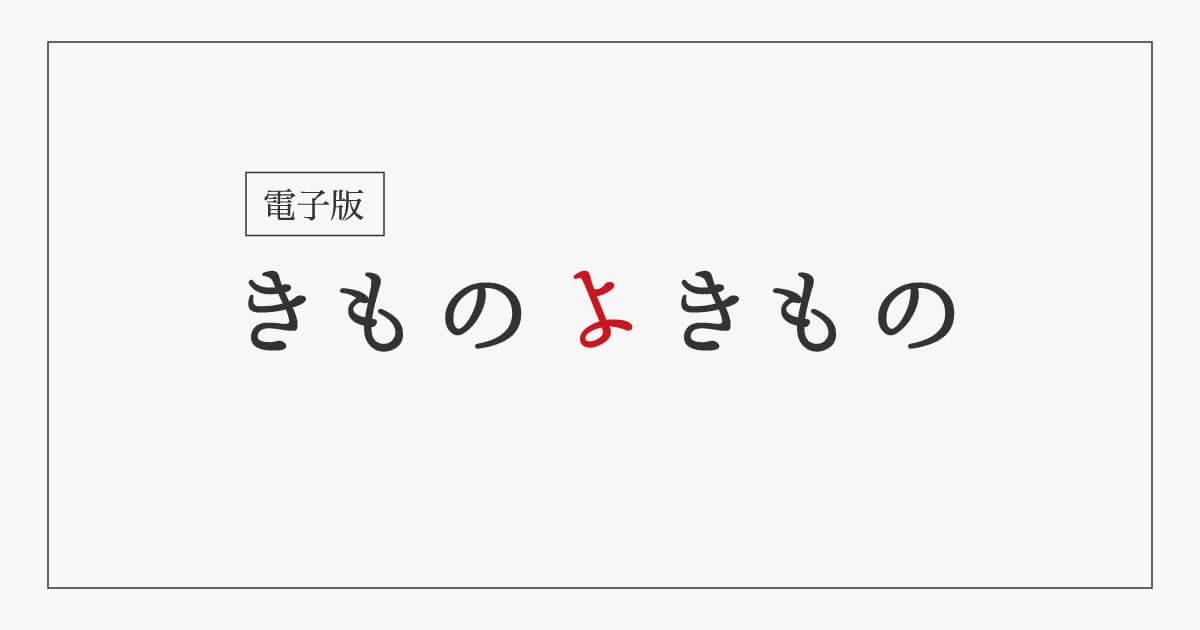 https://k-takahasi.com/ja/wp-content/uploads/2020/02/b_kyk.jpg
600
800
たかはしきもの工房
https://k-takahasi.com/ja/wp-content/uploads/2018/04/logo-top.png
たかはしきもの工房2020-08-20 10:00:132020-09-10 12:54:58令和2年8月
https://k-takahasi.com/ja/wp-content/uploads/2020/02/b_kyk.jpg
600
800
たかはしきもの工房
https://k-takahasi.com/ja/wp-content/uploads/2018/04/logo-top.png
たかはしきもの工房2020-08-20 10:00:132020-09-10 12:54:58令和2年8月