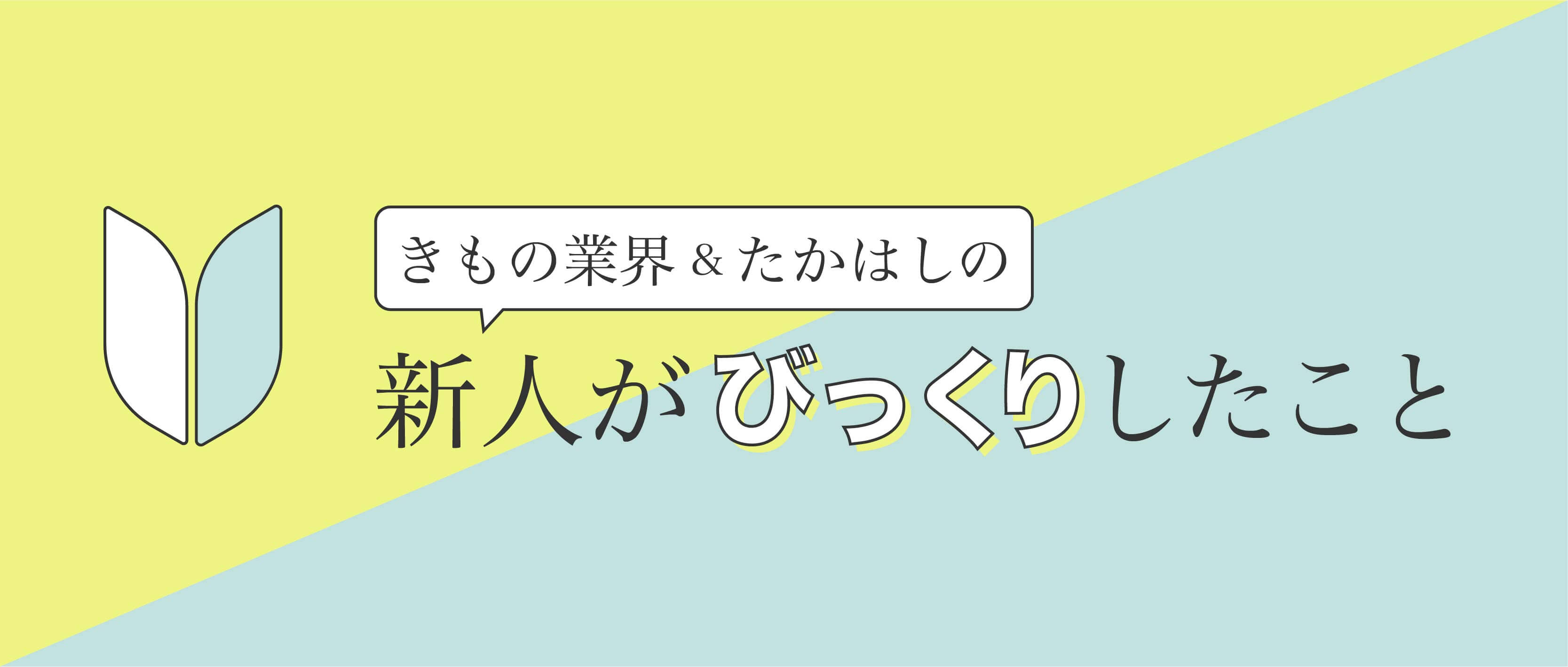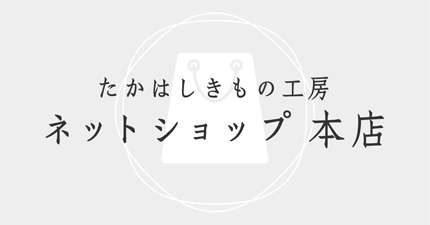たかはしBLOG

自分に合う呉服屋さんを気軽に探せる方法
ここ数年できものを楽しむようになられた方は、最初はお母さまのきものや、おばあさまのきもの、リサイクルきものなど、身近にあるきものや既に仕立てられているきものから始めた方がほとんどなのではないでしょうか。恐らく、呉服屋さんできものをまず一枚買ってから始めたという方は、少ないと思います。
呉服屋さんで開催されている着付け教室などをきっかけに、そのお店の馴染みになると、買い物がしやすくなったり、ちょっとした疑問も聞きやすいということがあるでしょう。
しかし、呉服屋さんとまったく接点の無い場合、呉服屋さんに気軽に入ることができないという声をよく聞くことがあります。
気軽に呉服屋さんに入ることができない原因としては、
呉服屋さんでこんな風に言われて悲しかった
希望を伝えたのに希望の通りに仕立ててもらえなかった
すごく高額な商品を買わされたらという不安がある
買うつもりが無いのに行ってはいけないのではないか
など、ネット上などでネガティブな情報を目にすることが考えられます。
日常できものをもっと楽しむために、今回は、呉服屋さんとの上手な付き合い方をお伝えします。
日常できものを楽しむための呉服屋さんとの付き合い方
理想は、お住まいの近くで直接相談に乗ってくれる呉服屋さんがあると、すごく良いです。御用達のお店になるような地元の呉服屋さんと一軒は繋がっておくことをおすすめします。
ただ、その一軒のお店だけに絞って行くということではなく、核となるお店を見つけ、目的に応じて複数のお店を使い分けると良いです。
たとえば、地元の呉服屋さんを核とするお店として、大手チェーン店の呉服屋さん、リサイクルきもの屋さんなど、目的に合わせて通うというような形です。
核となるお店に、自分の寸法や持っているきものや好みなど、いろんなことをわかってもらっていることが、きものライフを楽しむにあたって大きなメリットになります。
たとえば・・・
素敵な帯を見つけた時、手持ちのきものに合うかどうかがわかる
着合わせを考えた時、何か弊害がある場合、それは止めた方が良いなどのアドバイスがもらえる
小物を選ぶ時、手持ちの小物と似ている場合に、新たに加える色味としておすすめの小物を提案してもらえる
このように、何か商品を選ぶ際にも、着ることを前提とした提案がもらえて、着方や着合わせについても相談に乗ってもらえると、きものの楽しみ方の幅が広がりますよね。
また、核とするお店に、地元の呉服屋さんをおすすめしたい理由がふたつあります。
ひとつめは、チェーン店の呉服屋さんの場合、転勤によって人が移動してしまう可能性があるからです。地元の呉服屋さんの場合は、その可能性が低いです。
ふたつめは、チェーン店の呉服屋さんの場合、そのお店の方の想いだけで経営しているわけではないため、担当する人が替わることで齟齬が発生する可能性もあります。地元の呉服屋さんの場合、経営者が直接接客する場合もあり、相対的にその可能性が低くなります。
そのため、長い目で見て考えると、地元の呉服屋さんを核になるお店にしておくと良いです。
いずれにしても、付き合っていくお店の中で、確実にこの人だったら信頼できると思える人が見つかる事が一番です。
長く付き合える呉服屋さんを見つけるには
長く付き合える呉服屋さんを見つけるには、日常できものを着ることを前提にしているかどうかを、取り扱いしている商品の種類やスタッフの対応を見ていくと良いです。
まず、商品の取り扱いについて。きものや帯だけではなく、肌着や帯揚げ、帯締めなど、きものを着る時に必要な小物が充実しているかどうかが重要なポイントです。
昔は、きものを買うだけで着ないお客さまは沢山いらっしゃいましたが、今はきものを買う方や呉服屋さんに入ってみたい方にとっては、きものを着ることにプラスになるお店を探していると思います。
きものを着るためにいい商品の提案があるというのも選ぶ視点のひとつではありますが、きものを着ることに即して経営しているお店が、きものを着ることにプラスになるお店です。
たとえば、きものと帯は沢山取り扱いがあるのに、帯揚げや帯締めがほとんど置いていないお店の場合、きもののコーディネートには興味が無い可能性が高いです。
逆に、小物の提案があるお店や寸法の相談に乗ってくれるようなお店は、着ることにとても興味があるお店の可能性が高いわけです。
次に、接客してくれるスタッフについて。着方や着合わせの相談はもちろん、お客さまからの質問に対して、親身になって対応してくれるかなどが、ポイントになってくると思います。
たとえば、帯締めや帯揚げなどの小物を買おうとしている時、その商品についての話だけではなく、疑問に思っていることや、次に着ていく場所にどんなものを着たら良いのかなど、着る時を想定して会話がされているかどうかで、自分との相性も確かめられると思います。
お客さまの話をあまり聞かずに、一方的に決めつけるのではなく、一緒に相談しながら選んだり決めたりできるかどうかが、きものを着始めた方には必要なお店だと考えています。
こうじゃなきゃダメですというような形ではなく、多方面からの視点で提案がもらえるお店なら長くお付き合いできると思いますし、お客さまが疲れたり、がっかりすることも少ないでしょう。
実際に、自分に合う呉服屋さんを見つけるには、そのお店に来店して、確かめるほか無いわけですが、呉服屋さんに行くのに一番ハードルが低いのは、お友達の御用達のお店に一緒に連れて行ってもらうケースです。お店と自分の間に、仲介してくれる人がいるから非常に安心ですよね。
ただ、注意したいのは、お友達にとってベストなお店であっても、自分にとってベストなお店かどうかはわかりません。そのため、最初は一歩引いた気持ちで、自分の感覚でお店を見ていくと良いと思います。
一人でもできる気軽に呉服屋さんに入る方法
お友達の御用達のお店に行く時も、ひとりで呉服屋さんに行く時も、試してもらいたいことがあります。これは、呉服屋さんに入る口実にもなるので、気軽に呉服屋さんに入りやすくなる方法です。
それは、「きものについて、ちょっと教えてくれませんか?」と呉服屋さんに入ってみることです。
たとえば、着合わせの話や、寸法について、リサイクルきものを着ていて困っている点など、買う目的ではないけれど聞いてもいいですかという体で、尋ねてみることです。
これは呉服屋さんにとっても、話のきっかけになり、お客さまとの接点にもなります。
きものを楽しむために、良いお付き合いが長くできるお店を探すのであれば、ぜひいろんなお店に沢山入ってみることをおすすめします。
いろんな呉服屋さんに行って、自分に合う呉服屋さんかどうかを探していく中で、このお店なら信頼できる呉服屋さんが見つかったなら、一度きものを仕立ててみると、きものの楽しみ方が広がります。
きものを仕立てるために、寸法をメジャーで測っただけで決めて仕立てた場合、寸法が狂う可能性もあります。そのため、サンプルのきものを試着することで、より体に合った寸法に調整してくれるお店もあります。
ただ、そのようにして仕立てた場合であっても、一回の仕立てで一番着やすいベストなきものには、なかなかたどり着かないです。
なぜなら、選んだ反物の生地の落ち感にもよりますし、サンプルを試着したとしても、着る時の腰ひもの位置がズレると身丈も変わります。裄についても、礼装用と日常用では寸法が違います。仕立て方の袷と単衣でも違ってきます。これを言い出すとキリが無いので、ここで留めておきます。
まったく同じ寸法できものを仕立てたとしても、すごく自分に合ってて良い感じという時と、ちょっとその感じとは違うという時もあるのはそのためです。
きものを纏った感覚を体感し、いろんなことを考え出すとキリが無いですが、だからこそ自分なりのこだわりが生まれることも、きものの楽しみのひとつではないでしょうか。
人間だものトラブルもあるけれど、幸せもある
いろんな呉服店さんと付き合っていく中で、ちょっとしたトラブルもまったく起こらないということは、ほとんど無いと思います。誰もが人間なので、失礼なこともあるかもしれませんし、間違いも起こることもあるでしょう。
そのため、自分に合う呉服店さんを探していく別の視点として、何かトラブルがあった時の解決方法で、判断できることが多いと思います。
以前、きものをどこかの呉服屋さんで買った時の経験をSNS投稿されていた内容を事例にお伝えします。
そのお客さまは、希望の寸法を持っていき、その通りに仕立てて欲しいと頼んだそうです。しかし、仕上がってきたきものはその寸法の通りにはなっていなかったので、直してほしいと依頼したところ、そのお店では「あなたの身長からこちらが判断して仕立てた」と言われたそうです。
この場合、お店側でお客さまが希望された寸法に問題があると思ったのであれば、仕立てる前にお客さまに伝えた方が、このトラブルを回避することができたでしょう。
会話をすることで、たとえば、この身丈だと短いと思いますと伝えたら、私は余分は一切要らないのでぴったりにしたいのでこの寸法で仕立てて欲しいという会話になったのかもしれません。お客さまが希望した寸法の理由がわかれば、希望した寸法で仕立てることができたのでしょう。
以前のように、きものをあまり着なかった時代には、きものを人に着せてもらうことが多かったので、身丈を長めに仕立てるのが一般的でした。そのため、仕立てる寸法を任せますということになると、身丈が長めに仕立てられる可能性が高いです。
このようにトラブルがあった時、すぐに謝ってくれるお店だと、気持ちよく付き合っていけますよね。
ただ、これは逆にお客さまの場合も同じです。お店に任せると言ったのであれば、任せた責任がお客さまにはあります。その結果、もし自分の思い通りにならなかった時、一方的にお店が悪いと決めつけて文句を言ってしまうと、お店との良い関係性を築いていくのは難しくなります。
お店もお客さまも、腹がくくれているかどうかということが、良い関係を築けるかどうかというところの分かれ道になります。
お店と良い関係性を築いていくなら、何か気づいたことがあれば素直にそれを伝える環境を築いていくことに意識を向けてもらえると、お互いにとって良い関係ができていくと思います。
どうぞ恐れずに、教えてもらいたいことを持って、呉服屋さんにどんどん入ってください。もしお店の人に面倒くさがられたら二度と行かなければ良いだけですし、もし間違えて謝ってもくれないお店はもう行かなければ良いだけですから。
これまで呉服屋さんに行ったことがある方にとっては、今までがっかりした経験もあるでしょうけれど、逆にすっごく幸せな経験をされたこともあると思います。
きものライフは、自分一人での楽しみもありますが、一人だけの楽しみじゃないと考えています。
きものを通して人の輪を広げていくことで生まれる楽しみは、人との関わりで楽しみが増幅されるような感じを経験されたことはないでしょうか。その人の輪の中には、お友達はもちろん、お店もあって欲しいと願っています。
今は、呉服屋さんとの関わりは無く、ネットで全部揃える方も多いかもしれませんが、直接的な人間と人間との関わりの中で、より深まっていく思いが生まれるはずです。
そういった経験も共有しながら、どんどんみんなでお互いに良い形を目指しながら手を携えて、きものがもっと楽しいものになったらいいなと思っています。
ぜひ核となるお店を見つけて、きものライフがより楽しくなるようなお店との関係性を築いていっていただければと思います。
ぜひ呉服屋さんに行ってもらいたいと本気で思っている女将の動画はこちらをご覧ください。
【自分に合う呉服屋さんを探すコツ&気軽に入る技を伝授!こわくない!ドンドン入ろう呉服屋さん♪】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

「丸洗い」と「洗い張り」の違いとは?
きもののメンテナンス、「染み抜き」や「丸洗い」、「洗い張り」など、どのようにされていますか?
たとえば、、、
一度着たら汗や汚れが気になるから「丸洗い」している
明らかなシミが付いたところだけ「染み抜き」し、あとは「丸洗い」している
「丸洗い」は安価でお手軽だから「丸洗い」だけしている
「洗い張り」は仕立て代がかかるから高いから「丸洗い」で済ませる
など、「丸洗い」する機会の方が多いかもしれません。
きもののメンテナンスの中で、「丸洗い」と「洗い張り」の効果が同じと思われている方も多いと思いますので、今回は、「丸洗い」と「洗い張り」の違いをお届けしていきます。
「丸洗い」とは?
まず、「丸洗い」についてお伝えしたいと思います。
「丸洗い」はドライクリーニング溶剤できものを洗う方法です。溶剤は石油からできているため、油汚れに強いと言われています。きものを丸ごと洗っても生地が縮まないこともあり、気軽に利用される方もいらっしゃるでしょう。
基本的には、きものの「丸洗い」は洋服をドライクリーニングするのと変わりませんので、
きものを丸ごと洗える
衿汚れや裾口の汚れを個別に湯洗いをしてくれる丁寧なところもある
アイロンでプレスすることで糸目が整うのでシワも取れる
よほど汚れがひどくない限りは衿汚れや染み抜きでの別料金なし
など、お手軽で良いと思います。
ただ、一度着ただけで目立った汚れも無いのに「丸洗い」するのはお勧めしません。
その理由は、溶剤の成分が不明なため、生地の染めにまったく影響がないかはわからないからです。
昔に比べて現代では、様々な薬品が使われています。反物自体に使われていることもありますし、保存に使用する紙にもノリが、収納する箪笥にも接着剤や防カビ剤が使われています。そのため、いつ何がどう化学変化を起こすのかは判断できないので、できるだけ溶剤を使う頻度を少なくする方が、生地への影響リスクを小さくできますよね。
「洗う=劣化」です。
生地は、洗えば洗うほど毛羽立ちや擦れに繋がります。そのため、生地を長持ちさせるためにも、「丸洗い」をする時を自分で見極めることが大事です。
ちなみに、「丸洗い」に出すタイミングの見極めポイントは、次の通りです。
衿汚れを自分で落とせているかどうか
袖口が黒ずんできていないか
裾の裏側の八掛が黒ずんできていないか
お尻回りや膝裏のシワが気にならないか
膝前の生地がヨレていないか
さらなる疑問点として、次のシーズンまで着ないきものを収納する時、どのようにメンテナンスしているのか気になった方もいらっしゃるかもしれません。
たとえば女将の場合、衿汚れを毎回自分で落とし、問題が無いと判断したきものはそのまま収納しています。同じきものを毎シーズン着ていると、意外と黄ばみや汗汚れも簡単には変色したりはせず、着ること自体がメンテナンスにもなっています。
何年も箪笥にしまったままにしておくよりは、年に1回は着る、もしくは2年~3年に1回でも着てあげるようにすると、きものを長持ちさせることにも繋がります。
とはいえ、1シーズン着た後、次のシーズンまで収納しておくのが心配な場合には、「丸洗い」するのもひとつの選択でしょう。
日常できものを着る頻度や状態などに合わせて、選択していくのをおすすめします。
「洗い張り」できものを育てるとは?
生地が喜んでいるように感じる、紬は育てて着るもの、と言われる「洗い張り」には、どんな効果があるのでしょうか。
生地が綺麗に見える
天然繊維は細かい繊維をより合わせた糸を何本も重ねて1本の糸にしています。とくに真綿の場合は、繭玉を広げて糸を紡いでいくので、細い繊維がより合って作られています。
そのため、毛羽立ちがありますし、着ているうちに細かい繊維が出てくることがあるのです。
「洗い張り」をすると、生地から細かい繊維が抜け落ち、光の屈折が変わることで綺麗に見えるようになります。
着心地が良くなる
紬系の反物は先練といってセリシンを落とし、糊で繊維を固めた状態にして織っていきます。糊を使用せず柔らかい状態だと織ることができず、織りムラが出たり、糸が切れやすくなったりするためです。織った後、湯通しをすることで糊を落としますが、生地の奥に入った糊はそのまま残っています。
「洗い張り」をすることで奥に残った糊が落ちていき、生地がより柔らかくなり着心地がとても良くなるのです。
吸着した見えないホコリもすっきり落とす
絹は繊維が繊細なので、目に見えないような小さな粉塵やホコリも吸着してしまいます。そのような生地の中に入り込んだ汚れを、水の力で洗い落すことができるのが「洗い張り」です。
「丸洗い」の溶剤でも効果はありますが、ドライクリーニングでは取れにくいものもあるため、「洗い張り」することでよりすっきりと落とすことができます。
生地の収縮や歪みをリセットする
きものは時間が経つことで、少なからず生地の収縮や歪みが生まれます。
「洗い張り」は反物の状態に戻してから水を通して洗うため、生地の収縮や歪みをリセットすることができます。
創意工夫で長く着られる
反物の状態に戻して仕立て直しをするので、生地を転地することで取れなくなったシミを見えないところに隠したり、体型の変化に合わせて寸法を直すこともできます。
このように「洗い張り」をすることで、きものがより体に沿うようになって、「丸洗い」では得られない着心地の良さが生まれていくようです。
「洗い張り」は、きものを長持ちさせ着心地良くするだけではありません。きものを着る頻度が高いと、4~5年で裾がすり切れてしまうため、洗い張りの際に八掛を替えることも、楽しみのひとつです。
濃い色のものに替えたり、染め替えして違う色にしたりと、おしゃれの楽しみがプラスされますね。
たとえば、八掛が赤くて嫌だなって思う古いきものも、「洗い張り」して八掛を替えることで、また長く着られるきものになります。
良い機のきものは「洗い張り」3回目からが着どき。「洗い張り」で育てた生地の肌ざわりの良さは「丸洗い」とは比べようもありません。お金をかけた以上の効果をぜひ思いきって体感いただければと思います。
女将による「丸洗い」と「洗い張り」の違いはこちらの動画をご覧くださいませ。
【きもののお手入れ!「丸洗い」と「洗い張り」の違いとは?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
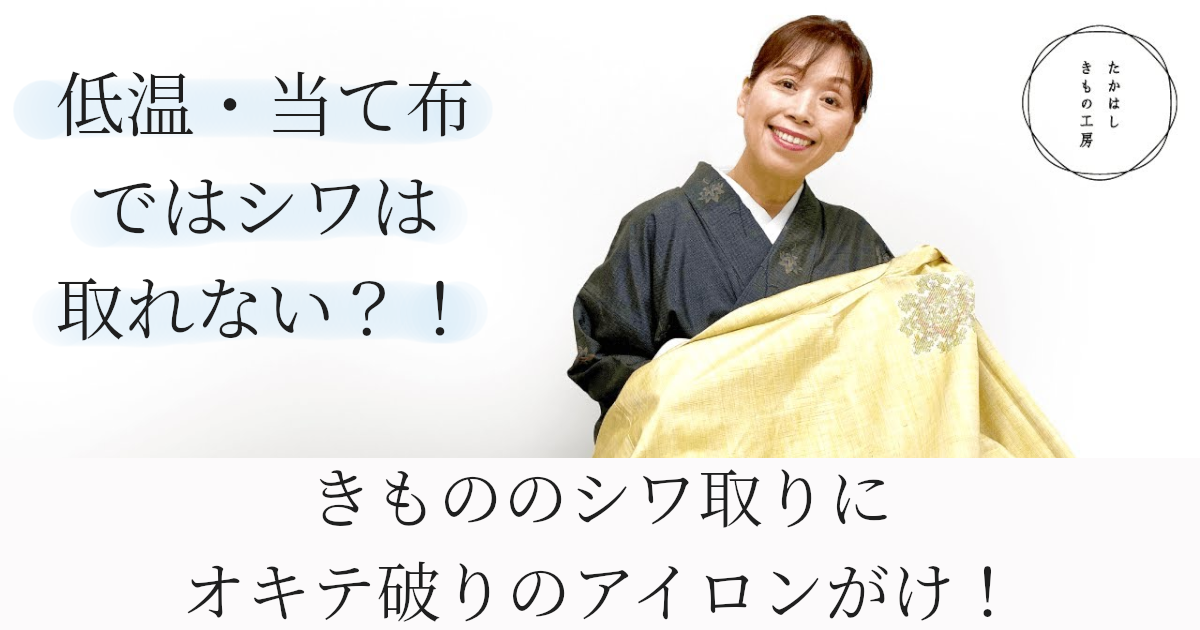
きもののシワ取りにオキテ破りのアイロンがけ!
日常できものを楽しむようになってくると避けては通れないのが、きもののシワを取るアイロンがけ!
箪笥から出したきものの袖に予想外の畳みシワ
長い時間座ってついた座りシワ
腰ひもで縛った箇所の深いシワ
長年の折り癖によるシワ……
今回は、アイロンがけが苦手な人でもアイロンがけしたくなるような方法をお伝えしていきます!
時間と手間をかけてもシワ取りできない
絹のきものにアイロンがけする場合、「低温で当て布をしてアイロンがけしてください」ということをよく聞きます。
低温、当て布をしてアイロンをかけたのに、ぜんぜんシワがとれない! という人、たくさんいらっしゃると思います。
アイロンがけに時間をかけ、温度に気をつけ、当て布をして……と、手間をかけたにも関わらず、シワがまったく取れない! これでは、アイロンがけが嫌いになっても仕方ありません。
絹のきものの生地にとって、絶対的に安心なのは低温で当て布をしてのアイロンがけですが、はっきり言ってシワは取れません。
「シワ」は繊維の折れやつぶれです。生地のシワを取る原理を考えた時、低温&当て布では繊維の折れやつぶれを膨らませることができないため、シワを取ることができないわけです。
では、どうすればよいか。
当て布無しでのアイロンがけも含め、きものの畳みシワや腰ひもで縛った箇所の深いシワを取る方法を、具体的にご紹介していきますね。
きものの畳みシワを取るアイロンがけの方法
実験1)中低温&当て布でのアイロンがけ
きものを広げて畳みシワのある裏面に手ぬぐいで当て布をします。アイロンは絹モード(中低温・約100℃)に設定し、蒸気は一切無しでアイロンがけをしてみます。
アイロン自体の重さがあるので、力を入れずにかけます。注意点としては、キセの部分にはアイロンをかけないようにします。
このかけ方だとシワはまったく取れません。
実験2)当て布無しでのアイロンがけ
当て布無しでアイロンがけすると、当て布でのアイロンがけよりは、少しシワが取れた状態になります。
さらに温度を上げて、羊毛モード(約130℃)にします。これでアイロンの中温くらいになります。中温でアイロンをかけると、だいぶ取れます。
※設定温度は、メーカー機種によります。取扱説明書をご確認ください。
同じきもので別の箇所を中温でアイロンがけしたものが、次の画像です。
蒸気無しでアイロンがけする場合は、中温で当て布無しでのアイロンがけが一番シワがキレイに取れます。
実験3)蒸気有り中温&当て布でのアイロンがけ
家庭用アイロンで蒸気有りでアイロンがけする場合、アイロンから水がボタボタと漏れることもあるので、当て布をする等、注意して行います。
蒸気有りの中温でアイロンがけしたものは、次の画像です。
最初のシワが取れていなかった部分に、蒸気有りでアイロンをかけると、シワが取れています。
ここまでをまとめると、
シワが無い箇所は蒸気無し中温でのアイロンがけ
シワがひどい箇所は蒸気有り中温でのアイロンがけ
キセや裾はアイロンの重さで潰れないよう重さを乗せずにかける
この方法は、女将自身が実験してきたのはもちろん、プロからリサーチして得たものです。中温で当て布無しのアイロンがけすることで、きものの畳みシワがキレイに取れます。
深いシワを取るアイロンがけの方法
中温で当て布無しでは取れない深いシワでも、家庭用アイロンを使って、シワがキレイに取れる方法をお伝えします。
この方法は、袖丈を長く仕立て直しした時に袖底や肩に出てしまう深いシワを取るために編み出した方法なので、かなり有効です。
今回は、きものの背中側に紐で付いた深いシワにアイロンがけしています。
<用意するもの>
乾いたタオル1枚(心配な時は厚手のタオル、慣れてきたら薄手のタオル)
濡らして絞った小さなタオル1枚
<アイロンがけの方法>
①乾いたタオルを半分に折り、シワがひどい部分の上に置きます。さらにその上へ濡らして絞った小さなタオルを重ねます。濡れたタオルは直接きものに付かないように注意します。
②濡れたタオルの上から、蒸気無しの高温でアイロンがけします。その際、まったく重さをかけずにアイロンをかけるのがポイントです。
③アイロンを少し持ち上げて、円を描くようにタオルの表面をなぞるようにしてかけていきます。ある程度かけたら、乾いたタオルときものの間に手を入れて、少し熱いぐらいになっているとベスト。
※アイロンがけしていない右側の部分に比べるとシワが取れています
④深いシワで取れにくい部分には、濡れたタオルを外し、もう一度、乾いたタオルの上から高温のアイロンをかけます。この時も、重さをかけません。
⑤タオルを取ってみて、まだシワが取れていない場合には、折っていたタオルを広げて置き、またその上から高温のアイロンで重さをかけずにアイロンがけします。
⑥きものに蒸気が残っている状態の時、そのまま干して乾かすのも良いですが、タオルを置いて再びアイロンがけして乾かすと、縫いなおしの筋までキレイになります。
※ただし、生地の傷になっているようなものは取れません
本当にひどい深いシワの場合には、ここまでの行程を3回ほど繰り返すことで、キレイになります。ポイントはアイロンの熱と蒸気で糸を膨らませることです。
表面をやり終えたら、裏面を同じようにアイロンがけすることで、さらにキレイになります。
このアイロンがけの方法だと、高温のアイロンによって温められたタオルから出た蒸気が、乾いたタオルを通してきものに届きます。重さをかけていないので、蒸気だけがきものに届くので、水染みを作る心配がありません。
重さをかけない理由は、アイロンの熱や蒸気で繊維の折れやつぶれであるシワを膨らませることでシワを取るためです。重さをかけてしまうと、せっかく蒸気で膨れた繊維がアイロンの重さでつぶれてしまいます。
当て布にタオルを使用しているのは、タオルは手ぬぐいよりも生地の構造が複雑なので、熱が直接きものに行きにくいので安心だからです。
このように、シワ取りにはアイロンが効果絶大であることを知っていただけたと思います。
きもの以外でもシワ取りに有効なアイロンがけ
ここまで、きもののシワ取りでのアイロンがけをお伝えしてきましたが、きもの以外でもアイロンがけが好きになってしまうようなシワ取りに効果的な方法があります。
普段、洗濯して乾かした後、シワ取りのためにアイロンがけしているものに効果的です。
たとえば、ハンカチで試していただくとよくわかります。
ハンカチを洗濯し、普通の脱水コースを5分~8分かけると、しわくちゃになりますよね。
このハンカチをそのまま干して乾かすと、乾いた後のシワをアイロンで取るのはひと苦労です。
シワをキレイに取るポイントは、干して乾かす前にアイロンがけをしてシワを取ることです。シワを取ってから乾かすと、本当にキレイにシワが取れます。
「うそつき袖」や「半衿」も全部洗濯機で洗って脱水をかけた後に、すぐアイロンがけをするので、シワがキレイになる、と女将。効果が目に見えるので楽しくなって、どんどんアイロンがけが好きになったと言います。
アイロンがけが心配な場合には、まずは絹の端切れや、古くて着なくなったきものから試してその効果を確認されてみてはいかがでしょうか。
女将がシワが取れるアイロンがけの方法をわかりやすく動画で説明しています。ぜひ、ご覧ください。
【常識を斬る!シワが本当にとれる方法!低温・当て布ではシワは取れない?!】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

浴衣をきもの風に楽しむためのちょい広バチ衿
夏に浴衣を着るのに、浴衣としてはもちろん、きもの風にも着たいと思ったことありませんか?
以前、綿麻や麻のきものや浴衣を、浴衣としてもきもの風にも、どちらも対応できるようにするために、ちょい広バチ衿が良いですとお伝えしました。
以前、ご紹介した「ちょい広バチ衿」はこちら
https://k-takahasi.com/blog/2022/10/10887/
「ちょい広バチ衿」の動画はこちら
この動画でお伝えした「ちょい広バチ衿」の仕立て方について、誤解を生んでしまったようなので今回、改めて「ちょい広バチ衿」についてお届けしていきます。
「ちょい広バチ衿」≠「広衿をバチ衿にしたもの」
以前、紹介した動画を見た方が、「ちょい広バチ衿」にしてくださいと呉服屋さんにお願いしたら、呉服屋さんが困ってしまったということがあったそうです。実際、呉服屋さんから直接お問い合わせをいただいたこともありました。
たかはしきもの工房のYouTubeの動画のコメント欄にも、
「ちょい広バチ衿にしてくださいと伝えたら、仕立て屋さんから裏衿が必要です。」
と言われたという書き込みをいただきました。
そして、「ちょい広バチ衿」には裏衿を使うのかという問い合わせもいただいたのです。
さらに、「あづまやきものひろば」の柴川さんが、「ちょい広バチ衿」について動画の中で話されていたというのですが、女将が伝えたかった衿とは異なっているようでした。
柴川さんの話に出ていたのは、よくアンティークのきものや、おばあちゃんの箪笥から出てきたきもので見かける衿のことかもしれません。
広衿のきものは、衿の内側にある「引き糸」や「スナップボタン」を使って衿を折りますが、その衿の部分を元々縫い留めてしまう仕立て方があります。
恐らく、日常できものを着る場合に、衿を折って着るのは面倒くさいから、衿を折る必要がなくなれば便利だからという理由でできたのではないでしょうか。
広衿のきものの衿を折って縫う仕立て方を「ちょい広バチ衿」と想定したことで、仕立て屋さんや和裁師さんにも誤解が生じてしまったのではないかと予想されます。
夏に浴衣や夏きものを楽しむためのご提案としての「ちょい広バチ衿」は、より涼しさを重視したいので、夏物に裏衿を付けるということはいたしません。なぜなら、生地の厚みで衿が膨れて、余計に暑さを感じてしまうためです。
たかはしで提案する「ちょい広バチ衿」とは、バチ衿の幅を少し広げることだけを指しています。
「ちょい広バチ衿」=バチ衿の幅を少し広げること
衿幅の違いがどんなことに影響するのかをお伝えしていきます。
二種類の浴衣に衿を入れてきもの風にしていますが、比べると衿幅が違うことが分かると思います。
向かって左側は、既製品の浴衣です。
衿幅が背中心で約5.5cm、胸元の部分で約6.5cmと、背中と胸元でおよそ1㎝の差があります。
「バチ衿」とは、三味線のバチのように持ち手から先端に向かって幅が広がっているように、背中から衿先の方に向かって、衿幅が少しずつ広がっている衿のことです。一方、背中から衿先に向かって一定の衿幅の衿を「棒衿」と呼んでいます。
一般的な既製品の浴衣は、「バチ衿」になっていて少し胸元で衿幅が広くなっています。
向かって右側は、綿麻の反物を浴衣に仕立てたものです。
きもの風にも着られるようにと背中心では約5.5cmですが、胸元で衿幅が広くなるようにした衿になっていますが、これも「バチ衿」です。裏衿を付けずに衿を半分に折って作っている「バチ衿」になります。
女将は身長が高め(164㎝)ですし、きものについて様々な実験をするために、背中心の衿幅を5.5cmではなく、6㎝にして仕立ててみたところ、暑苦しく感じたそうです。
そのため、たかはしでは背中心の衿幅は5.5cmを推奨します。身長が170cm以上の方であれば、少し衿幅を増やしても良いかもしれません。たとえば、IKKOさんは、一般的な衿幅に比べると相当衿幅を広くしています。
きものの寸法が考えられた昔と今とでは、平均身長が変わっています。学校保健統計調査によると、約100年前と比べ、女性の平均身長は約10cm弱高くなっているそうです。
きものの寸法は着る人の身長や体型に合わせたものであるので、縦に伸びた分、横幅がまったく変わらないわけはないと考えています。たとえば、比率で考えた時、縦に120%伸びたら、横に120%の幅になるわけです。
そのため、身長や体型に合わせて衿幅を調整した方が、きものの着姿がキレイに見えます。
「ちょい広バチ衿」にするための衿幅は?
「ちょい広バチ衿」に仕立てるために、衿幅をどの部分から広げると良いのかというと、
女将の結論としては、次の通り。
背中(背中心)の衿幅は5.5cm
耳の下、肩のあたりから少しずつ衿幅を広げていく
衿を入れずに着ると、向かって左側の方が涼しげに感じませんか?
ただ、身長が高めの方の場合、左側の衿幅だと、衿元が貧相な感じに見えてしまう場合もあります。
せっかく浴衣を仕立てるのであれば、浴衣地も質の良いものが多く出回っていますし、価格も高くなっているので、きもの風にも楽しめると着られる機会も増えて良いですよね。きもの風にも着るためには、衿幅を広くすると胸元がゆったりとしバランスよく見えます。
どのくらい衿幅を広げれば衿元や胸元がキレイに見えるのかを、衿幅のイメージができるように、5.5㎝幅に畳んだものを背中にクリップで留めています。
背中の衿幅と同じ5.5cm幅のまま「棒衿」にした場合のイメージです。
江戸前のチャキチャキしたような躍動感や普段着のカジュアル感があって、可愛らしさも出る衿幅です。
きもの風にも着たいと考えると、衿幅を広げた方が良いと思います。
既製品の浴衣の場合だと、6.5cmぐらいなので「棒衿」に比べても、あまり大きな差は感じないかもしれません。
※左側が「棒衿」で、右側が胸元あたりで衿幅が約6.5cmの「バチ衿」
さらに衿幅を広げて胸元で7.5cmぐらいの幅になると、きもの風に感じられると思います。
このように衿幅によって、着姿の印象に違いが出ますよね。
たとえば、礼装用の訪問着の場合、衿幅を広くすることによって、カジュアル感よりもフォーマルで優雅な雰囲気に感じられます。
また、衿を広くすることで、肩線が外側に移動するので、肩幅がスッキリと見える効果もあります。
ただ、身長が低い方や細身の方が衿幅を広くすると、バランスがよくありません。身長が高く、大柄の男性の場合には、衿幅を広げた方がバランスよく着こなせるはずです。また、女性も同じように、たとえば、とてもグラマラスな方は衿幅が広い方がスッキリと見えます。
このように衿幅による見え方の違いを踏まえて、浴衣での「ちょい広バチ衿」を提案しています。
きものの衿は、基本的には反物を半分に割った生地を使用して作ります。反物幅が40cmとすると、半分に割ったものが20cm幅の生地。その生地をさらに2つに折ると10cmあるので、縫い代部分を除くと、最大で9cmの衿幅を作ることができます。
ところが、9cmの幅となるとものすごく広い衿幅になるので、広げたとしてもせいぜい8cmくらいまでとなるでしょう。
ただ、できるだけ衿を汚したくないと衿幅を細くと思われるかもしれません。でも実は、衿を汚れにくくするためには衿幅で調整するよりも、衿を首からどれだけ離して着付けられるのかが大切です。
衿が首にくっついてしまう場合は、首の後ろの衿を横に広げるようにして着付けることで、首から衿が離れるので、衿幅を広くしても衿が汚れにくくなります。
普段着テイストを残しつつ、衿を入れることできもの風に着る場合には、身長や肩幅、胸幅によって、7~8cmぐらいで衿幅を割り出すのが良いでしょう。
背中心の衿幅が約5.5cmで、胸元に向かって衿幅をどのぐらいに広げると格好いい着姿になるのかを把握するために、自分で鏡を見ながら手持ちの広衿のきもので試してみても良いかと思います。
浴衣を浴衣として着たり、衿を入れてきもの風にも着たりと、夏のきものの楽しみ方に繋がれば嬉しいです。
女将による「ちょい広バチ衿」の動画はこちらをご覧ください。
【ゆかたをきものチックに楽しむ!ちょい広バチ衿のすすめ完全版】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
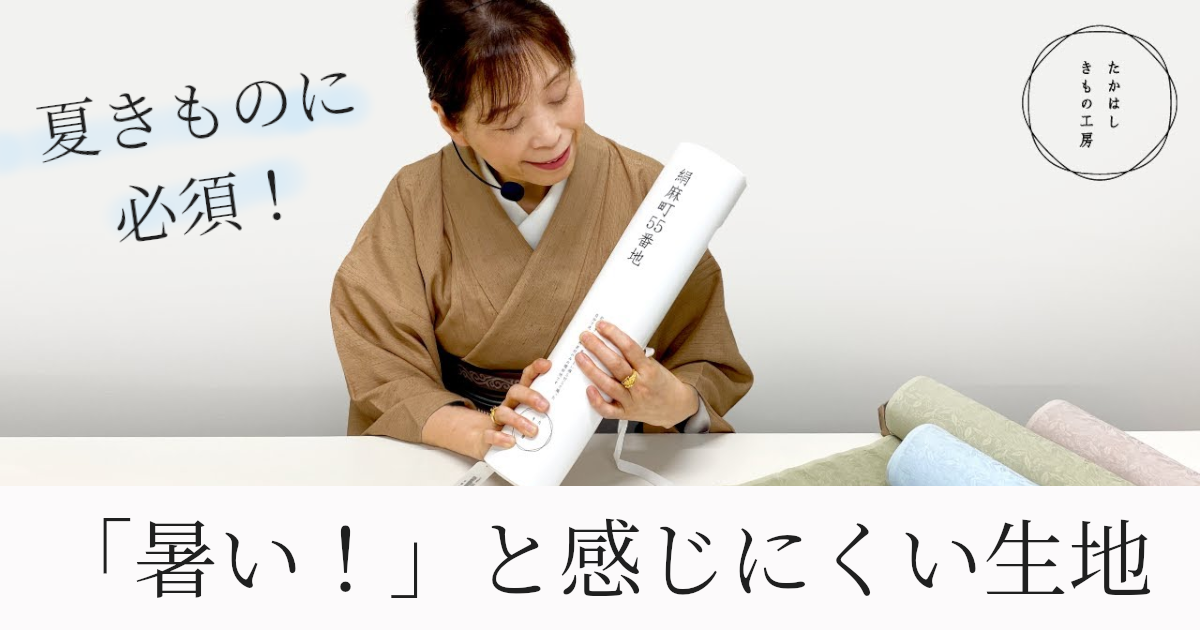
夏きものに必須!「暑い!」と感じにくい生地
昔に比べると、夏の気温がどんどん高くなっている感覚があります。そんな中でも、きものを楽しみたいという方にとって、どうすれば少しでも涼しく着られるでしょうか。
「涼しい肌着って、ありませんか?」こういったご質問をいただくことも、しばしばです。
そのため、たかはしでは、どうすれば少しでも不快感が軽減できたり、汗をたくさんかいてもお手入れが楽に済むか、暑く感じにくくなるのか、試行錯誤の中から生み出してきた商品がいろいろあります。
その中でも、今回は、夏に暑いと感じにくい生地について、ご紹介します。
一番の不快感、肌への張り付きを解消したい
きものを着ていて汗をかいた時、生地が汗でペタッと肌に張り付いて、その不快感と同時に、なおさら暑く感じるという経験をされたこと、ありませんか?
生地に凹凸が少なく、滑らかな素材だと、体に張り付きやすいです。
また、生地が体に張り付くことで、生地が肌と空気を遮断し、より暑く感じてしまいます。
この不快感を解消するために、体に生地が張り付かず、体と生地の間に空気を含ませるようにすることが必要だと考え、「絹麻町55番地」という襦袢地が生まれました。
絹と麻の美味しいとこどりの着心地の良さ
「絹麻町55番地」は、タテ糸に絹100%、ヨコ糸に麻100%の交織の襦袢地です。
※交織とは、違う素材の糸を用いて、織り交ぜている生地をいいます。
素材に絹と麻を選んだのは、絹の落ち感・ツヤ感・ゴージャス感という質感や着心地の良さを保ちつつ、麻の涼しさ・肌への張り付きにくさ・ざっくり感を程よく併せ持って、美味しいとこ取りができるのでは、と考えたからです。
その特長は次の通りです。
体に張り付かず涼しく、着心地良い
タテ糸に絹100%、ヨコ糸に麻100%にしたことで、絹の程よい落ち感のある着心地と、麻の張り付きの無さで涼しさを実現しています。
洗濯機で洗えて、アイロン要らず
ご自宅の洗濯機で洗うことができます。脱水も短い時間で良く、生地が濡れているうちに手で叩いてシワを伸ばして乾かすと、アイロン無しでもほぼキレイになります。
もちろん、アイロンをかけた方がキレイな仕上がりになりますが、かならずアイロンがけが必要というわけではありませんので、扱いやすいです。
柔らかものにも硬いものにも単衣にも使える
汗で体に張り付かないハリ感がありますが、程よい落ち感もあるので、柔らかものにも硬い紗のようなきものにも、単衣にも合わせることができます。
このような特長がある「絹麻町55番地」の絽の襦袢地を、ぜひ夏の襦袢としてその着心地を体感いただきたいです。
また、襦袢地としてだけではなく、生地の扱いやすさと体感の涼しさとを兼ね備えたオールマイティーな生地として使えるため、まずは「うそつき袖」からお試しいただければ、その着心地の良さを味わっていただけると思います。
プラスで涼しくするための居敷当て
「絹麻町55番地」の絽の襦袢は、透け感に問題が無ければ、居敷当ては不要です。
透け対策として居敷当てを付ける場合に、ダイレクトワッフル生地をおすすめします。
生地に凹凸があるので、きものを着る時に少し生地が引っかかる感じがあり、着はじめの頃は滑りが悪く感じることもありますが、涼しさは体感していただけると思います。
また、綿100%の生地で収縮率がほぼありませんし、使っているうちに生地の凹凸が無くなり、程よく滑らかになっていきます。生地の凹凸があるため、少しの膨らみがありますが、気にならなければ浴衣や襦袢などの居敷当てとして、涼しくお使いいただけます。
居敷当てを付けるかどうかのひとつの判断基準としてですが、きものにいつも居敷当てを付けている場合には、襦袢に居敷当ては不要です。きものか襦袢に居敷当てが付いていれば、ステテコだけでも透けることはありません。
光を下から当てて透けないかどうかの実験はこちらの動画をご覧ください。
【夏きもの”透ける”を検証!《最新版》】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
※たかはしでは、居敷当てはあくまでも透けの防止対策であり、生地の強度を増すためのものではないと考えています。
もし、これから夏のきものに挑戦する場合には、高温多湿な日本の夏は変えられないので、夏はきものを着ないこともひとつの選択です。少しでも暑さを感じにくく、涼しく楽しむには、何を一番の軸にして考えるのか、身につけるものを足し引きして試されるのが良いでしょう。
その中のひとつの選択肢として、「絹麻町55番地」の着心地とお手入れのしやすさを、ぜひお試しください。
「絹麻町55番地」の開発秘話もある女将による夏に暑さを感じにくい生地についての動画はこちらをご覧ください。
【夏きものに必須!「暑い!」と感じにくい生地】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
紹介した商品
洗える襦袢地 絹麻町55番地…
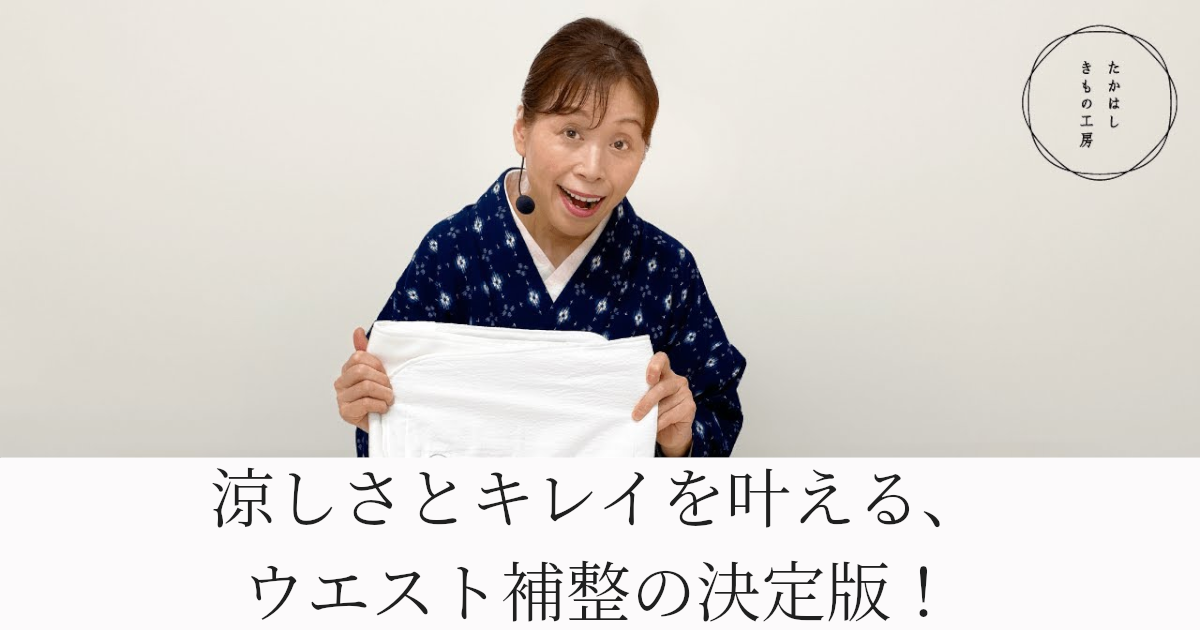
涼しさとキレイを叶える、ウエスト補整の決定版!
ウエスト補整にはどっちを使ったらいいの?
「ウエストの補整には、満点腰すっきりパッドスキニーと満点ガードル裾よけと、どっちを使ったらいいんですか?」と聞かれます。
※以下、スキニー(満点腰すっきりパッドスキニー)とガードル裾よけ(満点ガードル裾よけ)と表記
ウエスト補整で大切に考えていることは、骨盤を立てることです。
この「骨盤を立てる」というキーワードを中心に、スキニーとガードル裾よけについて、お伝えしていきます。
満点腰すっきりパッドスキニーの特長とは?
スキニーは、骨盤全体ではなく、骨盤の半分とウエストのくびれている部分を覆うように作っています。
スキニーを体にキュッと締めながら着けていくことで、腰肉とお腹のちょっとポヨポヨしたお肉を上に持ち上げるように締めることで、腰まわりのお肉を上げます。
そのように着けることで、骨盤が立ち、骨盤が立つと自然と体の前が開くような効果が確かにあります。
「満点腰すっきりパッドスキニー」の絶対的な特長は、
お腹のお肉を持ち上げる
腰のお肉を持ち上げる
ウエストと骨盤の高さを揃える
ハリを持たせる
紐が食い込まない
汗をとめる
というような効果が期待できます。
暑さ対策のため、極力生地が厚くならず、汗をきものや帯にうつさないように改良を重ねてきていますが、スキニーを着けると暑いと感じる場合には、避けた方が良いと思います。
では、このスキニーを着けたら、ガードル裾よけは要らないのかというと、そうではありません。
ウエスト補整に満点ガードル裾よけは不要?
ガードル裾よけは、お尻までキュッと引き締めてくれます。
腰まわりのお肉が締められてポタポタした感じがなくなると、お尻が引き締まって見え、より骨盤が立ちます。
ガードル裾よけは、骨盤を布の面で締めてあげることで、体がかなり楽になる、と感じていただけると思います。
ただ、感じ方は人それぞれ。「私はどうだろう?」と、ご自身の体感を大切にしてください。
ガードル裾よけの力布は放物線状になっているため、体に沿うように締められるようになっており、つるんと滑らない形になっています。
体が曲線ではなく直線になっているところの方が布地の止まりが良いです。生地目がピッタリと真っ直ぐな部分に当たっていくためです。
スキニーで補整をした上に、ガードル裾よけを着けることで、骨盤を気持ちよく立てることができます。
ガードル裾よけで使用している素材は植物系再生繊維・キュプラの薄手の夏織で、自信を持っておすすめできる涼しくて爽やかな着け心地です。
ただ、滑りの良い糸を使い、織りも平らのため、汗をかくと体に張り付きやすく、それが蒸れや暑さにつながりやすくなる、という一面もあります。
季節や気分で試すことがきものの楽しみの幅に
最初の質問の「満点腰すっきりパッドスキニーと満点ガードル裾よけと、どっちを使ったらいいんですか?」に戻りますと、これについてはどっちも良いのです。
スキニーで補整をした上でガードル裾よけを着けることにより、さらにキューッと骨盤が締まり、お尻までパンッと張った形になります。
スキニーを着けないで、ガードル裾よけだけ着けるということも、もちろんアリです。
季節によって暑さに耐えられないという場合には、スキニーもガードル裾よけも着けずに、ステテコだけ履くのが一番涼しいと思います。
かならず全部を身に着ける必要はありません。
季節によって、どこを一番のポイントにして選び取るのかは変わると思いますし、その日の気分でも変わると思います。
無条件にいつも同じものを選ぶというのではなく、季節やその日の気分などを考え合わせて、いろいろ試していくことで、それが自分にとってのきものの楽しみの幅になると思います。
「満点腰すっきりパッドスキニー」と「満点ガードル裾よけ」の使い心地では、骨盤を立てる点では一緒ですが、その効果・効用は違いますので、それぞれ選んでお使いください。
女将の満点腰すっきりパッドスキニーと満点ガードル裾よけの違いの説明動画はこちらです。
【ウエスト補整の決定版!満点腰すっきりパッドスキニーと満点ガードル裾よけの違い】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
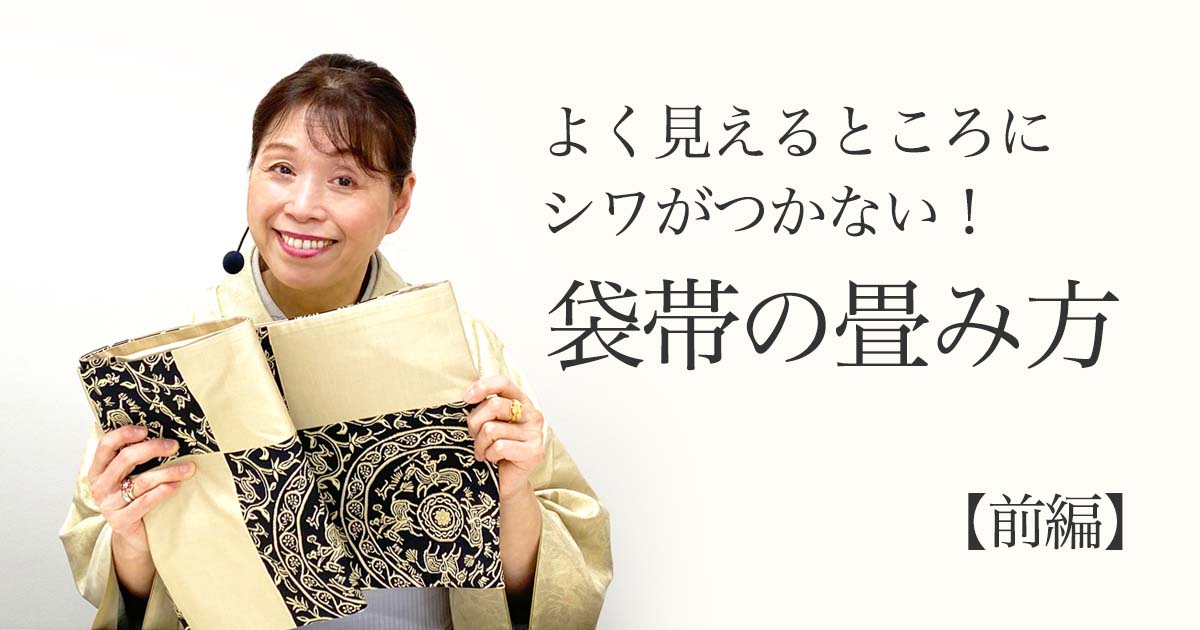
よく見えるところにシワがつかない袋帯の畳み方【前編】
お太鼓とお腹にシワを作らない!
皆様は、袋帯の畳み方どうされているでしょうか。なんとなく、とか買ったときの折れ線のまま、という方が大多数かと思います。
袋帯の畳み方で大切なのは2つ。
1)見やすいこと
2)お太鼓やお腹に折れ線が出ないこと
袋帯は、だいたい6等分に畳まれていることが多いのですが、着る人の体型はいろいろ。胴回りのサイズだけでなく、帯を閉める時のクセも違います。
久しぶりに出してみて結んでみたら、お太鼓の真ん中に畳ジワがカッキーン!と出てしまったり、前帯の部分に頑固な縦の折れ線があったり、なんて経験はありませんか。毎回アイロンをかけるのも面倒ですし、だいたいアイロンをかける時間もないときもあります。
自分がお太鼓にどこの部分を出したいか、また出せるか。自分のベストな位置の数字をまず知る必要があります。
だいたい数字で割り出せないの?と言われるかもしれませんが、人の体は十人十色。また出したい部分の好みも微妙に違っています。最初に1回測ってしまえば、次からはそれと同じにすればいいので、一度自分のお太鼓と前帯のベストな場所を確認しましょう!
まずは自分のベストお太鼓位置を知る
用意するのはクリップ4つ!
クリップで、前帯のお腹にくる部分とお太鼓にくる部分に印をつけます。
そして、帯を解いてたたみ直すのです。
まずは、前のお腹部分を起点に帯を半分に折り、端は長さが違えば片方をたたんで揃えます。
そのあと、三つ折りもしくは四つ折りにしたときに、お太鼓部分が折れないように調整すればOKです。
お太鼓のところが折れそうであれば、ずらして畳むとよいでしょう。
もしその時点で、折れ線が入っているようだったら、アイロンで伸ばしておきます。
また、帯の長さと自分のベスト位置を測って数字にしておけばリカバリーもききますし、他の帯にも応用ができます。
ピンチを挟んだ状態のときに、他の帯をそれに揃えて畳むのもいいですね!
平らに畳んで、畳紙に仕舞うときは、この畳み方でOK!
次回後編は、ズボラ女将がすぐ閉められてシワにならず、本棚みたいに立ててしまえてすぐ選べる!!
という禁断の(?)袋帯の畳み方をご紹介いたします!!
お楽しみに!
女将のわかりやすい袋帯の畳み方の説明動画はこちらです!
【袋帯を、美しく締めるために!よく見えるところにシワがつかない袋帯の畳み方】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
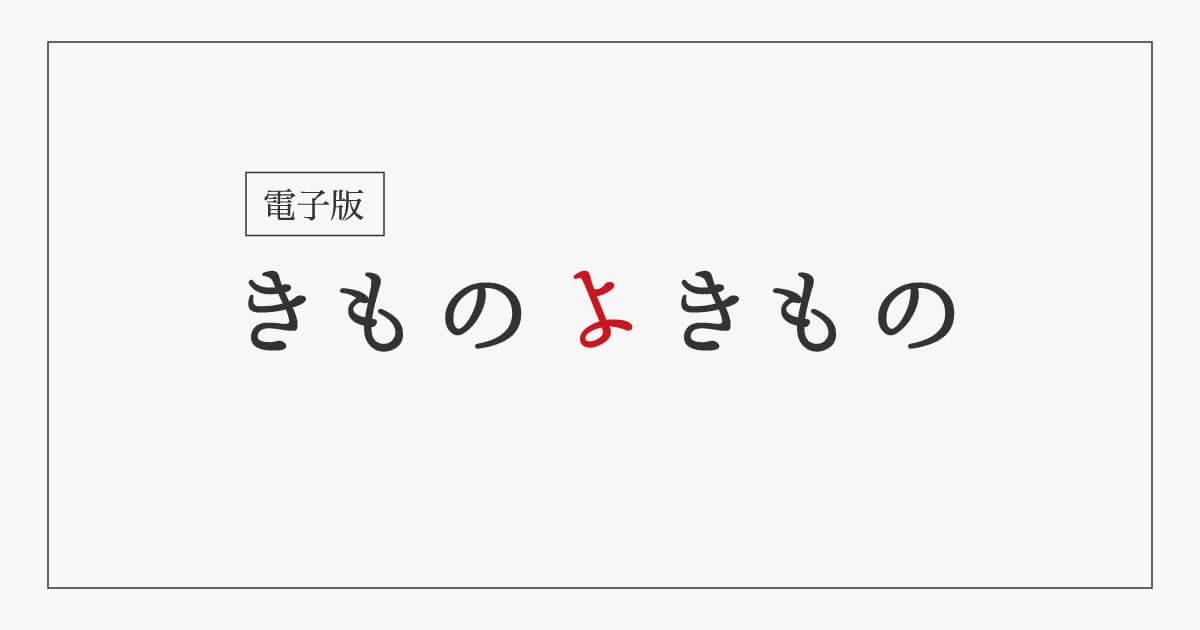
令和5年2月
あっという間の二月、新年が明けたばかりなのに…、と、いつも言ってる気がします。
歳を取ると、月日が経つのが早いと言いますが本当にそうですね。笑
さて、私がライフ…

和装ブラ選びのためのバストサイズの測り方
自分のバストサイズ、きちんと把握していますか?
きものの着姿の美しさは、下着で決まるといっても過言ではありません。きちんとボディメイクすることで、きものを着心地よく美しく、着崩れずに楽しむことができます。
下着選びに重要なのは自分のバストサイズをきちんと把握することからです。洋服だってブラをするけれど、意外と自分のバストサイズをすぐに答えられえる方は少ないのです。いつ測ったか忘れてしまった‥‥といわれることもしょっちゅうです。
また、実際測ってみようとしても、どこをどう測ればいいの? という疑問もあります。
今回は、和装ブラ選びに役立てていただきたい『バストサイズの測り方』をご紹介します。
ブラを選ぶときに自分のトップバストとアンダーバストをきちんと把握している人は少なくて「だいたいこれくらいかな〜」という感覚で選んでいませんか?
実際に接客させていただく時にブラジャーのサイズ、アンダーバストとトップバストは何センチですかと伺った時に、すらっと答えられる方は十人に一人いらっしゃるかな? という感じです。
和装ブラのサイズも、SML表示なのでだいたいでいいやと思いがちなんですけれど、最適な肌着を選ぶにはやはり、自分サイズをしっかり測っておいたほうがいいです。
特に大切なのはアンダーバスト
和装ブラ選びで重要なのはアンダーバストのサイズです。
アンダーバストの締め付けが強いと、苦しいものです。せっかくきものを着ていても、辛くて台無しになってしまいますから、自分のサイズをしっかり把握しておきましょう。
測り方は、バストの下の付け根の部分。これは、もし胸が下がっていたら持ち上げて、付け根の位置で必ず水平に測ってください。
斜めになると、その分数字が増えてしまいます。
そうして測ったアンダーバストを、サイズ表のどのサイズにあてはまるか探してみましょう。こちらがたかはしきもの工房のPut…

枕ひもで苦しくならない! コツのコツ
枕ひもを強く結ばなくても、お太鼓が落ちない方法
お太鼓結びをするときに欠かせない「帯枕」。
枕ひもを結んで止めるのですが、いつの間にか帯の中から上にあがってきて帯揚げを押し上げたり、締めすぎて苦しくなってしまったり、逆にゆるくて帯が下がってきてしまったり‥‥。
なかなか程よい枕ひもの結び方ができていない、ということはありませんか?
特に初心者の方に多いのですが、ぎゅうぎゅうに強く結んでいる場合。
帯が落ちてきてしまったら嫌だから、しっかり止めたいから‥‥。気持ちはわかりますが、枕ひもを強く結びすぎると、気持ち悪くなったり、肋骨が痛くなったり、グラマーさんだと胸が目立ってしまったりして、あまりいいことはないのです。
女将自身も、鳩尾あたりを締め付けることが嫌で、なんとか楽にならないものかと工夫を重ねて、伸びる枕ひもの「メッシュの帯枕 空芯才」シリーズや枕ひも、また「結ばないけど枕ひも」などを開発してきました。
それでも、枕ひもや胸ひもをきつく結ぶ人は多く、それが原因で「着物は痛い、苦しい」ということにもつながっているのではないでしょうか。人に着付けをしてもらったときも、着物が苦しい原因はこの胸元のひも類であることが多いです。
例えば、当社の商品で「三賢伊達締め」というものがありますが、これが生地が切れたということで返品を承ったことが何度かあります。最初は縫製不良かと思っていたのですが、返品していただいた商品を見たら、相当強い力で引っ張った形跡が見られました。
「三賢伊達締め」は引き締めるというより、適切にあてて摩擦で止めるものなので、ぎゅうぎゅうに締める必要はありません。
枕ひもも同じように、適切にあてていけば苦しくはなりません。
今回はその枕ひもの当て方をしっかり解説していきます!
枕ひもを3つのステップでしっかり帯の中に入れ込む
帯枕は、枕ひもを強く結ばないと落ちる、と思っている方が多いかもしれませんが、帯のテとタレが交差しているところに帯枕をきちんとのせれば、枕ひもをきつく結ぶ必要はありません。
ひもを結んだら、帯の中に深く沈めると、鳩尾にひもも食い込まないし、帯枕も背中にぴたっとつきます。
ただ、結び目を帯の中に押し込んだだけではすぐに上がってきてしまうので、以下の3つの手順でしっかりとひもを帯の中に入れ込む方法を試してください。
1)真ん中を、しっかりと帯の中に沈める
2)両脇も、しっかりと帯の中に沈める
3)最後にもう一度、さらに真ん中を帯の中に入れ込む
いかがでしょうか。これをすると枕ひもが上にあがってくることもありませんし、鳩尾も苦しくなりません。
<おまけ>
帯揚げをあらかじめ帯枕にかけておくやり方をなさる場合は、帯揚げで帯枕をくるんでしまってからひもを結ぶと、脇の部分の帯揚げがぐしゃぐしゃになってしまいます。
完全に包まないで、帯揚げの上2/5から1/3を折り畳んで帯枕にかけて、帯揚げが帯枕を1周するかしないかくらいにしておくと、脇がぐしゃっとならずに綺麗に仕上がります。
一度お試しください。
きものを楽に美しく着たいから‥‥「苦しい」と思う原因があったら、減らしてみませんか?
女将のわかりやすい説明動画はこちらです!
【きものの痛い!苦しい!を解決!枕ひも、キツすぎない?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…