投稿

いい着心地と着姿を叶える肌着の選び方
「どんな肌着を選んだらいいんだろう」と悩まれたことはありませんか?
何かを決めるとき、選択のための軸を持たずに決めることは、なかなか難しいと思います。
きものに限らずですが、主体性を持たないままでいる場合、誰かに教わらなくちゃという思いが強いのではないでしょうか。
たとえば、昔、学校の先生の言うことは聞きなさいと言われていたように、着付け教室や着付けの先生が言うとおりにしなければいけないと思ってしまうのも当然かもしれません。
ただ、これからは、自分がどんな風に感じたいのか、どのようにきものを着たいのかがとても大事だと思います。たかはしでは、それぞれの主体性を大事にしたきものの着方をおすすめしていますし、それを前提に肌着を作っています。
今回は、この視点であなたにぴったりの肌着の選び方について、ご紹介します。
ブラジャーをつけなきゃいけない?
ブラジャーは、かならずつけなきゃいけないと思っていませんか?
そんなことはありません。もし、つけたくなかったら、つけなくていいんです。
まず、ブラジャーをつけるにしても、何のためにつけるのかをしっかり、考えてほしいです。
自分でどれが気持ちいいか、どういうキレイさを望むのかを、一度、考えてみてください。誰かに言われたからこうするのではなく、本当に必要かどうかを考えてみてください。そして、もし必要がないと思ったら、なくていいんです。
たとえば、乳房にドロンッて重力が下にかかってくることで、気持ちがどよんとしたとします。この場合、ブラジャーで押さえた方がすっきりするし、気持ちがいいですね。
一方で、押さえ過ぎてぎゅっときつく感じるのは嫌だから、その間を選びたいと思ったとします。その場合は、たかはしの商品では「くノ一涼子」を選びます。
「くノ一涼子」は、下がってきたお肉をある程度サポートできますし、涼しさを優先される方にもおすすめです。
「くノ一夏子」の場合、まったく押さえる感じがなく、麻わたが入っているので胸の位置は目立たなくなります。
内側にポケットがあるので、詰め物を入れて調整することができます。そのため、体の厚みが薄い方は高くしたい場所にタオルなどを入れて調整してください。肩口にもポケットに入れられるようになっているので、全体にふわっとした厚みを出したい方のために作りました。ブラジャーではなく補整着のため、直接肌に着てもよい商品です。
たかはしの一番人気は「Put…

ここちよい着付けのために、補整する?しない?
きものを着付ける時に、補整をするのか、しないのか、ちょっとネット上を検索しただけでも、「補整は絶対した方がいい」とか「昔は補整してないのだから補整しなくて良い」とか、さまざまな意見が見られます。
たとえば、補整をせずに着る方たちの意見の中に、補整なしで着ると体型に沿って自然で良いという意見もあります。
一方で、そういった意見を聞いた方が、「私、補整してて、すみません」のような肩身の狭い思いをしている方がいるかもしれません。
着付けをするのに補整をするしないは、個人の自由なのですが、ここちよい着付けをするために、補整をしている方でも意外と知らない、たかはし流補整のイロハをお届けしていきます。
これから着付けを習う方や、習いたてというきもの初心者さんにも、ぜひ知ってほしい内容です。
「すっきり見える」だけじゃない補整をする理由
たかはしでは、「補」い「整」えるという字を使って「補整」をお伝えしています。
補整をする・しないは、どちらが上等かということではありません。
たとえば、自分にとって理想の着姿にするためや、自分にとって着ごこちのいい着付けに近づけるため、着付けの手間を減らしたいためなど、自分の好みに応じて、補整をする・しないを選ぶのが良いでしょう。
ちなみに、女将自身が「補整する・しない?」を聞かれたら、補整をする派です。
まず、補整をする目的として、全体的なバランスで考えた時、着姿がすっきり見えることです。きものを着るみなさんも望んでいることでしょうし、実は、すっきり見えるイコール着くずれしにくいんです。
たとえば、上半身が細くて、下半身にふわっと膨らみが出る体型をされている方。中年以降になると、特に腰まわりに浮き輪のようにお肉が付いてきやすいです。それ以外でも、上半身やウェストはすごく細くてお尻に向かって張ってきて、下半身にボリュームが出やすい骨格診断でウェーブ体型と言われる方がいらっしゃいます。
ウェーブ体型の方が、ウェストに合わせた上半身の着付けをすると、下半身のボリュームが強調される形になり、パーンとお尻が張って見えてしまいます。
この場合、ウエスト補整を入れることでお尻が小さく見える効果が得られます。
きものの生地は、タテ糸とヨコ糸が真横×垂直に重なって織られています。この生地目を意識して体に沿わせるようにすると、シワがよりにくくなります。
たとえば、裾を下すぼまりにしたい時、ウエストが細くてお尻が張っていると、お尻の部分で生地が引っ張られて歪みができます。そのため、最初は下すぼまりになっていても、歩くことで生地に力がかかっていくと、裾が開いてきてしまいます。
このように、お尻や太ももに張りがある体型の場合、裾が広がりやすいのです。生地の力にあらがって着付けているので、当然着くずれやすいです。
ウエストをお尻や太ももの張りに合わせて補整を入れ、できるかぎり真っ直ぐ寸胴にすると、生地がピタッと体に沿うようになります。
そのため、下すぼまりになった裾に対して、そのまま生地が上に上がるので歪みができにくいです。すると、生地の落ち着きが良くなり、着くずれしにくくなります。
さらに、一番気になるお腹の肉や腰肉は、帯を締めた後にぽっこり下腹として出てきてしまいがちです。たとえおはしょりを1枚にしてきれいにしても、立ち座りで腰に帯がぶつかって動くことで、上半身がブカブカと緩むことでも、着くずれに繋がります。
また、長い帯板を使うとどすこい体型に見え、帯板が腰にぶつかって着くずれてしまう場合があります。帯は細い部分に滑って移動していくので、帯と一緒に生地も動き、上半身の生地が緩みブカブカになって着くずれてしまいます。
お腹まわりのお肉が浮き輪のようにつき始めると、お肉を押さえこみたい気持ちになりますよね。
ただ、腰まわりのお肉を押さえ込んだとしても、ウエストが細いままだと腰まわりが張った状態になってしまいます。だから、ウエストに補整を入れていくと良いのですが、補整を入れれば入れるほど、太って見えることを心配されると思います。
そこで、補整の詰め物を多用せず、自分のお肉を持ち上げて、お肉を動かす、という新発想の補整を実現してくれるのが、「満点腰すっきりパッドスキニー」です。補整のための詰め物が少なくても補整が簡単にできるし、一発で補整が決まるという点も大きなメリットです。
パッドスキニーを、一番くびれているウエストだけ付けるのではなく、かならず骨盤にもかかる形でお肉をキューッと締めるように付けることで、お肉が動いていきます。(スポーツをされてきた方で筋肉質な方の場合、筋肉は動きにくいのでその上に補整を足すこともあります。)
自分のお肉がウエストの補整として入っていくため、パッドスキニーを使うとサイズダウンすることもあります。
仮に、補整は一切、付けなくて裾が広がってしまっても全然良いですという場合、それはその人の個性だと思いますし、ひとつの着方でもあると思います。
たとえば、補整を何もしなくても寸胴な体型ですという方もいますし、腰の曲線がなく真っ直ぐな方もいますので、補整が必要なのかどうかは、その人の体型にもよります。
下半身の補整を例に、お伝えしてきましたが、胸元を寄せて上げることも上半身の補整のひとつです。
胸のお肉が横に広がるような感じがする、下に落ちてしまうという場合、補整でお肉を上げることができたらすっきりと見えます。もし、胸のお肉をつぶして補整した方が良いと感じているのであれば、それが良いと思います。
かならず、こうしなければならない、ということはないのです。
大切なきものにも補整が効く理由
着姿や着ごこちに加えて、補整をすることは、きものを守ることにも繋がります。
タオルや補整アイテムを使用すると、その分、吸水性が上がるので、汗がきものに移ることを軽減することができます。
もちろん、補整をしたことで暑くて汗の量が増えるという側面もあります。
以上のことから、補整をする意味は大きくふたつです。
ひとつは、生地をすっきり体にまとわせることで着くずれを防ぐこと。もうひとつは、きものを守ることです。
着付けをするのに何を選び取るかは人それぞれです。これらふたつを考え合わせて、たとえば、補整を入れる量を季節によって調整するなど、考えると良いでしょう。
補整をする・しないは、上も下もなくフラットに考えて、自分の体に聞いて、選んでいくと良いと思います。
すべては自分の感覚と自分で選び取ったものを信じて、その上でここちよい着付けをされることで、もっときものを楽しめるようになると良いですよね。
ここちよい着付けをするために、女将の愛と理論と情熱がつまった動画はこちらをご覧ください。
【きもの初心者さんにも知ってほしい!ここちいい着付けの為に!補整ってしないとダメ?】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…
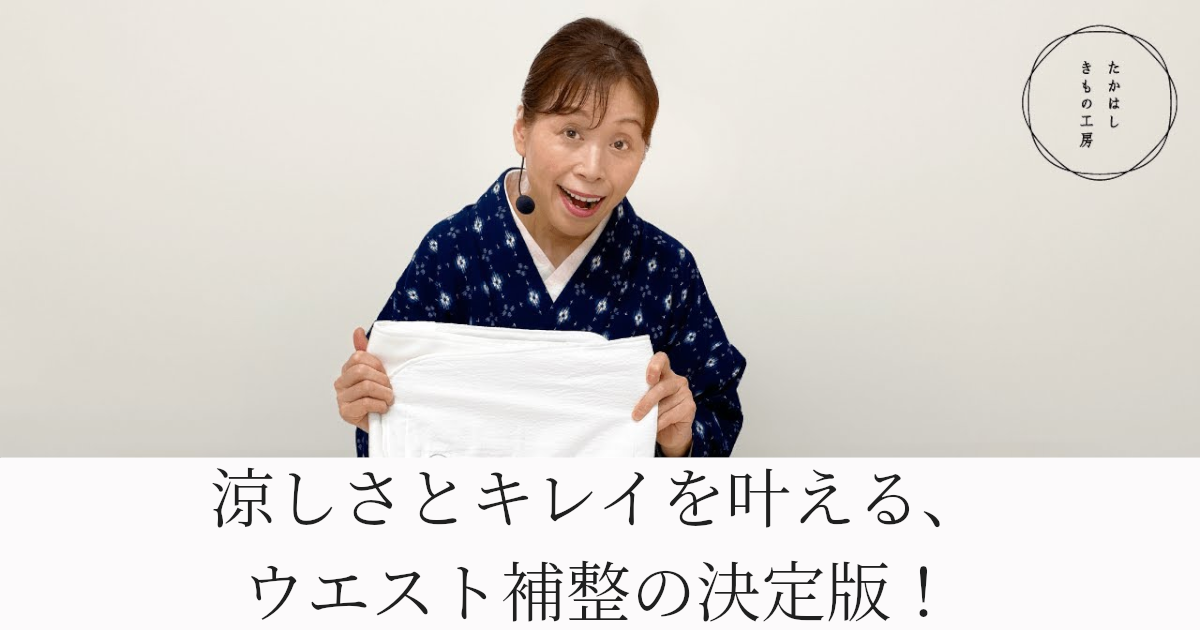
涼しさとキレイを叶える、ウエスト補整の決定版!
ウエスト補整にはどっちを使ったらいいの?
「ウエストの補整には、満点腰すっきりパッドスキニーと満点ガードル裾よけと、どっちを使ったらいいんですか?」と聞かれます。
※以下、スキニー(満点腰すっきりパッドスキニー)とガードル裾よけ(満点ガードル裾よけ)と表記
ウエスト補整で大切に考えていることは、骨盤を立てることです。
この「骨盤を立てる」というキーワードを中心に、スキニーとガードル裾よけについて、お伝えしていきます。
満点腰すっきりパッドスキニーの特長とは?
スキニーは、骨盤全体ではなく、骨盤の半分とウエストのくびれている部分を覆うように作っています。
スキニーを体にキュッと締めながら着けていくことで、腰肉とお腹のちょっとポヨポヨしたお肉を上に持ち上げるように締めることで、腰まわりのお肉を上げます。
そのように着けることで、骨盤が立ち、骨盤が立つと自然と体の前が開くような効果が確かにあります。
「満点腰すっきりパッドスキニー」の絶対的な特長は、
お腹のお肉を持ち上げる
腰のお肉を持ち上げる
ウエストと骨盤の高さを揃える
ハリを持たせる
紐が食い込まない
汗をとめる
というような効果が期待できます。
暑さ対策のため、極力生地が厚くならず、汗をきものや帯にうつさないように改良を重ねてきていますが、スキニーを着けると暑いと感じる場合には、避けた方が良いと思います。
では、このスキニーを着けたら、ガードル裾よけは要らないのかというと、そうではありません。
ウエスト補整に満点ガードル裾よけは不要?
ガードル裾よけは、お尻までキュッと引き締めてくれます。
腰まわりのお肉が締められてポタポタした感じがなくなると、お尻が引き締まって見え、より骨盤が立ちます。
ガードル裾よけは、骨盤を布の面で締めてあげることで、体がかなり楽になる、と感じていただけると思います。
ただ、感じ方は人それぞれ。「私はどうだろう?」と、ご自身の体感を大切にしてください。
ガードル裾よけの力布は放物線状になっているため、体に沿うように締められるようになっており、つるんと滑らない形になっています。
体が曲線ではなく直線になっているところの方が布地の止まりが良いです。生地目がピッタリと真っ直ぐな部分に当たっていくためです。
スキニーで補整をした上に、ガードル裾よけを着けることで、骨盤を気持ちよく立てることができます。
ガードル裾よけで使用している素材は植物系再生繊維・キュプラの薄手の夏織で、自信を持っておすすめできる涼しくて爽やかな着け心地です。
ただ、滑りの良い糸を使い、織りも平らのため、汗をかくと体に張り付きやすく、それが蒸れや暑さにつながりやすくなる、という一面もあります。
季節や気分で試すことがきものの楽しみの幅に
最初の質問の「満点腰すっきりパッドスキニーと満点ガードル裾よけと、どっちを使ったらいいんですか?」に戻りますと、これについてはどっちも良いのです。
スキニーで補整をした上でガードル裾よけを着けることにより、さらにキューッと骨盤が締まり、お尻までパンッと張った形になります。
スキニーを着けないで、ガードル裾よけだけ着けるということも、もちろんアリです。
季節によって暑さに耐えられないという場合には、スキニーもガードル裾よけも着けずに、ステテコだけ履くのが一番涼しいと思います。
かならず全部を身に着ける必要はありません。
季節によって、どこを一番のポイントにして選び取るのかは変わると思いますし、その日の気分でも変わると思います。
無条件にいつも同じものを選ぶというのではなく、季節やその日の気分などを考え合わせて、いろいろ試していくことで、それが自分にとってのきものの楽しみの幅になると思います。
「満点腰すっきりパッドスキニー」と「満点ガードル裾よけ」の使い心地では、骨盤を立てる点では一緒ですが、その効果・効用は違いますので、それぞれ選んでお使いください。
女将の満点腰すっきりパッドスキニーと満点ガードル裾よけの違いの説明動画はこちらです。
【ウエスト補整の決定版!満点腰すっきりパッドスキニーと満点ガードル裾よけの違い】たかはしきもの工房「ズボラ女将の和装の常識を斬る!」
更新情報はInstagramで発信していく予定です。
Instagramを登録されている方は、是非「たかはしきもの工房…

着付けに補整って必要?【きもの初心者必見】
こんにちは。きもの初心者の小野寺です。
2022年の梅雨はあっという間に過ぎ、東北の気仙沼ですら30度超えの日々が続いた日などありました。
そんな暑い日が続くと、どうしても少しでも涼しく着たい!着るものを減らしたい!となってしまい、着物に手が伸びにくくなりました…^^;
「補整しなければ涼しいのでは?」
と、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
でも、本当に補整がなくなれば涼しいのか、補整がないと大変なことってあるのでしょうか?
今回は、実際に試して感じたことを共有したいと思います^^!
普段の補整について
私は体型が痩せ型で、普段の補整はこんな感じです。
腰回り
…

何とかならない?着物で目立つぽこりん下腹【きもの初心者必見】
「体にお肉があるなら、痩せればいいじゃない。」って、痩せれるならやっているわけで( ノД`)
こんにちは。たかはし二年目&きもの初心者の佐藤めぐみです。
自分で着付けて出かけられるようにはなったものの、その着姿は…。
母:「あんだ、ちょっと瘦せだらいんでないの?」
※訳:あなた、少し痩せたらいいんじゃないの?
ある日、きもの姿の私を見た母の第一声(;'∀')
その同じ日。
女将:「めぐみさん、ちょっと太ったのかな?(着物が)縦縞だから目立つのかもしれないけどね。」
気仙沼にUターンしてから5年。気仙沼で美味しいものを心の向くまま食べ、自分を甘やかしまくってきた結果…移住前と比べて体重が自分史上最大の増加率。
もう「着物だと痩せて見えるね」も通用しないぞ(;'∀')<いや痩せようよ自分(笑)
頑固な下腹のお肉を亡き者にするには少々時間と努力が必要なので、補整でなんとかできないものか。助けてください、女将ぃぃぃ(…

太って見える着付けで再確認した紐の性質【きもの初心者必見】
たかはしに入社する何年も前から、たかはし製品を愛用していたきもの美人になりたい小野寺ペコ吉です。愛用していた、などというと、まるで着物を着慣れた人のようですが、なんのなんの。
反省はするが学習しない、という私の得意技で、何度、着物を着ようとも、今ひとつ着慣れた風情を醸し出せないまま年月ばかりが流れておりました。
それでもなんとか着物を着られているのは、やはり、かゆいところに手が届くたかはしの和装小物があったから。自社商品を誉めるのは手前みそではありますが、着付けのハードルをググッと下げてくれる相棒たちは、本当に手放せない存在なのです。
でも、なぜかうそつき衿が、ぶかぶかと浮いてしまう時があったり、腰回りがボコボコともたつきがちで、そもそものガッツリ体型が、輪をかけて相撲の関取が歩いているような着姿になることが多く、ずっと悩んでいました。
※ちなみに気仙沼弁では、大きくぶかぶかの状態をガフガフになる、と言います。
「帯がうまくできなくてぇ〜(>_<)」とか、「朝バタバタしていてぇ〜((+_+))」とか、言い訳にも疲れ果てました。
そもそもの着付けがまったくなっていないのもありますが、それにしても衿のガフガフと、腰回りのどっしり感をなんとかしたいな〜と、常々、思っていたのです。
女将が伝授!美しい着姿の土台とは?
先日、たかはしで小袋帯の結び方講習会があった時のこと。
帯結び以前に、会場にあらわれた私の着姿が気になった女将が、見るに見かねて「いーから、いったん着物を脱いでみて」と、相撲取りペコ吉を救わんと、名乗り出てくれました。
ごっつぁんです。
一番の問題点は、私自身が気仙沼の豊かな大地に育まれて、だいぶ肥大化したことです(/ω\)
「そんなことはわかってるから!」と、事もなげに女将にかたづけられつつ、着付けがなってない原因をひとつひとつ丁寧に教えてもらいました!
◎ペコ吉の着付け問題点…
